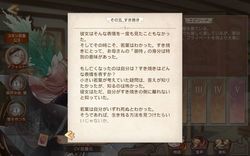すき焼き・エピソード
◀ エピソードまとめへ戻る
◀ すき焼きへ戻る
すき焼きのエピソード
常に華やかな服を着ている。
穏やかで誰にでも優しく接しているが、実は独占欲が強く、プライベートを何より大事にしている。
Ⅰ やってきた場所
ここの神がおわす場所には、歳を取らない女の子が住むという伝説を聞いた。
それで俺と若葉は近くの村までやってきた。
若葉は医者の家に生まれ、医術の腕はさほど高くないが、村民のよくかかるような病気なら治せる。
医者をしながら、伝説の地を探していた。
そして、俺たちは旅に出た。
若葉は御侍の子で、俺はただ「委託を受けた存在」だった。
幼くして父親を亡くしたせいか、子供の頃若葉は何かと理由をつけては俺のそばにいたがった。
その頃は今のように無表情でもなく、憧れに満ちた表情をしていた。
だけど、俺には今ぐらいの距離がちょうどいい。からかってやるのも楽しくなってきた。
「昔は霊薬なんかを探しにきたものだが、今はこんなでたらめな伝説のためにはるばるここまでねぇ…」
俺の言葉には嘲笑が込められている。
「若葉、何をしたい?」
「すき焼きには関係ないでしょ。」
やっぱりまだ子供…その口調からはそう思わざるを得ない。
「わかったよ。でもこのまま進んだら、そこのおちびさんを踏みつけちゃうぞ。」
その言葉を聞くや否や、若葉はすぐに立ち止まり、踏み出した足を空中でぴたりと止めた。
「ミャ」
近くの村の住民に聞いた道だった。
堕神の襲撃を受けた場所だそうで、人間の生活の痕跡がほとんど残ってない。
それなのに、こんな小さな子猫がいるとは。
若葉は何も言わず、出発時に村民からもらった煮干しを、猫の口元に持っていった。
「拾ってあげれば?」
俺は意外に思った。子供の頃はこういう小動物を抱いて帰ってきては、興奮して私に見せてくれる子だったのに。
今や俺の前では、素直な愛情表現をしなくなってしまった。
いつからだっただろう?
俺の前で「好き」という言葉を口にしなくなったのは…
子猫は食べ物をもらったお礼のように若葉の足にじゃれついた。若葉はそれを抱き上げようとはしない。
愛おしそうに撫でたり、そのような視線を送ったりすることすらない。
若葉は振り返らず何歩か歩くと、俺に背を向けてこう言った。
「縁がなければ、寂しくなることもない…」
その静かな言葉に、俺ははっとなった。彼女の語気に珍しく笑いが込められている。まるで俺をあざ笑うかのように。
「昔よく言ってくれた言葉じゃない?」
Ⅱ 目に見えるもの
ここは一面の楓林だった。若葉の家にあった大きな庭園ほどではないが、静まり返った緑色が赤く染まる頃には、つい過去を思い出してしまう。
ここは、若葉のかつての家と景色がそっくりだ。
ここを選んだ理由はもう一つあった。
温泉が湧いているのだ。
若葉はそれを聞くと、さっそくここに住むことを決めた。
協力を惜しまない村民たちのお陰もあり、私と若葉に安住の地ができた。
それ以来、ここは診療所のような存在になった。
村民たちは診療に来る時、よく食べ物を持ってくる。
若葉が薬草にかかりきりなったり、部屋にこもって医術の研究をしていても、衣食に困らなくなった。
だが、俺は若葉が何か隠していることに気が付いていた。
若葉はゆっくりと、俺の知らない若葉になっていく。
悲しいことだった。御侍と同じく、若葉も俺から去ってしまうのかと。
自分にはどうしようもできないことだったから、俺は不安になった。
「すき焼き、今日は若葉、家にいる?」
突然の来訪者が、俺の思考を遮った。
最近よく出入りするようになった女の子だった。若葉と仲が良いようだ。
来るたびに、大きな籠を抱えている。
「ああ、いるよ。」
俺はいつも通り笑って言った。
「じゃ、お邪魔します。」
女の子は嬉しそうに走って中に入っていった。
その背中を見ながら、彼女が若葉のよい友達になってくれればいいと願った。
一日、二日…日々は過ぎていく。
薬の香りがした若葉の部屋から、なぜかほのかな悪臭が感じられるようになった。
俺は若葉と話そうとしたが、「新薬を煮ているから邪魔しないでほしい」という返事が返ってきた。
俺は若葉ほど薬に詳しいわけではないが、それでも日に日に強まる臭いには不安になった。
俺の予感はすぐに的中した。
ある日、扉が乱暴にこじ開けられた。
「若葉先生はいらっしゃるかね?」
慌てふためいた顔をした男が、飛び込んできた。
「ただの熱だと思っていたんだが、3日経っても引かないし、顔にできものまで出ているんだ!」
その中年の男は、泣きそうな口調で私に伝えた。
そこで、俺は若葉を連れて行った。
その人と、以前通りかかった村へ向かった。
ボロボロの寝床の上に、顔中発疹と水疱だらけになった女の子が静かに横たわっていた。
俺は、その顔に見覚えがあった。
よく見てみると、毎日若葉のところへ来ていたあの子だった。
その瞬間、俺の隣に立っていた若葉の動揺が感じられた。
ああ、とても嫌なこの感じ……
御侍といい、若葉といい、俺はいつも、何もしてやれない。
顔を青くした若葉を見て、どんよりした無力感が心の底からあふれ出た。
一体…何が起きたんだ?
そう思いながら、俺と若葉は女の子の父親について彼らの家にやって来た。
「どうして…どうして?」
診療が終わると、若葉はつぶやいた。息が荒くなった女の子を、ただぼんやりと見ている。
そして突然何かを思い出したように、厳しい口調で聞いた。
「ここ数日、誰が彼女を看病していたの!?」
「私はよそへ出かけていて、ずっと妻が…」
父親は突然詰問してきた若葉に気圧されたようだった。
「奥さんは?」
「寝ているよ。自分も頭が痛いと言って……あ!も……もしや……」
その場全員が、予測できない事態の始まりを悟った……。
「すき焼き、私の部屋の引き出しに入っている箱を。」
若葉はそう言い終えると、父親ともう一つの部屋へ入っていった。
そのきっぱりとした眼差しと語気に、俺は抗うことができなかった。
昔の御侍そっくりの頑固さ。
俺はためらわなかった。
若葉の部屋の前で、異様な臭いを嗅いだ俺は再びはっきりと思った…
この扉を開けたら、何かが変わるかもしれない。
頭の中に、若葉の表情の一つ一つが浮かぶ。
その時の俺には、もはや選択肢はなかった…
Ⅲ 心の向かうところ
質素な部屋に、薄い薬草のにおいがする。
のはずだったが。
扉を開いたら、目に入るのは散らかっている光景だ。見たこともないものもあちこち置かれている。
「チューチュー」という声が部屋の隅から聞こえて来た。よく見ると、籠の中に閉じ込められた何匹かのネズミだった。
なんで部屋にネズミがいる?
お嬢様の若葉はこのような影に潜んでいる汚れたものに一切触れたことがない。
急に、あの女の子は若葉を見に来た時、毎回大きい籠を持っていた。
なるほど、そんなことか…
机の上の瓶や缶と薬草、及びまだ作る最中の杵とその上の薬の屑を見て、俺はようやくわかった。若葉はずっとこの部屋で薬を開発していた。
もっとも気になるのはその開けた本だ。
若葉が小さい頃に読んだ医術とかなり違っているようだが、本に書かれたものは全部この小さい机に置かれていた。
そして俺は視線を、試験体らしいネズミが入っている籠に移した。よく見るとその中に噛まれたネズミの死体もある。
とても衝撃だったけど、この場に一体なにがあったのか、まだわかっていない。
若葉はなんでこのような薬を作ったのか?その女の子の悪病となんの関係があるのか?
想像だけで答えが出ない。
御侍の要求で、戸棚の中の箱を手に入れるのが今のやるべきことだ。
扉の外に、俺と女の子の父親はずっと立っていた。
女の子の母親もその病気を伝染されたように、熱の下がらない状況になった。
幸い発見が早かったので、そんなにひどくなかった。
長く待った後、若葉はようやく部屋からでた。
「今後も彼女たちをこの部屋から離れさせないでください。そしてこれで毎日彼女たちが使ったものを全部ぬぐってください。」
若葉は先に俺が取ってきた箱を開いて、残る黄緑色の水薬を全部女の子の父親にあげた。
「これは?」
「これを使って彼女たちを消毒できる。病気に役立つから」
「ありがとう。若葉先生。」
薬を手に入れた男が必死に若葉に感謝していた。
でも、若葉の表情からわかる。
このことはまだ終わっていない。
でも、帰ったとしても、この前の疑問を口にしなかった。
「何があったのかを聞かないの?」
「君は医者だろう?病人を治療するのは当たり前じゃないか?それとも、あの色が怪しい水薬はなんだと聞いてほしいか?」
「あれは私が作った。本に書かれた通りに」
「ならいい」
「なんでいつも嘘をつくかな」
「嘘?」
「あなたが言いたいのはこれじゃない?違う?」
若葉は反抗期になったのか、俺に口答えをする回数も増えたが、今回みたいなのは初めてだ。
若葉はもう一度自分の部屋に引っ込んだ。
二日目の朝、彼女はその黄緑色の水薬を薬箱にいっぱい詰め込んだ。
そして声もなく急いで俺から離れて行くようにした。
「どこへ行く?」
「町に。」
「昨日あんな大量の水薬を、あの女の子の父親にあげたじゃないか?」
「うん、コホ…これらは町のみんなの分。」
「風邪か?」
「大丈夫、水薬を作った時ちょっとむせただけ」
「なんだって?」
俺の話がまだ終わっていないうちに、若葉は薬の瓶を開けた。すごく鼻をつく匂いが出てきた。
「ペストよ。あの女の子は私の部屋にいるネズミが噛んだから今の状況になった。」
「ペスト?!」
その病気の由来は詳しくないが、非常に面倒だということはわかる。それに、うっかり他人に伝染してしまうことも。
一刻の躊躇もなく、俺は若葉と一緒に町に行った。
そんなに大きい町ではない。そしてみんなが若葉を信頼しているから、彼女の言うことに従った。
あれから何日間、若葉はずっと頑張ってペストの病人を治療していた。
部屋にその鼻をつくにおいが満ちた。俺は簡単な補助をやっていた。
いつもより忙しくなった若葉を見て、家のため行医し続けたあの姿を思い出した。
「私はお母さんじゃないよ。」
若葉の声が聞こえた。
「わかってるよ〜小さな若葉だ……」
「でもさっきのあなたの目は、いままでお母さんを見てた目だ。」
「え……」
「コホ…知ってるわよ。昔の私もずっとあなたを見ていたから。」
若葉は薬草が浸かっている水盆を手に持って、淡々と俺に言った。
「ガチャン」
水盆が突然落ちた。その後に来たのはもう一つの重苦しい音だった。
反応の時間もなく、俺が振り返って見たのは、地面に伏せた若葉の姿だった。
Ⅳ 全部あなた
住処に帰った後、若葉を布団に休ませた。
ここの住む誰でも若葉を凄腕の医者と言っているが、この凄腕の医者が倒れた時、彼女を治療できる人はいない。
「コホ…コホ…」
間もなく、若葉は目覚めた。
「目覚めた…」
俺が安心したばかりに、若葉はすごく咳を始めた。
「まさか…君も…」
「コホ…私は医者よ。そんなに愚かじゃない。コホ…」
若葉の咳がますますひどくなって、血まで出てしまった。
「じゃなんで…」
「忘れたの?私の家族は代々奇病を遺伝している。お父さんはこの奇病のせいで亡くなった。あんないい人なのに、あんなに優秀な医者なのに、自分を救えなかった。」
若葉は言って、口元の血の跡を拭った。
「コホ…コホ…おそらく私もお父さんと同じになるね。」
「君は…いつ知ったんだ?」
「お母さんとあなたが話した時だよ。本当だと思わなかった。本当に救えなかったね…」
「君は自分の名前が若葉である理由を知っていたか?」
「お母さんが和葉なので、私が彼女のようになってほしいからじゃない?コホ…あなたもでしょう。私のことがお母さんに見えて、だからずっと側にいて…コホ…コホ…世話になってくれた。違う?」
「若葉は新しい葉っぱだ。御侍は君が生まれた時からずっと健康に成長できるように名付けた。」
「お母さんは私を愛していたのはもちろんわかってる。コホ…でも新しい葉っぱも老いる。私もこの世界の規律に従っているだけだ。」
若葉の声はちょっと掠れている。目に溜めた涙が決壊した。
「でも、死にたくないよ!本当に怖いよ!私が…コホ…あんなにたくさんのことをやって、町のみんなにペストの危険すら招いたのに…自分を救えなかった…コホ…コホ…」
若葉の泣き声は止まらない。彼女は昔の御侍と同じで、ずっと強がっている。
でも俺はもう一度見て見ぬ振りをした。俺はすべてを知っているのに、なにもしてあげられなかった。
必然的な結果だから、変えられないことだから、諦めた。
御侍と、きっと彼女を世話すると約束をしたのに。
「もうすぐ秋だ、一緒に紅葉を見に行こう…」
満面の紅葉、それは若葉と御侍が大好きな風景だった。
でも御侍が紅葉の中に倒れたあの日以来、若葉はほとんど見に行かなかった。
だから、若葉がここに住む理由は、それも一つだろう。
その後、若葉の体が想像できない速度で悪化している。
俺ができることは彼女に付き添うしかない。
ある日、俺が若葉の意思に従って、全ての研究資料とペストに感染したネズミを全部焼いた。
その中に、若葉が救いをもらえると信じた本もあった。
その本の表紙にある二匹の旋回している黒い蛇を見て、落ち着かない俺が彼女にこの本の由来を聞いた。
その本は誰からもらったのか。
だが若葉の答えはとても簡単だった。
一人の旅の商人が他の国に手に入れた神秘の医書と言って、彼女にあげた。
若葉はずっと生きられる方法を探していた。
人魚の伝説でも、あちこちの神の伝説も、根拠のないうわごとばかりだった。
だからこの本は彼女に希望を与えた。
だが最後は彼女の希望を叶えなかった。
若葉と共にいた最後の日。
楓は俺達と約束したように、赤くなった。
若葉が小さい頃に戻ったように、疑り深い目で俺を見た。
「すき焼き、最後に一つ聞きたい。正直に答えて」
「何?」
「私のこと好き?意味がわかるよね。」
「…うん。もちろん…好きだ」
俺は微笑んだ。
最後までも、彼女に素直になれない。
「この…嘘つき…」
若葉は笑った。だが目に涙がいっぱいだった。
「でも…ありがとう…」
気に入った答えをもらったように、若葉は目を閉じた。涙も顔に表れた。
それから、若葉は目を覚まさなかった。
その後若葉を、彼女の母親が大好きな楓の森に埋葬した。
この空っぽな住処を見て、心の中にも一つの空白が出たようだ。
「にゃー」
猫の声が近づいている。
すぐ俺の前に出た。
その見慣れた模様は、まるでここに来た時に若葉に食べ物を乞うた子猫のようだ。
こんな大きくなったのか。
「俺達についてこなくてよかったな。俺達と関わると全て消えてお終いになるからね」
「全部消えるの?じゃ、君も消えるの?小夜みたいに…」
後ろから薄ら寒い声が聞こえた。
後ろに向くと、一人の青い羽織を着た青年がそこにいた。懐に全身黒い猫を抱いていた。
「消えないよ。せめて今はない。」
なぜか自分の心の虚しい感じを隠そうとしていた。
「ここに住んでいるのか?」
「ああ、本当の主はもういないけど……」
俺は扇子を開いて、気づかれないように聞く。
「あなたは?何しにここに来た?」
「彼女との約束を果たしている」
「彼女?」
「うん、もう戻ってこない人なんだ。」
「余計な約束は寂しさを増やすだけでは?」
思わず笑った。
「じゃ、なんで君は泣きそうな顔をしているの?」
彼の声は相変わらず何の感情もない。初めて会った人にこんなことを言われるとは思わなかった。
「ここはいいね。こんなに美しい紅葉が見える。君はどう思う?」
目の前のこの人は優しく猫を撫でて、彼女に聞いているみたいに。
そして彼は俺に聞いてくれた。
「ここは何という場所ですか?」
「紅葉小舎と呼んでいい」
夕暮れに染められたように赤き森を見て、彼に言った。
なぜか、ここに捨てられない感情が浮かんだ。
ここに留まるのも一つの選択肢かも。
寂しさを感じるのは、誰かと絆を結びたいから。
でも、それは俺の言い残しだ。
Ⅴ すき焼き
とある寒い冬の夜、和葉という御侍が初めて彼女の食霊を召喚した。それはすき焼きだ。
「俺を召喚したのは君か?今後はよろしくな」
淡い香りがする美しい男が微笑んで言った。
「よろしくおねがいします」
和葉も笑って答えた。
御侍の傍にいたのは、約五、六歳の女の子だった。
「私の娘の若葉です」
若葉は和葉の背後に隠れてすき焼きを覗いた。
彼の美しい外見は、小さな若葉は讃嘆の言葉すら見つけられなかった。
「はっくしょん」
すき焼きは開いた窓からの寒い風に咳き込んだようだった。
「あ!まさか今は冬なのか!」
すき焼きが寒がる様子を見て、若葉は部屋の扉と窓を全部閉じた。
そして急いで箪笥からたくさんの厚くてきれいな着物を取り出して、すき焼きにあげた。
「俺は食霊だから、大丈夫だ」
とすき焼きは断ろうとしたが、その安心と甘味を感じる声で言ったことを若葉は疑いなく信じた。
だが彼女は依然としてその着物を全部すき焼きに固執してあげた。
「お母様が言った。この服は全部若葉の将来の結婚用の誂え物だ。これらをあなたにあげたら、若葉のお嫁さんになってくれる?」
「若葉、それは……」
御侍の話を待たずに、私は答えた。
「いけないね。若葉は女の子だよ?」
子供はその天真爛漫の様子で歳に合わない発言をした。すき焼きは特に気にせず、微笑んでごまかした。
これはすき焼きと若葉の初対面だった。
あの歳、若葉は6歳で、和葉は24歳だった。
だが歳を取るに従って、冗談だった発言はまだ終わっていなかった。
若葉はもう立派な少女となったが、すき焼きへの愛慕の心は全然減っていなかった。
医術一族に生まれた若葉は素質が良かったが、医術を勉強する気がなかった。
女の子だが、若葉は小さい頃から当主として育てられていた。
しかし若葉は毎日すき焼きについていた。すき焼きは父親のいない若葉が自分に甘えていると思って、彼女を気ままにさせた。
御侍はすごく困った。
だが若葉はすき焼きの話しか聞かなかったので、御侍はよくすき焼きに若葉のことを相談した。
若葉とお父さんがあんな病を持つことも、その時に知らされた。
そしてその時に、すき焼きはこの一族が表のように華やかではないことをだんだんと知った。
服と食料はいいものだが、若葉が4歳の時に、当主であった父親が遺伝病で亡くなったあと、この一族は以前よりもすでに没落していた。
規模は結構大きかったので、その当主を狙う人も少なくない。
それにあの時の若葉は当主の地位を受け継ぐ気は全然持ってもいなかった。そのため次期当主の地位を守ろうとした御侍は家族の他人事に困惑させられた。
「若葉はまだ幼いんだ。彼女はこれらに意味を感じてません」
その紅葉に染められた季節に、御侍が庭の前の楓の樹の下で、すき焼きにこういった。
「私が彼女にできることは、私が離れる前に彼女に全部教えていって、彼女が自分を自ら守れるように」
何かが起こるのを知ったかのように、この御侍が笑っているのに、すき焼きは何となく悲しくなった。
「彼女には健康に暮らしてもらいたい。でも私が亡くなっても、若葉の傍にはあなたがいる」
御侍の話には、それまで見えなかった感情が透けて見えた。
「うん、ちゃんと世話をする」
すき焼きは目の前の人の願いを拒めなかった。
「縁を結ばなぬ、寂しさを増やすのみ」
彼女は人間、俺の御侍で、いずれ離れる……とすき焼きは思った。そして彼はこの、自分でもよくわからなかった感情から逃げた。
だがそうすればするほど、逃げ切れなかった。
いつの間にか、すき焼きの視線にこの一人で家族を支えた女性の後ろ姿しかなかった。
深い感情ではなかったが、気になっていただけだ。
その御侍が自分の子のため、このすでにばらばらになった家族のため、どこまで堪忍できるかを、気になっていた。
そんな生活はその日までだった。それはせっかく一緒に紅葉を見に行った日だった。
すき焼きと若葉が見たのは、一面の紅葉の葉に倒れて、目覚めない御侍だった。
不健康にやせ細る顔は、紅葉が引き立てていても、美しさを増やさなかった。
もともとピッタリの着物なのに、その時も分けのわからない広さと混乱のみだった。
若葉の泣き声が途絶えずに耳に響いた。すき焼きは何の反応もできなかった。
結局こうなったね。人間と食霊の絆はそれだけだった。
思った通りの結末で、すき焼きはとても苦しかった。
彼が思わなかったのは、本当にあの時が来たら、彼は彼女のために泣くことすらできなかった。
俺は最悪の食霊だな。
と思ったら、すき焼きは思わずちょっと笑った。
あの年、若葉は14歳で、和葉は32歳だった。
母親の死はようやく若葉に死の恐怖を知らせた。
そしてその時に、彼女はすき焼きのいままでにない表情を見た。
あれは泣くよりさらに悲しむ笑顔だった。
彼女はそんな表情を一度も見たことがなかった。
そしてその時こそ、若葉はわかった。すき焼きにとって、お母さんの「御侍」の身分は特別の意味があった。
もし亡くなったのが自分では?すき焼きはどんな表情を表すか?
小さい若葉が考えていた疑問は、答えが知りたかったが、知るのは怖かった。
彼女はただ、自分がすき焼きの傍を離れないと知っていた。
若葉は自分がいずれ死ぬとわかった。
そうであれば、生き残る方法を見つけたらいいじゃないか。
御侍が亡くなった後、若葉は別人に変わったように、医術を勉強し始めた。すき焼きにも昔のように親しくしなかった。
それでも、若葉も一族から受け入れられていなかった。
まもなく、若葉はこの家から離れた。
すき焼きも約束した通りに、若葉と一緒に離れた。
◀ エピソードまとめへ戻る
◀ すき焼きへ戻る
Discord
御侍様同士で交流しましょう。管理人代理が管理するコミュニティサーバーです
参加する-
-

-
副管理人
-
-
-

-
副管理人
-
-
-

-
ななしの投稿者
312019/05/20 23:10 ID:ma1z4w9a12/12 最後です。よろしくお願いします!
-
-
-

-
ななしの投稿者
302019/05/20 23:09 ID:ma1z4w9a11/12
-
-
-

-
ななしの投稿者
292019/05/20 23:08 ID:ma1z4w9a10/12
-
-
-

-
ななしの投稿者
282019/05/20 23:08 ID:ma1z4w9a9/12
-
-
-

-
ななしの投稿者
272019/05/20 23:07 ID:ma1z4w9a8/12
-
-
-

-
ななしの投稿者
262019/05/20 23:06 ID:ma1z4w9a7/12
-
-
-

-
ななしの投稿者
252019/05/20 23:06 ID:ma1z4w9a6/12
-
-
-

-
ななしの投稿者
242019/05/20 23:05 ID:ma1z4w9a5/12
-