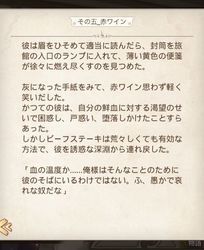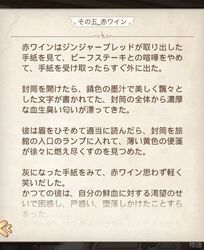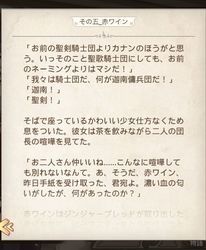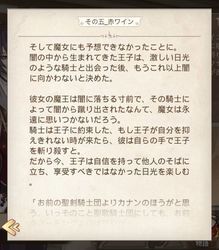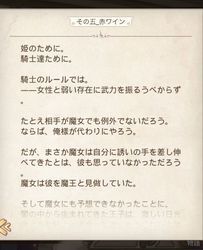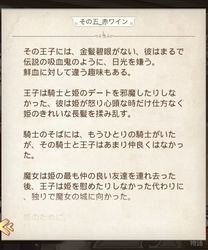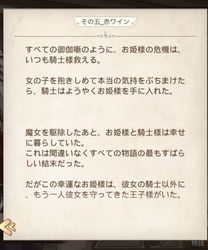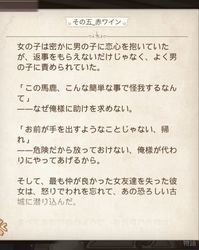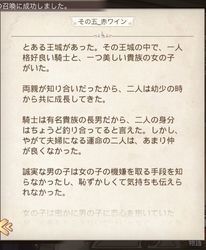赤ワイン・エピソード
◀ エピソードまとめへ戻る
◀ 赤ワインへ戻る
赤ワインのエピソード
高飛車な赤ワインは自分の実力に絶対的な自信がある。
剣術に精通しており、敵が気づかないうちに
戦いを終わらせるほどの腕前。
普段は華麗な服装とアクセサリーを好み、
非常に贅沢である。
陽の光が直接入る場所を嫌う。
Ⅰ.衝突
俺様はかつて、もし自分の御侍を認めることができなかった場合、どうすればいいのかなんて考えたことがある。
だが、俺様を召喚したこの少女は、不思議と俺様を満足させた。
公爵の娘が持つのは贅沢な生活だけではない。
内面から溢れる気品、微笑みの中のとした自信、凡人を惹きつける話し方、自宅の玄関から街の外まで続く求愛者の列。
これらは全て、彼女が首につけている輝く宝石がはめ込まれたネックレスがもたらすものでも、華麗な礼服がもたらすものでもない。
貴族とは高価な服を着て、贅沢な生活をしていれば名乗れるものではない。気品と自信を持たない貴族は、贅沢な品を積み重ねて作られた中身のないおもちゃに過ぎない。
俺様を召喚した少女は、鳥の羽で飾った精巧な扇子を手に、俺様の周りを何度も廻り、じっくりと観察した上で、ほっとしたようだ。
「ふぅ――よかった!鈍重なヤツが召喚されるんじゃないかって心配してたのよ。あなたはなかなか見栄えがいいわ。
まるでおとぎ話の中の吸血鬼みたい」
そう話す彼女の目には不思議な光が宿っていた。
「ふん、あいつに見せびらかしてやりたいわ。私だって食霊を持つ御侍になったって。それに私の食霊はあいつのなんかよりずっと素晴らしいって!」
その後、俺様は彼女の心の中のつっかえが取れ、ほっとした気分になった理由を知ることになった。
服のセンスが絶望的で、まったくの礼儀知らず、立ち振る舞いもひどく荒っぽい食霊を目にし、俺様の眉間に無意識に皺が寄った。
その後、御侍の口から聞いたところによると、その粗野なヤツはビーフステーキという名で、彼女のフィアンセの食霊なのだという。
「やっぱり持ち物は持ち主に似るのね。でしょ?赤ワインもあの人たち嫌いでしょ?」
「彼と結婚しなければならないなんて、御侍様も大変だな」
「だ、黙りなさい!誰があんな男と結婚するものですか!荒っぽくてロマンチックじゃなく、この私にまったく無関心なんですから」
「……そいつが荒っぽいかどうかなんて関係あるのか?お前たち、政略結婚だろう?」
「黙りなさい!」
赤い顔をしていた御侍を見て、俺様はグラスの中で煌めいている赤い酒を少し嗜んだ。
女の言葉は本心と違う。
俺様は葡萄棚の影にもたれ、未来の夫婦がちょっとした言葉が原因でケンカを始めそうになるのを目にし、思わずため息を吐いた。
この二人、結婚までにはまだしばらくかかりそうだ。
次の瞬間、人を嫌な気分にさせる影が俺様の目の前を通り過ぎ、二人の元へ向かおうとした。
俺様が手を広げて行く手を邪魔すると、そいつは赤い瞳でまっすぐにこっちを睨んできた。
「どけ」
「どこへ行くつもりだ?」
「町の外にまた堕神が現れたから、御侍を呼びに行くところだ。邪魔をするな」
「二人がデート中なのが見えないのか?この町に料理御侍は他にいないとでもいうのか」
「デートより堕神の方が大事だ。そこをどけ!」
俺様は腰の長剣を抜いて眼の前に立てた。暴力で解決したくはないが、目の前のこいつには我慢ならない。
このビーフステーキとかいうヤツは、言動といい、着るものといい、いちいち人を苛立たせる。ただ、剣の腕前だけは突出している。
「おいビーフステーキ!お前たちまたケンカか!」
「どいてろ!今日は必ず決着をつけてやる!このキザ野郎が!」
「お前はとばっちりを受けないようにちょっと離れてろ。俺様はずっと前からこの礼儀知らずをギャフンと言わせてやりたいと思っていたんだ」
「お前たちホントに気が合うなあ~毎日会ってるのにまだそんなに仲がいいなんて」
「黙れ!」
「黙れ!」
Ⅱ 血
御侍には、よく一緒にお茶を飲みに出かける友達のグループがある。メンバーには御侍に比べておしとやかで純真な女が多い。
その中の一人は初めて俺様を見た時、驚いて飛び上がった。そして付き添いできた執事の背後に隠れ、ビクビクしながら聞いた。
「あなた、吸血鬼なの?」
「なんだと?お前、怖いのか?」
「こ、怖くなんてないわ」
その頬を赤らめた娘は純真そうな輝く目をしており、俺様は彼女のことが忘れられなくなった。
しかし、その子はいなくなってしまった。
ある日のパーティーの後、馬車に乗った彼女は家に戻らなかった。
王都では最近、貴族の少女が行方不明になるという事件が増えている。この事件の担当者がまさに御侍のフィアンセだった。
彼女には分かっていた。失踪した娘が危険に晒されているということを。
もちろん、俺様たちが彼女に危険なことをさせたくないと思っていることも。
「私が囮になってもいい。あなたたちがしっかり守ってくれるから。お願い。彼女を傷つけた人間を自分の手で懲らしめたいの」
俺様はこのとき初めて、彼女がフィアンセに頭を下げるのところを見た。
ただ、予想通り――
「この件は君とは関係ない。関係のない者を事件に巻き込むわけにはいかない」
俺様はその時、彼が袖の下で手を固く握りしめているところを見た。この男は決して、自分の愛する女を危険な場所に行かせるようなことはしない。
ビーフステーキの御侍はビーフステーキと同じで、女の気持ちが全く理解できない。
不器用な男は愛する女性に自分の気持を伝えることが苦手だ。
バカのペアだ。
ただ俺様はこのバカどもが決して嫌いではない。
この敵は俺様が討ってやろう。
恐らく、多くの人間から吸血鬼と呼ばれるようになったせいで、俺様は血の匂いにとても敏感になってしまった。
一部の人間の血は甘い匂いがする、また別の一部はどこか苦い匂いがする。
さらに吐きそうなほど腐ったような匂いがする人間もいる。
だから、あの美しくきらびやかな貴族の夫人が優雅で知性的な笑顔で御侍と挨拶をしていた時も、俺様はどれほど香水を使っても隠しきれない匂いを感じ取っていた。
そして意外なことに、彼女の名がつけられた古城には簡単に入れた。
連れ合いを失ったその伯爵夫人は寂しさを紛らわすため、いつも自分の城で様々なパーティーを開いていた。
俺様は階上からの熱い視線を感じた。あの夫人は濃厚な血の匂いを身にまとい、熱狂的とも言える目でじっと俺様を見ていた。まるで彼女の願望を満たすことができるものが俺様の体の中にあるかのように。
なぜだかわからないが、俺様はその時突然、王国に伝わるある怪談を思い出していた。
不老不死で光を拒絶し、血液を飲む、暗闇の貴族。
彼女も俺様をあの伝説の中の存在に見立てているのだろうか?
俺様は何の力も持たない夫人のことを心配する必要はない。俺様たちが視線を交わした時、彼女の目の中に喜びの光が宿るのが見えた。
すると間もなく従者の一人が他の人々の視線を避けて俺様の元へやってきた。
「奥様が上の階で一服してはいかがと申しております」
手に持っていたグラスを置き、ダンスを楽しんでいる男女を恭しく避けながら二階へと上がっていった。
暗い色の礼服を着た夫人は威厳に満ちた姿勢で俺様の目の前に立ち、微笑みかけていた。
「失礼をお許しください。書斎でお話をしましょう」
彼女は俺様を吸血鬼と誤解した最初の人間ではない。しかしそんな俺様に会って、嬉しそうな顔を浮かべた初めての人間だった。
Ⅲ 血の温度
俺様達が書斎に入る前、俺様は微かに、一つの影が書斎を離れたのが見えた。遠く離れたところからでも、彼の体にある吐き気がするほどの濃い血生臭い匂いが漂ってきた。
俺様は吐き気を我慢して伯爵夫人について書斎に入った。
そしてその女性は書斎の扉が閉まるなり、その端正で温和な姿勢はすぐ崩れた。
彼女は熱狂的と言えるほどの態度で俺様の手を握って、俺様が聞くまでもなく、自分から今までやってきたことを全て話した。
自分の若さを保つために、彼女は自分で選んだ少女を宴会から連れ去った。
少女の血が彼女が言う効果抜群の保養品となり、そしてその可哀相な少女たちは永遠に冷たい墓の中に閉じ込められた。
彼女が俺様を探す目的も、一目瞭然だった。
伝説の吸血鬼族は、不老不死と言われている。
更に重要なのは、彼らはとある方法で普通の人類を彼らと同じような存在に変えることが出来る。
俺様の特徴は、その伝説の存在とかなり似ていることは否めない。
これはまさに彼女が夢見た不老不死だった。
彼女は興奮しながら俺様に話した、彼女は少女たちを誘拐し続けてもいい、彼女たちの鮮血を供物として俺様に捧げると。彼女がこの古城のすべての部屋を日の光が当たらない場所に建ったのは、いつか俺様がここに来るための準備だった。
俺様は目の前のこの哀れな人類を見て、思わず手を上げて、彼女の髪を耳の後に挟んだ。
それを喜んだ彼女は、俺様が本当に彼女が求めた吸血鬼かどうかも確認せずに、すべてを俺様に教えた。
だがこの愚かしさに対して、俺様は同情を持たなかった。
「以前攫った娘たちはどこに?」
「彼女たちはすべてあなた様の供物になりました!残り少ないですが、全て私にお任せ下さい!すぐに新しい供物をお持ちします!」
「すべてが……」
「はい!細心の注意を払ったから気づかれることはありえません!ですからご心配なく、これからの食料は、あなたの忠実な下僕であるこの私が調達致します!」
彼女の期待に満ちた目を見て、俺様がふとあの日執事の後ろに隠れ顔を赤くし、盗み見てたあの娘のことを思い出した。
もう、間に合わないか。
どうやら俺様は貴族に足りないらしい。優秀な貴族は、優秀な女性の期待に応えるべきだ。
「伯爵夫人、恐らくあなたの計画は失敗するでしょう。あなたの体内の血液は、とっくにあなたの魂と一緒に腐った。ゴミ箱の中身より臭いあなたは私の下僕になる資格はない」
こんな徹底的に腐ってるような存在は、真相を知る権利がない。
あなたは絶望の中で自分がしてきたことを懺悔するといい。
俺様は長剣を抜き出し、信じられないような顔をしている彼女の胸に刺した。
温かい血液が胸元から徐々に広がり、歓喜の光を放っていた目が少しずつ焦点を失った。
痛みで泣き叫ぶことすらできずに、彼女はこの世を去った。
俺様はベッドに横たわって、徐々にシーツを赤く染めていく死体を見て、手を伸ばして彼女の両目を閉じた。
血の匂いが空気の中で拡散している。俺様は胸を押さえて、血液に対する渇望を押さえ込む。
こんなものに誘惑されてはダメだ。
こんな気持ち悪い血液なら尚更だ……
その時、騒ぎ声が聞こえた。床すら揺れ始めた。
俺様は書斎を飛び出してダンスパーティー会場に向かった。
まだ会場に到着していないうちに、慣れ親しんだ腹立たしい叫び声が聞こえた。
「赤ワイン!出てこい!ここにいるのはわかっている!お前があんなゴミにやられるはずがない!さっさと出て来い!」
俺様は歯を食いしばってホール二階の階段に着いた、しかし目に映った光景がステーキに落とし前をつけてもらうことを吹き飛ばした。
俺様の御侍がいつの間にか華麗なドレスに着替えて、ダンスパーティーに紛れ込んだ。
一目で分かった。たとえ仮面をつけていても、彼女は容易く注目の的になる。
そして彼女の側には、もっと目立つ奴がいた。
気を失った御侍は、まるで愛人同士のように親しげに彼の腕に抱かれていた。
そいつはまさにさっき書斎から離れた奴だった。
突入してくる兵士たちと対峙している彼の顔には、不可解が書かれていた。
まるで自分が何を間違ったかもわからないかのように。
俺様は知っていた。その包囲されていた奴こそが、伯爵夫人を悪魔に落とした最大の共犯者だってことを。
なぜかわからないが、ビーフステーキは俺様が二階から飛び出したのを見てほっとし、そしてすぐに両剣を握り締めて警戒の目で包囲されている奴を見やった。
俺様は二階から飛び降りて、彼の隣に立った。御侍の婚約者は緊張に満ちた顔で俺様たちの隣にやってきて、彼の手にある長剣は震えていた。彼の側で俺様は彼の動揺を感じた。
「彼女を放せ。私が代わりになる」
「なぜ彼女を君と交換しなければならない。君の血は彼女のような暖かさがない」
俺様は思わず長剣をきつく握り締めた。これは俺様のミスだ。
まさかあの強情な御侍が、俺様がいない時にここに潜り込んでくるとは思わなかった。
ビーフステーキはその、頭を傾げて無邪気に笑っている奴を睨んで、いきなり飛びかかった。
彼の動きに従って、交流などなくても、俺様は正しいタイミングを狙って戦局に加わった。
奴の懐に抱かれている御侍のことを考えると、俺様とビーフステーキの動作は制限されていた。ビーフステーキの腕が切られ、血が出た。
そいつの顔にもビーフステーキの血が飛び散った。彼は突然表情を変え、笑顔は徐々に不気味な渇望になった。
次の瞬間、彼は御侍を投げ捨てた。俺様は御侍を受け止め、ホールで戦ってる二人を見る。
戦い始めた瞬間、俺様はこいつが人類ではないことに気づいた。
彼は俺様達と同じ、食霊だった。
同時に、彼のビーフステーキを見る目が何を意味するかもわかっていた。
今さっき、一人の女が奴のような目をしていた。それは長く探し続けた人を見つけたような目だった。
血の匂いを分別できない人間にはわからないだろう。
俺様は他の人類や食霊から、ビーフステーキのような温かい血を感じたことがない。
それは、冷たい暗闇の中を生きてきた者が誰しも拒絶できない温度だった。
まるで寒い冬の中で、熱くても手を離せない炭火のように。
Ⅳ 承諾と付託
ビーフステーキと兵士達の攻撃で、その食霊はすぐ逃げた。
彼が逃げた時のビーフステーキ見る目は、恐ろしくてぞっとした。だがその無神経な奴は全く気づいていないようだった。
俺様達は深追いせずに、急いでさっきのホールに戻った。
契約に通じて、俺様は彼女が無事であることを感じとった、もう目が覚めたかもしれない。
しかし、あの一度も彼女を褒めたことがない男はそれを知らない。
彼女が、婚約者が自分を抱きしめて大泣きしているのを笑いそうになったところを見て、俺様は思わず頭を振った。
そして、その部下に恐れられてきた厳格な男は、部下達の注目の下で、心の中に隠していた言葉を全部ぶちまけた。
婚約者が起きるところをみて、男はポカンとした。
「馬鹿!私が好きな気持ちは私が死んでからじゃないと言えないのか!」
「おおおおま、お前!冗談が過ぎるぞ!」
「知らない!もう一回言って!私が好きと!何よりも好きと!」
「そんなこと言っていない!」
「言った!全員聞いた!」
「誰が聞いた?誰が?今月のボーナス要らないんだな!」
はらはらドキドキする始まりは、幸いな事に、円満な結末を迎えた。
国を騒がせた悪質な事件は、犯人の死刑で幕を落とした。
同時に、ただの政略結婚だと言い続けていた二人も、正式に婚姻関係を結んだ。
二人ずっとこのように、口喧嘩しながらも、人生の最後まで付き添った。
「もういい年だから、喧嘩は恥ずかしくないのか?」
「赤ワインにだけは言われたくないわ。あなたもよくビーフステーキと喧嘩するでしょう!」
「……それは、あいつが挑発してくるから!」
「ち……嘘つき」
男は御侍より早く他界した、男の前でいつもつんけんしていた御侍は、この時は格別に優しかった。
彼女は影で二人を見守っている俺様を見た。
俺様が側に行ったら、彼女は俺様の手を取った。
「私は知っているのよ。彼が最も心配していたのは、私とステーキだった。赤ワイン、最後の頼み、聞いてくれる?」
彼女のやさしい笑顔を見て、俺様は何かを思いついたが、よくわからなかった。
俺様は眉を顰めて、頷いた。
「あなたとビーフステーキはお互い嫌っている事は知っている。でも二人は本当は仲がいいことも知っている。だから彼の代わりに、私の代わりに、ビーフステーキをよろしくね」
「……ち、めんどくさい。まあでも、ちゃんと見張っとくから、心配するな」
Ⅴ 赤ワイン
とある王城があった。その王城の中で、人一倍格好良い騎士と、人一倍美しい貴族の女の子がいた。
両親が知り合いだったので、二人は幼少の時から共に成長してきた。
騎士は有名貴族の長男だから、二人の身分はちょうど釣り合ってると言えた。しかし、やがて夫婦になる運命の二人は、あまり仲が良くなかった。
誠実な男の子は女の子の機嫌を取る手段を知らなかったし、恥ずかしくて気持ちも伝えられなかった。
女の子は密かに男の子に恋心を抱いていたが、返事をもらえないだけじゃなく、よく男の子に責められていた。
「この馬鹿、こんな簡単な事で怪我するなんて」
ーーなぜ俺様に助けを求めない。
「お前が手を出すようなことじゃない、帰れ」
ーー危険だから放っておけない、俺様が代わりにやってあげるから。
そして、最も仲が良かった女友達を失った彼女は、怒りでわれを忘れて、あの恐ろしい古城に潜り込んだ。
すべての御伽噺のように、お姫様の危機はいつも騎士様が救う。
女の子を抱きしめて本当の気持ちを曝け出したら、騎士はようやくお姫様を手に入れた。
魔女を駆除した後、お姫様と騎士様は幸せに暮らしていた。
これは間違いなくすべての物語に於ける最も素晴らしい結末だった。
だがこの幸運なお姫様は、彼女の騎士以外に、もう一人彼女を守ってきた王子様がいた。
その王子には金髪碧眼がない、彼はまるで伝説の吸血鬼のように、日光を嫌う。
鮮血に対して違う趣味もある。
王子は騎士と姫のデートを邪魔したりしなかった。彼は姫が怒り心頭な時だけ仕方なく姫の綺麗な長髪を揉み乱す。
騎士の側には、もうひとりの騎士がいたが、その騎士と王子はあまり仲良くはなかった。
魔女は姫の最も仲の良い友達を連れ去った後、王子は姫を慰めたりしなかった代わりに、独りで魔女の城に向かった。
姫のために。
騎士達のために。
騎士のルールでは。
ーー女性と弱い存在に武力を振るうべからず。
たとえ相手が魔女でも例外ではないだろう。
ならば、俺様が代わりにやろう。
だが、まさか魔女は自分に誘いの手を差し伸べてきたとは、彼も思っていなかっただろう。
魔女は彼を魔王と見做していた。
そして魔女にも予想できなかったことに。
闇の中から生まれてきた王子は、激しい日光のような騎士と出会った後、もうこれ以上闇に向かわないと決めた。
彼女の魔王は闇に落ちる寸前で、その騎士によって闇から蹴り出されたなんて、魔女は永遠に思いつかないだろう。
騎士は王子に約束した。もし王子が自分を抑えきれない時が来たら、彼は自らの手で王子を斬り殺すと。
だから今、王子は自信を持って他人の側に立ち、享受すべきではなかった日光を楽しむ。
「お前の聖剣騎士団より迦南(カナン)の方がいいと思う。いっそのこと聖歌騎士団にしても、お前のネーミングよりはマシだ!」
「我々は騎士団だ、何が迦南傭兵団だ!」
「迦南!」
「聖剣!」
傍らで座っているかわいい少女は仕方なくため息をついた。彼女は茶を飲みながら二人の団長の喧嘩を見てた。
「お二人さん仲いいね……こんなに喧嘩しても別れないなんて。あ、そうだ赤ワイン。昨日手紙を受け取った。あんた宛よ。濃い血の匂いがしたが、何があったんだ?」
赤ワインはジンジャーブレッドが取り出した手紙を見て、ビーフステーキとの喧嘩をやめて、手紙を受け取ったらすぐ外に出た。
封筒を開けたら、錆色の墨汁で美しく飄々とした文字が書かれてた、封筒の全体から濃厚な血生臭い匂いが漂ってきた。
彼は眉をひそめて適当に読んだら、封筒を旅館の入口のランプに入れて、薄い黄色の便箋が徐々に萌え尽くすのを見つめた。
灰になった手紙をみて、赤ワインは思わず軽く笑いだした。
かつての彼は、自分の鮮血に対する渇望のせいで困惑し、戸惑い、堕落しかけたことすらあった。
しかしビーフステーキは荒々しくても有効な方法で、彼を誘惑の深淵から連れ戻した。
「血の温度か……俺様はそんなことのためにあいつの側にいるわけではない。ふ、愚かで哀れな奴だな」
◀ エピソードまとめへ戻る
◀ 赤ワインへ戻る
Discord
御侍様同士で交流しましょう。管理人代理が管理するコミュニティサーバーです
参加する-
-

-
副管理人
-
-
-

-
ななしの投稿者
166年まえ ID:n3shisjxⅤ(9/9)
-
-
-

-
ななしの投稿者
156年まえ ID:n3shisjxⅤ(8/9)
-
-
-

-
ななしの投稿者
146年まえ ID:n3shisjxⅤ(7/9)
-
-
-

-
ななしの投稿者
136年まえ ID:n3shisjxⅤ(6/9)
-
-
-

-
ななしの投稿者
126年まえ ID:n3shisjxⅤ(5/9)
-
-
-

-
ななしの投稿者
116年まえ ID:n3shisjxⅤ(4/9)
-
-
-

-
ななしの投稿者
106年まえ ID:n3shisjxⅤ(3/9)
-
-
-

-
ななしの投稿者
96年まえ ID:n3shisjxⅤ(2/9)
-
-
-

-
ななしの投稿者
86年まえ ID:n3shisjx赤ワイン エピソードⅤ(1/9)
-