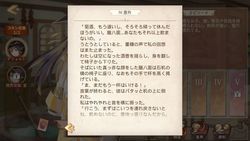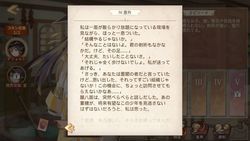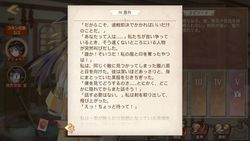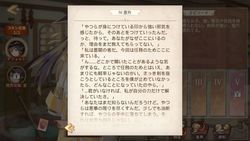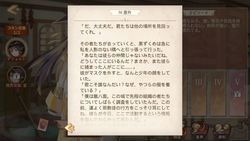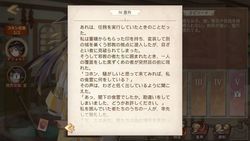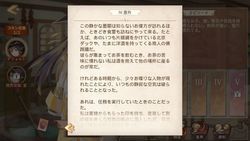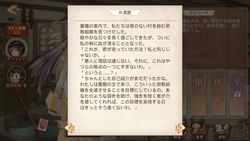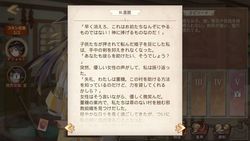菊酒・エピソード
◀ エピソードまとめへ戻る
◀ 菊酒へ戻る
菊酒のエピソード
洒脱で自由気ままな女子、強い意志や自我を持つ、ルールに縛られない。
剣術が強い、独りで戦うことに慣れてる。
Ⅰ.御剣
強い風の中、落ち葉がゆらゆらと舞い上がり、乱舞する枯れた蝶のように見える。
私はゆっくりと目を閉じて、己の中の気を上げて集中力を上げる。そして、葉の方位を察知し、息を吸いこんだ。
(……ここだ!)
目を見開いて、握りしめた剣を掲げ、身を翻す。それから剣を静寂の中、葉を目掛けて振るった。
そのまま剣を鞘に納める。カチッと鍔が音を鳴らすと、葉が真っ二つに分断され、ひらひらと地面に落ちていく。
一息ついたそのとき、背後から足音が鳴り響いた。振り返ると、そこにはよく知った顔があった。山道からやってきた御侍である。
「菊酒、そなたの剣術は、ますます立派なものになりましたね」
「御冗談を。これはまだまだ私の望むスピードには達しておりませんよ、御侍」
そう答えながら、私は、口角を上げて目を細めた。それから晴れ晴れとした気持ちで、小さく頷く。御侍の持っている二本のお酒が目に入ったからだ。
「すべて順調に進んでいます。焦ることはありません。さあ、私の作った秋露白を試してみましょう」
私たちは石のテーブルの傍に座って、酒を飲みながら雑談を始めた。
私は毎日この鋳剣山荘の裏山で剣術を習っている。日暮れになると、御侍はたまにお酒を持ってやってきた。
裏山は静かで、人の姿はまばら。空にはまたたく星と、茂みには蛍の光。その光は点滅し、まばたきをしている親友同士のようだ。
そんな空を眺めながら、知らず知らずのうちに、酒瓶一本が空になっていた。
「菊酒、あなたは……離れたいと思ったことがありますか?私にはわかっています。貴方の気性からして、きっと同じ場所留まりたくないでしょう?」
御侍は唐突にそう口にして、杯に添えた手に力を込める。
「私はまだ修行中です。私のいる場所はどこであると思いますか? そこは、ここと何が違いますか?」
実は私は真剣にこの問題を考えたことがない。山荘での静かな日々は、私にその問題を忘れさせてくれた。
確かに御侍の言う通り、私は元々は自由に憧れている。
同じ場所に留まりたくないと望んでいた。だが、少なくともこのときはまだ離れたいと思っていなかった。
「そうですか、でも私は離れた方が良いと思いますよ」
「御侍、それはどういう意味ですか?」
「ははは……何でもありません。少しだけ、飲みすぎたようです」
御侍は力なく笑って、頭を振って言った。だが、そのときの私には、彼の話の意味がよく理解できなかった。
それ以来、御侍はほとんど裏山には来なくなった。私も次第に気づいてきた。鋳剣山荘の雰囲気はますます暗くなりました。
様々な車が頻繁に出入りし、輸送された材料は貯蔵室からあふれそうに積まれている。同時に大量に廃棄された原料とスクラップが次々と運ばれてきた。
「後任の新城主様の野心は大きいようだ」
「一番良い剣を作るように命じられた」
この山に二人いた鍛冶師は、すぐに剣を打つことになった。鍛冶部屋の明かりがほとんど消えないのを見て、私はため息をつくしかできなかった。
御侍はもう半月も鍛冶部屋に閉じ込められている。あの日の御侍は、このことがわかっていたのでしょう。
私は何とも言えない気分で、身を持て余していた。どうすべきか悩んで、何度も夜明けに御侍に会いに行った。出てきた御侍はいつも疲れた姿である。
私は黙って袖口のお酒を隠した。御侍はとてもお酒なんか飲める状態ではなかったからだ。
私は近くに来ているという友人の重陽糕を探しに行くことにした。
重陽糕は私が御侍が材料を採集しに行ったときに知り合った。彼女と話をするたびに、私の心中はいつでも穏やかになった。
「なぜ世間の人は追求するのか?自分を巻き添えにしたり、他人を巻き添えにしたりするのは特に問題だ」
私の向かいで重陽糕は静かにお茶を飲み、やっとゆっくりと口を開けた。
「これは彼らの命数――生まれる前から決まっていた運命だろう」
「あの道士みたいなことを言うね。ああ……そういえば最近彼はどうしている?」
もうこれ以上悩みたくなくなって、私は思い切って話を逸らす。
「あの娘が見つかったと聞いた」
「……それはよかった。長く探していたのでしょう?」
彼の友人である黄山毛峰茶は、修行していた太雲観で出会った女性をずっと探していたという。
彼女は御侍と共に亡くなったらしいが、食霊であるなら、また再びこの地に現れるだろうと……なかなかの執着ぶりである。
「菊酒、多言を許されよ。あなたの親しい人は、近いうちに災厄が降りかかるであろう。気をつけた方が良い」
別れ際に重陽糕は言葉を選んでそう告げ、この言葉を口にした。
「は?」
私は彼女のその言葉をすぐには理解することはできなかった。
「災厄」と、山荘を忙しなくする外の面倒事だと思って、詳しく考えなかった。
彼女はそれ以上、何も言わなかった。
Ⅱ.運命
どんより曇った靄の中へと、夕日が最後の光を差し込んでいく。爽やかな夕風が、東屋の中を漂っている。
「菊酒、いつもどおり剣の稽古をしないの?」
董糖の声が悠々と響き、突然わたしを思考の海から引き戻した。
「今日の練習はもう終わったよ。ただ、急に昔のことを思い出して、ここに立ち寄っただけさ」
私の言葉が終わると、董糖は微笑みながら酒瓶を一つ取り出した。
「この前、あなたの御侍が鋳剣師だという話をしてくれたけど、その続きを話してはもらえるかな?」
一方、臘八麺もいつの間にかその場にやってきていた。
「今日の用事が全部終わってね。ちょうどあなたたちを見かけたから、来ちゃった」
「まだ菊酒の昔話は聞いたことがなかったから、興味がありますね」
「君たち…まあいいか。ただの昔話にすぎないし」
私はやむを得ず董糖が渡した杯を受け取った。酒の香りが、東屋中に行き渡っている。
そうこうしているうちに、山荘で異常が発生してから一ヶ月が経った。すると御侍は私のもとにやって来るや、とある珍しい材料を探すように頼んできた。
「長い道のりになるだろうから、旅用の包みを用意したよ」
私は自らが義を辞することを許さず、断りもしない者だとわかっている。
しかし手中の包みを握っていると、なぜか不安な気持ちが少しずつこみ上げてきた。
城外の小道を歩きながら、私は御侍が目を逸らしたときの不思議な表情、そして山荘での出来事を思い出し、不安感がさらに深まった。
御侍の行動は、まるで私をその場から立ち去らせたいようだった。
「菊酒、本当のことを言って悪いけど……あなたのそばにいる人に、そう遠くないうちに災厄が降りかかるよ。」
突然、このあいだの重陽糕との会話が脳裏をよぎった。もはや不安を抑えることができなくなった私は、思い切って進む道を変えた。
私は手中の剣を強く握り、遠くにある山上の山荘を視界に捉えると、再び足を速めた。
そして城門の外に着くや、私は兵士に囲まれた。彼らの旗印が、城主のものだということに私は気づいた。
「こいつが、城主が言っていたあの食霊か?捕まえろ!」
彼らは訳もなく私を襲ってきた。私は剣を振り、いとも簡単に彼らを追い払った。
「菊酒、まずは剣を下ろすんだ。我々は城主の命令に従い、君を御侍に会わせるつもりだ。」
一人の将軍の格好をした者が、城門の中から現れた。
わたしはその人物のあとについて山荘の裏山に行き、見知らぬ道を何度も通ったあと、人目につかなさそうな祭壇が目の前に現れた。祭壇の真ん中には剣が一本置いてあり、両側には城主と御侍が立っている。
「御侍、あなたたちは…」
この前感じた不安が的中したと思った私は、前へと歩き出した。
だがその瞬間、私はどこからともなく現れた官兵に再び囲まれた。それでいて、彼らは私の剣を恐れて軽率に前へ出ようとはしなかった。
「菊酒……」
御侍は一瞬、怪訝かつ慌てた様子の表情を見せた。
「これで全員揃った、さあ、儀式を始めるとしよう!」
城主は嬉しそうな顔をして、大笑いした。
ここまで来て、ようやく私はおおよその流れを理解した。
「あなたの目的は何だ?」
私は大声で城主へと問い質した。
「ハハハハ!どうやらお前の御侍は、まだお前に教えていなかったようだな。いいだろう。死ぬ前にお前に教えてやろう。お前は鋳剣師の食霊としてこの剣に身を捧げ、俺の代わりにこの剣を――死ぬまで祀るのだ!だが、お前は常人ではないからな、さぞ大きな力を持つこととなるだろう!フハハハ!」
私はこのまま消えることこそないが、この剣に長く囚われ続けるというのは、私が最も嫌う束縛そのものだ。
悔しい気持ちが胸中を満たしていく中、鋳剣室から絶えず響く鉄を打つ音と、御侍の痩せた顔を思い出した。
そして、自分が幸運にも召喚され、この世界を旅したことも思い出した。風光明媚な自然の風景も見られたし、剣術も習うことができた。そう思えば、確かにやり残したことはないのかもしれない。
「御侍が私を必要とするならば、私は水火も辞さない。」
分かっている。何かを得るためには、何かを失わなくてはならないのだ。今、御侍のために私ができることは、ただそれだけだ。
Ⅲ.墨閣
かすかに光る星と冴える月の下で、私は最後の一杯を掲げながら、物語の最後を話した。
「私は食霊を利用したいと一度も思ったことがない。これは私たち自身の業であり、自分で背負わなければならない。」
御侍は強く拳を握り、歯を食い縛りながら言った。
そして衆人環視の中、御侍が剣を取り上げた瞬間、剣先がその胸に突き刺さり、赤い血が飛び散った。
「菊酒……壊してやれ。」
そう言って、御侍は私に顔を向けた。その目には釈然とした気持ちが映っている。
周りの者達が予想外の事態に驚いている中、私はその隙に逃げ出し、自らの剣を抜くや思いきり振り下ろした。祀られるはずだった剣は瞬く間に壊され、しばらくすると煙と化し、空へと消えていった。
周りが混乱する中、私は御侍のそばまで駆け寄った。
「この結果を選んだのは、自分と同族の者達を……そしてあなたを、救うためだ。これからは、何ものにも囚われることなく、永遠に自由でいて……」
言葉が終わると、目の前の人物は緩やかに両目を閉じた。
「ありがとう……御侍」
ずっと、いつも、君には世話になっていた。
このときようやく、私が御侍が言っていた「離れる」とは何なのかが分かった。
その後、城主は精神病を患い、弾劾されて失脚したという話があちこちに知れ渡った。この件を知った重陽糕は、わざわざ私を慰めに来てくれた。私はこの時になるまで、彼女がずっとこの城の中にいたことを知らなかった。
「重陽糕、ありがと。私はもう他のところに行くことに決めたよ。」
「このことは忘れてと、言いたいところだけど……あなたは思ったよりも心が大きいんだね。」
何といっても、私の旅はまだまだ遠く、この世の浮き沈みはただの一瞬のことにすぎず、その全てが乗り越えなければならない試練だからだ。
そして私は剣を取り、一人で遠くへと旅立った。
そうしてとある冬に、わたしはある村にて、見たことのない景色を目にした。
村人たちは荒地を守りながら、ひらひらとちらつく雪の中で飢えと寒さに襲われている。
一方で、朽ち果てた寺には食料と金貨が小さな山になるほどに積まれている。
ぼろい綿入れの服を巻きつけた二人の男の子が、冷たさで真っ赤になった手足でこっそりと寺の中に忍び込もうとしたが、見張りの男に棒で無理矢理追い出されていた。
「食い物がちょっとほしいだけだよ。ここには、こんなにもたくさんあるじゃんか!」
「そうだよ、ちょっとだけならいいじゃないか!」
「早く消えろ、これはお前たちなんぞにやるものではない!神に捧げるものなのだ!」
子供たちが押されて転んだ様子を目にした私は、手中の剣を抑えきれなくなった。
「あなたも彼らを助けたい、そうでしょう?」
突然、優しい女性の声がして、私は振り返った。
「失礼、わたしは董糖。この村を助ける方法を知っているのだけど、力を貸してくれるかしら?」
女性はそう言いながら、優しく微笑んだ。
董糖の案内で、私たちは罪のない村を蝕む邪教組織を見つけだした。
穏やかな日々を長く過ごしてきたが、ついに私の剣に血が滴ることとなった。
「これが、君が言っていた方法?私と同じじゃないか。」
「悪人に理屈は通じない。それに、これはやつらの拠点の一つにすぎないわ。」
「というと……?」
「ちゃんとした自己紹介がまだだったかな。わたしは墨閣の主であり、こういった邪教組織を全滅させることを目標にしているの。あなたのような弱きを助け、強きを挫く者が力を貸してくれれば、この目標を実現する日はきっとそう遠くないわ。」
Ⅳ.意外
私は、董糖の誘いに乗ろうと思った。一人でいる時間が長かったせいか、帰る場所があるのも悪くないことだ。
ここにどれくらい長く滞在するのかは分からないが、
あの者たちの境遇をこの目で見た以上、何かをせずにはいられなかった。
墨閣は、悪くない選択だ。少なくとも、私はここを気に入っている。
実のところ、墨閣は城にある荘園の中に建てられた茶楼だ。
広い荘園にある裏山の一角を私は整地し、剣術の修練の場として使っている。
この静かな墨閣は知らないお偉方が訪れるほか、ときどき食霊も訪ねにやって来る。たとえば、あのいつも片眼鏡をかけている北京ダックや、たまに洋酒を持ってくる商人の佛跳牆だ。
彼らが集まってお茶を飲むとき、お茶の苦味に慣れない私は酒を抱えて他の場所に座るのが常だ。
けれどある時期から、少々お喋りな人物が現れたことにより、いつもの静寂な空気は破られることとなった。
あれは、任務を実行していたときのことだった。
私は董糖からもらった印を持ち、変装して別の城を巣くう邪教の拠点に潜入したが、目ざとい者に見破られてしまった。
そうして邪教の者たちに囲まれたとき、一人の覆面をした黒ずくめの者が突然目の前に現れた。
「コホン、騒がしいと思って来てみれば、私の食霊に何をしている?」
その声は、わざと低く出しているように聞こえた。
「あっ、閣下の食霊でしたか。勘違いをしてしまいました、どうかお許しください。」
私を囲んでいた者たちのうちの一人が、率先して敬礼した。
「だ、大丈夫だ。君たちは他の場所を見回ってくれ。」
その者たちが去っていくと、黒ずくめは急に私を人影のない隅へと引っ張って行った。
「あなたは彼らの仲間じゃないみたいだね。どうしてここにいるんだ?まさか、また彼らに捕まった人がここに……」
彼がマスクを外すと、なんと少年の顔をしていた。
「君こそ誰なんだい?なぜ、やつらの服を着ている?」
「私は臘八麺。この城で先程の組織の者たちについてしばらく調査をしていました。この前、運よく邪教徒の行方をこっそり耳にしましてね。彼らが今日、ここで活動するという情報を掴んだからやって来たんです。」
「やつらが身につけている印から強い邪気を感じたから、そのあとをつけていったんです。っと、待ってください。あなたがなぜここにいるのか、理由をまだ教えてもらっていません」
「私は墨閣の者だ。今回は任務のためにここに来ている。」
「ん……どこかで聞いたことがあるような気がするな。ところで任務のためとはいえ、あまりにも軽率じゃありませんか?さっき剣を抜こうとしているところを私が止めていなかったら、どんなことになっていたのやら」
「…君がいなければ私が自分の力だけで解決していたさ。」
「あなたはまだ知らないのでしょうけど。奴らは悪事の限りを尽くすんだ。少しでも油断すれば、奴らの手中に落ちてしまう。それは食霊も例外じゃない」
「だからこそ、速戦即決でかかればいいだけのことだ。」
「あなたって人は……」
私たちが言い争っているとき、そう遠くないところにいる人物が突然叫びだした。
「誰か!そいつだ!私の服と印を奪ったやつは!」
私は、同じく敵に見つかってしまった臘八麺と目を向けた。彼は潔いほどあっさりと、身にまとっていた黒服を引きちぎった。
「私を見てどうするのです……とにかく、どこかに隠れてからまた話そう!」
「話す必要はない。」
私は剣を取り出して、飛び上がった。
「えっ!ちょっと待って!」
私は一面が散らかり放題になっている現場を見ながら、ほっと一息ついた。
「結構やるじゃないですか。」
「そんなことはないよ。君の剣術もなかなかだ。けど、その足……」
「大丈夫、たいしたことありません。」
「それじゃ全く歩けないでしょ。私が送ってあげる。」
「さっき、あなたは墨閣の者だと言っていたけど…思い出した。それってすごい組織じゃないか!この機会に、ちょっと訪問させてもらえないかなあ……」
臘八麺は、突然ぺらぺらと話しだした。あの董糖が、将来有望なこの少年を見逃すはずはないだろうと、私は思った。
「菊酒、もう遅いし、そろそろ帰って休んだほうがいい。臘八麺……あなたもそれ以上飲まないの。」
うとうとしていると、董糖の声で私の回想はまた止まった。
わたしは空になった酒壺を揺らし、身を翻して椅子から下りた。
側にいた真っ赤な顔をした臘八麺は石机の横の椅子に座り、なおもその手で杯を高く掲げている。
「ま、まだもう一杯はいける!」
言葉が終わると、彼はバタッと机の上に倒れた。
私はやれやれと首を横に振った。
「行こう。まずはこいつを連れ戻さないとね。飲めないのに、意地っ張りなんだから。」
Ⅴ.菊酒
光耀大陸のとある城の城主は、 その剣術で名を馳せている。その剣気に敵う者がいないため、城内は常に落ち着いており、襲ってくる者は一人もいなかった。
城主は代々、剣を携えている。その剣は城で唯一の鋳剣師の一族が造ったものだ。鋳剣師の一族はその家に生まれるや、 歴代の城主に最高の剣を造るために仕える日々が始まる。城主の剣はその一本一本に一族の心血が注がれている。そのため、鋳剣師の一族は長年隠居して姿を現さないが、 人々からは尊敬の念を受けている。
菊酒の御侍は、鋳剣師の一族における現在の家主だ。
初代城主は強力な剣術と宝剣を求めるために自らを剣に捧げ、剣と契りを交わした。
両者は相手の力を吸い取ることで共存していた。
だが、力には限界がある。人間は生きていくために、剣の力が尽きないように常に剣に仕えていなければならない。 剣は人間に力を与えるかわりに、その人間がそのカを維持するための新たな器を用意しなければならない。そのため、初代城主は初代鋳剣師でもあったそして、鋳剣師は常に城主の剣に仕えている。新たな城主が契りを交わすと、 先代は鋳剣師となり剣に仕え続けるのだ。
百年が経った今では、互いの一族は異なる道を歩んでこそいるが、血筋は同じだ。永遠にこの城で剣に囚われ続ける。
しかし、城主の代わりに身を捧げることができる存在がいるという発見があった。それこそが、食霊だ。
食霊は人間よりも大きな霊力を持っているだけでなく、人間と結ばれている。代わりになる存在としては最高だ。城主の代わりに、契りの代償を引き継ぐことができるのだから。
菊酒は一族の中で、最初に現れた食霊だ。
だが今の家主は自分を犠牲にしてまで、剣に関わってきた者たちを長年縛り続けた契りから断ち切った。自らと一族の者を解き放ち罪のない食霊をも救ったのだ。
今、互いの一族を百年あまりも閉じ込めていた剣は、ついに消えた。
それからというもの、光耀大陸には剣術に優れ、爽やかでありながら浮世離れしておりいつも一人で旅をしている少女の剣士が現れた。彼女はよく、人助けのために悪人を成敗している。だがその剣士は、墨間の者だとしか言わず、 名前を告げぬまま去ってしまうのだ。
そして、城にある山の近くに建てられた荘園では、墨閣と名付けられた茶楼が有名になっていた。
そこには色んな者が惹きつけられたかのように訪ねてくるという。
園内では清泉が石の上をつたって流れ、お茶の香りが漂い、粋な造りの東屋から琴の音が響く。なんとも趣のある光景だ。
しかしそこは誰でも入れるわけではない。墨閣の主に招待された者か、カのある者のみが、その素晴らしい光景を味わうことができるのだ。
◀ エピソードまとめへ戻る
◀ 菊酒へ戻る
Discord
御侍様同士で交流しましょう。管理人代理が管理するコミュニティサーバーです
参加する-
-

-
ななしの投稿者
335年まえ ID:m5k84jlsIV 意外⑧
-
-
-

-
ななしの投稿者
325年まえ ID:m5k84jlsIV 意外⑦
-
-
-

-
ななしの投稿者
315年まえ ID:m5k84jlsIV 意外⑥
-
-
-

-
ななしの投稿者
305年まえ ID:m5k84jlsIV 意外⑤
-
-
-

-
ななしの投稿者
295年まえ ID:m5k84jlsIV 意外④
-
-
-

-
ななしの投稿者
285年まえ ID:m5k84jlsIV 意外③
-
-
-

-
ななしの投稿者
275年まえ ID:m5k84jlsIV 意外②
-
-
-

-
ななしの投稿者
265年まえ ID:m5k84jlsIV 意外①
-
-
-

-
ななしの投稿者
255年まえ ID:m5k84jlsⅢ 墨閣⑥
-
-
-

-
ななしの投稿者
245年まえ ID:m5k84jlsⅢ 墨閣⑤
-