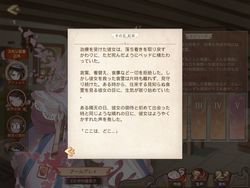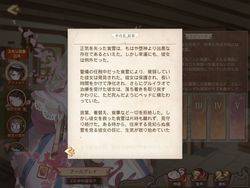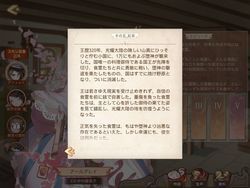紅茶・エピソード
◀ エピソードまとめへ戻る
◀ 紅茶へ戻る
紅茶のエピソード
果断かつ真面目な性格で、何事も中途半端には終わらせない食霊。
戦闘能力を上げることに執着し、どんな場面に遭遇しても優雅な立ち振舞いを崩さないのは、以前高貴な身分の料理御侍についていたからなのかもしれない。
過去に心身ともに疲弊した経験があるが、どんなに辛いことでもいずれ時間が傷を癒やしてくれると、人に手を差し伸べる温かさを持っている。
Ⅰ .委託
日課としてやっている射撃のトレーニングを済ませたら、私はよく「サタンカフェ」へ足を運ぶ。
食霊がオープンしたこのカフェは、絶品のコーヒーやドリンクを提供するだけでなく、人間には実行不可能とされる任務の代行業も営んでいる。
「マスター、いつものお願いするわ」
「サタンカフェ」のマスターであるコーヒーは、経営と管理に応じる食霊だ。いつも微笑みを見せている彼だが、今はある委託状を見て眉を顰めていた。
「手の焼ける委託のようね」
マスターの少し色あせた前掛けに、そっと目をやりながら尋ねた。
「ええ……」
ようやく返事をしてくれたが、マスターの表情は厳しいままだ。普段とは違う、仕事の顔をしていた。
「ちょうど君に、頼もうと思っていた」
「委託の内容は?」
私はたまにここで委託を受ける。
任務完了後、店長は報酬を分けてくれる。
食霊にとって、お金は無意味なものだが、人間社会での暮らしには欠かせない。
「光耀大陸に行ってくれるか?」
マスターは私が注文したドリンクをカウンターに置くと、まっすぐにこちらを見つめてきた。
「私の知っている中で、あの土地に一番詳しいのはやっぱり君だからね」
「……到着後の動きを教えてちょうだい」
「行方不明になった人間の女性を捜してほしい。年齢は18歳前後」
丁寧な任務説明に耳を傾けながら、私はマスターの目に吸い込まれそうになっていた。私はあわてて目を伏せた。
「わかったわ。すぐに出発します」
手渡された委託状を受け取り、店を出ようとしたとき、後ろから呼び止められた。
「待ってください。私も行きます。いいですよね?店長?」
振り向くと、その落ち着いた、ほのかに甘い声の主はミルクだった。一見付き合いにくそうな雰囲気だが、友達思いの心優しい食霊なのだろう。
「心配することはない。彼女ならきっと」
その目は、自信に満ちていた。
私には、今から向かう土地に、辛い記憶があった。彼らはそのことに触れないが、何かを察している様子だった。
「待っているよ、ハニー」
いつもの調子に戻ったマスターは、しかし申し訳なさそうな顔で言った。
ありがとう。本当にもう大丈夫よ。心配されるほど、やわじゃないのよ、わたくしは。力強い足取りで店を後にし、私は因縁の地、光耀大陸へ向かった。
Ⅱ ボタンイバラ
この国を後にして、どれくらい経っただろう。懐かしい景色を目にすると、種々の感慨が湧いてくる。目の前に広がるボタンイバラの花畑が、星辰の生暖かい風にそよいでいた。
ティアラ大陸は、365日を十二等分した独自の暦を持っている。星辰はちょうどその4番目に当たる。私はしゃがんで小さな白花に触れた。その瞬間、おぼろげな姿が頭の中を巡った。
「はじめまして。今日からは私があなたの御侍様よ。姫と呼ばれるのは好きじゃないの。そうね、ボタンと呼んで。」
「ほ〜ら、そんなに堅い表情しないで、リラックス、リラックス、笑ってみて?ふふ、せっかくわたしにそっくりの美人なんだから、自信を持ちなさい」
「わたしの父上も母上も、この国のために命を捨てたの。ずっと寂しかった私の世界に、紅茶、あなたが来てくれたのよ」
「ねえ、紅茶。ここはとっても平和でしょう。みんな助け合いの心を忘れず、生活しているの。素敵な国でしょう?」
「私も先代のような、立派な王になりたい。すべての民を守りたい。私にとってみんなは、家族のような存在だから」
「え?私は国を、あなたは私を守る?ふふ」
「紅茶、ありがとう。あなたに話すと、いつも私の心は晴れやかになるのよ」
姿だけでなく、彼女はどこか、私に似ていた。ちょうどこの季節に吹く風のような笑顔。彼女は、私がこの世界に来てから初めて出会った料理御侍だった。
彼女がいて、私は光耀大陸が好きになった。そして「サタン」のみんなが私を心配してくれる理由も、彼女が関係している。
Ⅲ 過去
(※誤字と思われる箇所を編集者の判断で変更して記載しています)
「任務に集中しないと」
私は立ち上がり、コーヒーから受け取った委託状を握りしめた。
行方不明になった少女は、光耀大陸に遊学していた人間の女の子で、まだ自身の食霊を持っていない。彼女は毎月家族に手紙を送っていたが、ある時ぱったりと途絶えたそうだ。少女は最後の手紙で、広い竹林について書いていたが、私はそれが手掛かりになる予感がしている。
「……きっとあそこのことね」
人間に派閥があるように、食霊にも似たような状況がある。竹林のある場所の見当はついていたが、そこは「彼ら」の支配下にある地域だ。
いかに「彼ら」に気づかれず侵入し、捜索するか。竹林の陰に身を隠し思案を巡らせていた。突如、視線の先に、黒い影が動いた。
「奇遇だな」
顔を上げると、不敵な笑顔を浮かべた甘い豆花と目が合った。私は思わずベルトに下げているフリントロック式銃に手をかけた。
「まあ、そう警戒するなって。オレたちの仲だろ…?」
甘い豆花の不気味な笑顔には、毒蛇の牙のような鋭さが貼り付いていた。初夏の昼間だというのに、背中に寒気が走った。この食霊にはできれば会いたくなかった。
私は銃を構えた。
「何も話すことはないわ」
「わあ怖い顔。かつての友だちじゃないか。さ、思い出話をしよう」
彼は薄く笑いながらその場に腰を下ろした。
「しかし、あの頃の君はもっと魅力的だったね」
彼は私を見つめながら言う。
「元の君なら、オレをもっと愉しませることができる」
黙れ……銃を握り直すと、突然の眩暈が襲ってきた。何が起こった?視界に映る林、奴の不気味な顔、すべてが猛スピードで回転し、突然、地面が迫りかかってきた。
「おや。やっと効いたね」
「効いた……どういうこと……」
甘い豆花は懐から香袋を取り出し、倒れている私を覗き込んだ。
「時間を稼ぐために長話をした甲斐があった」
彼は香袋を嗅ぎながら続けた。
「これ、なかなか便利なんだ。君をね、思い出の中に連れていける」
足元に咲くボタンイバラの白花が風に揺れている。私は頬についた土を払うこともなく、それをただ、茫然と眺めていた。
「もう一度あの人の顔を見られるんだ、幸せだろ?」
Ⅳ 現在
(※「甘豆腐花」→「甘い豆花」に変更しています)
香袋の、どこか懐かしい匂いに誘われ、私はいつの間にか、記憶の世界に浮かんでいた。
「鎖国を解くことは絶対にできない!この国は私が守る国。この地の民は、私にとって家族よ。他の大国との交流は、危険でしかないわ。」
「紅茶も分かってくれるでしょう?この国は、平和な生活に慣れているの。その安全を、他国の脅威に晒すというの?」
「あなたの心配には及ばないわ。父上と母上だって、他国によって殺されたのよ!」
「もういい!紅茶には、私の気持ちなんてわからないでしょう!この国の王は私よ!!」
執拗にこびりつき、ついに消し去れなかった悪夢が鮮明に、滝のようにとめどなく溢れ、私は自分の絶叫を聞いた。
「思った以上に効いてるね」
甘い豆花のささやきが、頭のどこかで反響している。
「貴様の思い通りに……させるか……」
かろうじて引き留められた意識の中、銃で香袋を打ち壊そうとしたが、もはや手足の感覚すら失われていた。かわりに、再び深淵に引きずりこまれる感覚があった。
「たった一体の堕神の襲撃で、私の国が滅んだ……」
「紅茶、あなたは正しかったのね……この国は、こんなにも脆い……」
「私たちだけで守ろうなんて、儚い空想だったわ……は、はは」
「もしあなたの言う通りにしていたら……あなたは傷つかず、みんなも死ななくて済んだね」
「ごめんね……」
「もういいの!泣かないで!どうか生きて!」
ボタンが銃を手に取り、自らの脳天に突き付けた。私は思わず手を差し伸べた。
「お願い、死なないで……」
ボタンを抱きしめるはずの手は、いたずらに宙を引っ掻いた。暗闇は、あまりにも果てしなかった。
「私のせいで、みんな死んだ。私が弱かったから、ボタンが全部背負った。私のせいで」
「死ぬべきなのは、私、ボタンじゃなく、私」
胸を突く衝動が私を蝕んだ。得体の知れない第三の思考が、静かに、確実に、身体の隅々まで張り巡らされるのを感じていた。
「覚醒が……始まったのか?」
甘い豆花の言葉と共に、意識が絶えるのを感じた。記憶の暗闇は、刻一刻と凝縮され、より濃密な空間へと姿を変えていくが、息苦しさは感じなかった。その無感覚に、ただ身を委ねていた。
「大丈夫よ」
どれくらい墜ち続けただろう。私は大きく、純粋な力によって包まれていた。
「大丈夫。すべては終わったの。悔いることも、恥じることもないわ」
「大丈夫、もう大丈夫……」
目を開けた私は、声の主を見ることはなかった。
ただ一輪のボタンイバラの白花が、暗闇に根を生やしていた。
再び意識を取り戻した時、私は既に「サタン」にいた。
目が覚めた私を見ると、ミルクはかすかに瞳を潤わせたが、向き直ると、コーヒーに文句を言い始めた。コーヒーは苦笑しながら、ミルクを静めようとしている。彼らのやりとりをぼんやりと聞いていると、どうやらティラミスが光耀大陸に行き、甘い豆花から私を救ったようだ。
「任務は……どうなったの?」
私は視線をコーヒーに向けた。
「ハニー……あれは君をおびき出すための偽の委託だったようだ。本当に申し訳ない」
「そう……」
甘い豆花が現れたのは、偶然ではなかった。
だがこれでよかったのかもしれない。私は過去を肯定するために、光耀大陸へ向かったのだ。
開け放した「サタン」の窓から、あたたかな風が舞い込んできた。
Ⅴ 紅茶
王暦320年、光耀大陸の険しい山奥にひっそりと佇む小国に、1万にもおよぶ堕神が襲来した。国唯一の料理御侍である国王が先陣を切り、食霊たちと共に勇敢に戦い、堕神の撃退を果たしたものの、国はすでに焼け野原となり、ついに消滅した。
王は若さゆえ現実を受け止めきれず、自身の食霊を前に銃で自害した。重傷を負った食霊たちは、主として心を許した御侍の果てた姿を見て錯乱し、光耀大陸の地を彷徨うようになった。
正気を失った食霊は、もはや堕神より凶悪な存在であるといえた。しかし幸運にも、彼女は例外だった。
警備の任務中だった食霊により、衰弱していた彼女は発見された。彼女は保護され、長い時間をかけて浄化され、さらにグルイラオで治療を受けた彼女は、落ち着きを取り戻すかわりに、ただ死んだようにベッドに横たわっていた。
言葉、着替え、食事など一切を拒絶した。しかし彼女を救った食霊は片時も離れず、見守り続けた。ある時から、往来する見知らぬ食霊を見る彼女の目に、生気が宿り始めていた。
ある晴天の日、彼女の御侍と初めて出会った時と同じような晴れの日に、彼女はようやく掠れた声を発した。
「ここは、どこ……」
関連キャラ
◀ エピソードまとめへ戻る
◀ 紅茶へ戻る
Discord
御侍様同士で交流しましょう。管理人代理が管理するコミュニティサーバーです
参加する-
-

-
ななしの投稿者
66年まえ ID:lkx6stuf最終話3
-
-
-

-
ななしの投稿者
56年まえ ID:lkx6stuf最終話2
-
-
-

-
ななしの投稿者
46年まえ ID:lkx6stuf最終話1
-
-
-

-
白羽
37年まえ ID:j7uu8339(Ⅱの続き)
「え?私は国を、あなたは私を守る?ふふ」
「紅茶、ありがとう。あなたに話すと、いつも私の心は晴れやかになるのよ」
姿だけでなく、彼女はどこか、私に似ていた。ちょうどこの季節に吹く風のような笑顔。彼女は、私がこの世界に来てから初めて出会った料理御侍だった。
彼女がいて、私は光耀大陸が好きになった。そして、「サタン」のみんなが私を心配してくれる理由も、彼女が関係している。
-
-
-

-
白羽
27年まえ ID:j7uu8339(Ⅱの続き)
「ほ〜ら、そんなに堅い表情しないで、リラックス、リラックス、笑ってみて?ふふ、せっかくわたしにそっくりの美人なんだから、自信を持ちなさい」
「わたしの父上も母上も、この国のために命を捨てたの。ずっと寂しかった私の世界に、紅茶、あなたが来てくれたのよ」
「ねえ、紅茶。ここはとっても平和でしょう。みんな助け合いの心を忘れず、生活しているの。素敵な国でしょう?」
「私も先代のような、立派な王になりたい。すべての民を守りたい。私にとってみんなは、家族のような存在だから」
(続きます)
-
-
-

-
白羽
17年まえ ID:j7uu8339Ⅱ
その二_ボタンイバラ
この国を後にして、どれくらい経っただろう。懐かしい景色を目にすると、種々の感慨が湧いてくる。目の前に広がるボタンイバラの花畑が、星辰の生暖かい風にそよいでいた。
ティアラ大陸は、365日を十二等分した独自の暦をもっている。星辰はちょうどその4番目に当たる。私はしゃがんで小さな白花に触れた。その瞬間、おぼろげな姿が頭の中を巡った。
「はじめまして。今日からは私があなたの御侍様よ。姫と呼ばれるのは好きじゃないの。そうね、ボタンと呼んで。」
(続きます)
-