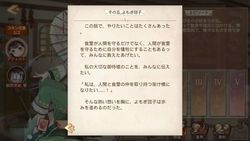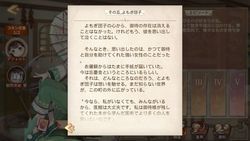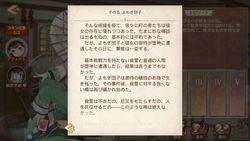よもぎ団子・エピソード
◀ エピソードまとめへ戻る
◀ よもぎ団子へ戻る
よもぎ団子のエピソード
太陽の光を浴びるのが好きな少女。
よく御侍を誘って散歩や遠足に出かける。準備はいつも用意周到で、様々なものを持ち歩いている。
Ⅰ 雨の祀日に
春もたけなわの日和。
清明節の時季――「すわ墓参りに」と出かけてみれば、嵐に見舞われて嘆息してしまう。春は嵐、とはよく言ったものです。
雷鳴の響く中、ぬかるんだ道を歩き、私はやっと目的の墓地に着きました。そして、墓碑に刻まれた文字を確認してから、くるりと背を向けて座ります。
雨に打たれ、ずぶ濡れになりながらも、それでも私は傘をさす気すら起きませんでした。むしろ、そんな雨の冷たさを欲していたのです。
耳元で、雨の音だけが響き、驚きつつも、それがむしろ心地よいとすら感じた――そのとき。
「暦法は間違っているな。こんな悪天候の時期に、わざわざ出かける気になどならぬ」
慣れ親しんだ男性の声が、不意に雨音に交じって聞こえてきた。私はハッとして振り返る。
でも、そこには誰もいない。雨に打たれる墓碑だけがあった。わかっている、今の声はただの幻聴……私の遠い記憶が蘇らせた想い出の声。
――だって、彼はもう戻ってこないのだから。
墓碑に書かれた文字に手を触れる。そこに、かつて何度となく呼んだ名を確認し、私は彼がもうこの世にいないのだということを改めて思い知る。
気づけば目に涙があふれていた。涙で前が見えなくなってからそのことに気付き、慌てて袖で顔を拭う。そこには、雨と涙で落ちたおしろいがついていた。
「御侍様、貴方は綺麗な女性がお好きでしたよね」
無理やり笑みを浮かべて、私は墓碑に向かって話しかけた。
「あのとき『お前も化粧を覚えたら綺麗になるだろう』って言ってくれたこと、覚えていますか?」
かつての御侍様の姿を思い浮かべ、私はまっすぐに墓碑を見つめる。
「だから、今日、初めて化粧をしてみたのです。私のお化粧、どうですか?よもぎ団子は……綺麗になりましたでしょうか」
しかし、その問いに答える者はない。私は悲しくて、もう一度、袖で涙を拭った。
「……どうして何も言ってくれないんです。私のお化粧が見るに堪えないからですか?」
私はひとり、訥々と語る。在りし日の御侍様を脳裏に描いて。
「だったら、ここに来て、好きなだけ私のことを笑ってください……どれだけ笑ってくれてもいいから、だから」
そう語りかけるも、当然返す言葉はない。私は耐えきれなくなり、顔を手で覆った。
――返事がないことなんて、わかっている……。
御侍様のいない現実に、私は嗚咽を漏らした。苦しさが胸に留まらず、全身に広まって、どうしようもない無力感に襲われた。
「御侍様……!」
掠れる声でつぶやいたその声は、無残にも雨音によって掻き消される。それと同時に、私は御侍様と別れたそのときのことを想い出した。
Ⅱ 逃亡
それは、薬草を採りに来たある日のこと。突然現れた外敵に、御侍様は私の手を掴んで、勢いよく山を駆け下りていた。その背後からは、恐ろしい笑い声が聞こえている。
「御侍様……!」
「振り返るな、前だけ見ていろ!」
私たちを追ってきているのは、体に鎖を巻きつけて酒の樽を引きずり、全身から黒い炎を纏った堕神という名の化物だった。
本来食霊である私は、その化物から御侍様を守るのが役目である。だが、御侍様の方が私よりもずっと勇ましく頼りになった。
そのときの私は、何をすればいいのかすらわからずに、ただ御侍様に必死についていくことしかできなかった。食霊として、なんとも恥ずかしいことである。
そこまで山奥に入り込んだわけではない。こんな山のふもとで堕神に出遭うなど、本当に運が悪い。どうしてこんなことになったのだろう。
しゃくり泣きをする私をなだめ、時に檄を飛ばしながら御侍様は私を引っ張っていく。そうして、二つの山を繋ぐ架橋に行き着いた。
御侍様は橋の中程で立ち止まり、息を乱している。私はそんな御侍様を見て、頭が真っ白になってしまい、呆然と立ち尽くしていた。
「はあ……はあ……よもぎ団子、お前は先に行け」
そう呟いて、彼は薬箱を私に渡した。
「これを持っていけ。これがあれば、あの患者は助かる……!」
御侍様が叫んだそのとき、私は地面に片膝をついている御侍様の右足が血まみれになっていることに気づいた。
「御侍様……!その足……!」
「いいから!早く行け!」
御侍様は私の背を押して急かした。
「だ……だめです!私が御侍様を支えて橋を渡ればいいのです!」
さぁ、と私は薬箱を置いて御侍様を支えようとした。
「お前……」
御侍様は戸惑った様子で、私を見上げる。その瞬間、堕神の笑い声が高らかに響いた。
(……近い!)
「早く行きましょう御侍様!」
私の言葉に御侍様は小さな溜息を引き換えに、大人しく私に体を委ねてくれた。その手に、しっかりと薬箱を持って。
私は御侍様を支えて躓きながらも、なんとか橋を渡っていく。
必ず御侍様と一緒に帰るんだ――その熱意で、橋の半ばを過ぎる。そのとき架橋が激しく揺れ、耳を突き刺すような笑い声が聞こえた。
「ギャハハハハ――」
振り返ると、そこには堕神の姿があった。もう橋のたもとまで辿り着いたのか。
次の瞬間、堕神は酒の樽を振りながら飛び上がった。黒炎で燃えた酒が雨となって私たちに降り注いできた。
「御侍様!」
「行け!お前ひとりなら、逃げられる!」
御侍様は有無を言わさず薬箱を私に押し付けて、強く私の背中を押す。
その勢いで、私は橋のきわまで押し出されてしまう。
「御侍様ぁ……っ!」
力一杯叫んだが、その声は堕神の笑い声で掻き消される。
「ギャハハハハ――」
これは現実なのだろうか。目の前で架橋が崩れ、堕神は御侍様を道連れに淵に落ちていった。
堕神の声が聞こえなくなるまで、私は呆然とそこに立ち尽くしていた。
――その後。
私は荒れた山道を辿って、ようやく淵の底で御侍様を見つけた。
彼の体は既にボロボロで、あちこちに恐ろしい傷口が刻まれ、地面を赤黒い血で染め上げていた。
あんな淵から堕神と共に落ちたのだ。覚悟はしていたが、いざ目の当たりにすると、その現実は否応なしに私を絶望に陥れる。
「お前は先に行け!」
いつも優しく、飄々としていた御侍様。彼があんな逼迫した表情をするなんて、私はあのときまで知る由もなかった。
最後まで私を見捨てず、私を生かしてくれた御侍様。
(もう、御侍様に会えないんだ)
その悲しい事実に胸を締め付けられ、私の記憶はそこで途切れた。
それから、ふたたび目を覚ましたとき。私は見知らぬ女性に背負われていた。
彼女の名は――お屠蘇。御侍様と同じように、私にとって特別な存在となるその人だった。
Ⅲ お屠蘇姉さん
御侍様の傍で意識を失い、目を覚ましたとき、私は誰かに背負われていた。のちに彼女がお屠蘇だと知るわけだが、そのときはまだ彼女のことがわからなかった。けれど、温かい背中だな、とぼんやり思ったことは覚えている。
そのときも今のように、耳には変わらず激しい雨音が聞こえていた。しかし、私の体に打ち付ける雨はない。
雨は止んだのだろうか? 不思議に思って顔をあげると、黒い傘が私の頭上を覆っていた。お屠蘇が私が濡れぬよう、傘をさしてくれていたようだ。けれど、お屠蘇は傘から外れてその体を濡らしている。こうした優しさがお屠蘇にはあった。
「よもぎ、どうかしたの?」
その声と同時に傘を差し出され、我に返る。御侍様の墓の前で、どれほどの時間を過ごしていたのだろうか。
「傘もささずにこんなところにいたら、風邪をひくよ」
その声に振り返ると、そこにはお屠蘇の姿があった。雨が降っても戻ってこない私を心配して、お屠蘇は迎えに来てくれたようだ。
「どうしてここに?」
「あんたはよくここに来てるみたいだからさ。に、してもひどい顔だね。化粧の仕方、教えてあげようか?」
そうだ。御侍様と別れたあの日から――お屠蘇に助けてもらってから、もう幾日も経っていた。昨日のことのように思い返せるというのに、奇妙な感覚に襲われた。
あの日。お屠蘇は、堕神を追ってあの山を越えてきたらしい。そんなお屠蘇に、私と御侍様は見つけてもらった。私は霊術を放ちながら、御侍様の体に寄りそって気を失っていたようだ。
お屠蘇にはずいぶんと世話になった。こうして御侍様の墓碑を建てられたのも、お屠蘇の協力があってこそだった。
「……すみません。あの日のことを思い出していました」
「なるほどね。ま、仕方ないさ」
ポン、とお屠蘇が私の背中を軽やかにたたく。その優しい温もりに、私は自然と笑みを浮かべた。御侍様がいなくなったことは悲しい。けれど、お屠蘇の存在が、私の悲しみを大分和らげてくれていた。
お屠蘇と共に、私は御侍様と住んでいた医館へと戻ってきた。
助けてもらったお礼に、私はお屠蘇に医館で過ごすことを勧めた。ここなら宿代もかからない。私はまだひとりでここにいるのは辛かったので、お屠蘇の存在は有難かった。
「ねぇ、よもぎ。私と一緒にこの町を出ない?」
ご飯の時、不意にお屠蘇はそう聞いてきた。一瞬驚くも、その顔は真剣な表情で、私は慎重に答えを返す。
「ありがとうございます、お屠蘇姉さん。でも、私はここに残ります。御侍様の医館を続けたいのです」
「医術なんてあんたにわかるの?大体、この町の奴らはあんたのことをよく思っていないじゃない」
彼女は眉を顰めて、少し拗ねた様子でそう言った。
お屠蘇は、医館に泊まってる間に私を取り巻く現状をそれなりに理解してくれたようだ。
御侍様の家は医療の名家で、私は薬の種類が分かるただの雑用でしかないこと。
そして、町の人たちは私のことがあまり好きではないこと。これは、悲しいことだけれど、事実だった。
御侍様に仕え始めたばかりのときは、まだそれほど風当りは強くなかった。けれど、それから数年経っても、私の容貌は全く変わらない。食霊なのだから当然なのだが、そんな私を見て、街の人たちは妖怪だ化物だと噂をし始めた。
彼らとて食霊という存在を知らないわけではない。ただ、何か良くない事が起こった時には、未知なるものに責任を押し付けたがるだけ。人として当たり前のことだろう。
今回のことだって、戻ったときにさんざん言われた。
「張さんは彼女のせいで死んだのだ!」
彼らの言葉は本当かも知れないと、私は思う。私がいなければ、御侍様は死ななかっただろうと思うから。
部屋の角には、あの日御侍様に渡された薬箱が置いてある。無事薬は患者に届けられた。御侍様が自分の命と引き換えにして託したあの薬のお陰で助かったのだ。
だからこそ私は、御侍様の願いはこの医館で一人でも多くの患者を救うことだと認識している。
「お屠蘇姉さん。私を誘ってくれてありがとうございます。とても、嬉しかったです」
私はまっすぐにお屠蘇を見つめ、そう伝えた。
「よもぎの願いは、とても難しいことだと思うけど……それでもやるの?」
「はい。どれだけ難しくとも、私は御侍様の遺したこの医館を継続させたいんです」
お屠蘇は、それ以上何も言わなかった。
「またいつか。きっと、あんたなら大丈夫さ」
そう言って、お屠蘇は去っていった。そのとき、置き土産として私に化粧道具をくれた。いつか、私が彼女に御侍様の話をしたことを覚えていたのだろう。
化粧道具は選ぶものによって見栄えが変わる。この色はきっとよもぎに合うだろう、とお屠蘇は笑った。その笑顔は美しく、私にはとてもまぶしく映った。いつかお屠蘇のように綺麗になりたい、と素直に思えた。
言葉にはしなかったが、彼女がここを離れたことは、正直寂しかった。だが、お屠蘇は元々ここの人ではない。最初から、長く留まるつもりはなかったのだろう。
そもそも彼女の差し伸べた手を振り切って、残ることにしたのは自分だ。だから仕方ない。私は笑顔で彼女を見送った。
それから、私は医館の継続に力を注ぎ始めた。
残念ながら、私は薬を見分けることしかできない。医療の基礎知識がないので御侍様が残した本を見てみたが、やはりよくわからなかった。
仕方なく、私は他の医者に助けを求めることにした。労働力を対価にし、勉強の機会を得たいと考えた。もちろん、すんなりとことが進むとは思っていない。それでも、前に進みたかったから、こんなところで立ち止まってはいられない。
迷うときは、いつも御侍様を思い出す。あんなに緊迫した状況の中でも、御侍様は薬箱を離さなかった。きっと彼にとって、医者として人を救うという使命は、何にも代え難いものだったのだろう。
御侍様に救われたこの命、少しでも彼のために使いたい。
医術を習い、彼が残した医館を経営する――それが彼のためにできる、唯一のことである。私はそう思った。
Ⅳ 仁なる心
医学の道は私が思ってた以上に険しかった。
「光耀大陸には古くから伝わってきた訓令が有る。一族の宝は男子に伝え、女子に伝えることなかれ」
これは町で最も古参の医者である頑固なお爺さんの言葉。
「これは我が一族の医術であり、門外不出である。帰ってくれ、お嬢ちゃん」
これは町の鍼灸名家の者の返事。
「食霊が人類の経脈を習うだと?笑い話にもならない!」
町の湯薬屋のおじさんが私を嘲笑った。私が妖怪だと噂を流したのがこの人の奥さんだと、御侍様から聞いたことがあった。
それでも私は、僅かでも可能性があるなら、と門を叩いた。御侍様の医館を続けるためなら、多少のことでは揺るがない。その覚悟はできていた。
「食霊に教えることなんぞないわ!帰った帰った!」
青年がそう叫び、医館の門が閉められる。私は小さく嘆息する。
(またダメでした……)
だが、こんなところで挫けるわけにはいかない。私は頭を切り替えて、次の医館を探そうと地図を取り出した。
そこで、さっきのが最後の一軒だと気づいた。
医館八軒、薬屋五軒。例外なく、全て断られた。
(御侍様、これからどうしたらいいのでしょうか)
疲れた体を引きずって家に帰った私は、御侍様の写真を抱えてベッドで身を縮ませた。そして、写真の中の御侍様の笑みを見て、私は泣きたくなってしまう。
「バカバカバカ……泣いてる場合じゃ、ないですよ」
強く目を瞑り、泣くのを堪える。明日にはきっと、道が開けるはずだ。
そう信じて、私は眠りについた。
翌日。私は、ひとまず薬草の販売を始めることにした。
医術が学べないなら、薬草を取ってくる依頼を受けるとか、簡単な病状を治せる薬を出すとかで医館を維持すればよいと考えたのだ。
だが、それだけでは足りない。そんなことは、私もわかっている。医術が学べなければいずれ医館は潰れるだろう。
そんな焦りをどこかに抱えつつも、私は今やれることに全力を注いだ。
薬草の在庫が足りなくなって、私は夕方もう一度山に採りに行くことにした。
「お屠蘇姉さんが、このあたりの堕神を掃討したって言ってたし、大丈夫ですよね」
私はそう自分に言い聞かせた。
そして目的の薬草を手に入れ、山を下りていたとき。しゃがみこんでいる老人に出くわした。それは、最初に私の弟子入りを断ったお爺さんだった。
お爺さんは、足を捻って動けなくなっていたと言った。私はそんな彼を背負って山を下りる。
「お爺さん、何をしていたのですか?」
「うむ……孫娘と勝負をしてな。薬草を採りにきた」
老人は気まずそうに答えた。
「まだそのくらいのことは、儂一人でやれるということを証明してやりたくてな」
「だからって夜の山は危ないですよ。一人で来るようなことは、やめたほうがいいと思います」
ピシャリと言って、少し厳しい口調になってしまったかも、と私は心配になった。
「……恩を売っても医術は教えられないぞ」
老人は警戒した口調でキッパリと告げる。私が弟子入り志願をしたから用心深くなっているようだ。私は思わず笑ってしまう。
「そんな理由であなたを助けたわけではありません。御侍様が教えてくれたのです、医者心は親心だと。お爺さんも分かっているんでしょう? 私は薬草を見分けることしかできませんけど」
「……張。そうか、お前は奴の弟子だったか」
そこで老人は長い溜息をついた。
「いったい奴に何があったんだ? 教えてくれ」
私は少し戸惑いを覚えたが、御侍様は、彼の話をよくしていた。個人的に交流があったのだろう。だからこそ、一番最初に弟子入りの件で伺った経緯がある。
そんなことも手伝って、私は彼にあの日のことを話すことにした。
「御侍様は、私を助けるために自分を犠牲にしたのです」
ちくり、と胸が痛む。まだあの日のことは思い出にできていない。生々しい情景が一気に私の中を支配する。慌てて私は頭を振った。
「だから、町の人たちの言っていたことは正しいかもしれませんね。私がいなければ、御侍様は命を落とすことはなかったでしょう」
「……お前は」
そう言いかけて、老人は言葉を噤む。何を言おうとしたのだろう? わからないが、彼は代わりに小さく嘆息した。
「なぜお前はまだここにいる?張はいなくなったというのに。お前みたいな……うむぅ、なんと言ったか……」
「『食霊』のことでしょうか?」
「ああ、そうだ。食霊、か……そいつは、主人がいなくなったら自由になるんじゃなかったのか?」
その言葉に私は肩を竦めた。
「私たちはペットではありませんよ。御侍様に仕えている存在です。最初から自分の意思で、御侍様に仕えています」
私は御侍様に仕え始めたときのことを思い出す。この人の傍にいたい、守りたいと強く願った。
「私は御侍様の願いを叶えたいです、彼にどんな願いがあるか今となってはもうわからないですけど」
私は空笑いで息を吐く。それと同時に、あの日託された薬箱のことが頭に浮かんだ。
「御侍様は、あんな緊迫した状況でも、決して薬箱を離さなかったんです……だからきっと御侍様は、医者としての使命を何よりも大事にしていたんじゃないかって思っています」
「だから医術を習おうとしているのか?金を稼ぐためじゃないというのか」
「私は人間と違って、お金をそんなに大事だと思っていませんから」
「……そうか」
老人は、暫しの沈黙後、突然口を開いた。
「志は立派なようだがな。それでも我が家の医術は教えられん」
「安心してください。そんなつもりはありませんから。お爺さんの家の医術は、男子にだけ伝えるんですよね?」
「そうだ。わかっているならいい……」
そう結び、お爺さんは低い声で唸る。
「あー、なんだ。お前さんの名前はよもぎ団子だったな? 張に教わって薬草の知識があると」
「ええ、そうです。御侍様から教えていただきました。ですので、薬草については任せてください」
「うむ……そうじゃない、そうじゃなくてだな。その、儂はなぁ……医術は教えられないが……」
お爺さんは言葉を詰まらせる。
「お前の家に、張が残した本があるだろう。それを読むのだ。あれは儂が渡したもの。だから、もしわからないところがあれば……儂に聞けばわかるだろう」
「その……それは、お爺さんが教えてくださるということですか?」
思わぬ展開に、私は驚きつつ聞いた。
「弟子にはせぬぞ。お前が本を読んでわからないことがあれば、助言くらいはしてやるという話だ」
老人はそこで咳払いをし、苦い表情を浮かべた。
「それと、もうひとつ。あくまでお前にしてやるのは『助言』だ。間違っても弟子などではないからな。よくよく認識しておけ」
お爺さんはフン、と息を荒げ、私を睨んだ。最初のときとは違う、優しさを含んだ口調だった。
「お爺さん……いいえ、師匠。なにとぞ、よろしくお願いします……!」
そうして、私はお爺さんの元に通うことになった。それは、なかなかに大変な日々だった。それでも医館のために前へと進めたことが私は嬉しかった。
(ね、御侍様……これからよもぎは、医術を学びます。御侍様の医館を継続させるために頑張りますから、遠いところからどうか、見守っていてくださいね)
Ⅴ よもぎ団子
中草町は、光耀大陸では有名な医術と薬の町だ。
他の地域からすると、この町の優れた医術と厳格な規則は特に印象的に映るようだ。
だがこの町の医師たちは、他国と文化交流することはなかった。外に技術が漏れることを防ぐため、内々でその技術を語り継いでいた。
このような町は、光耀大陸みたいな保守的な国の中にも、他に例を見ない。
食霊に対する態度も、中草町は他とは違っていた。今では世界的に知られた食霊たちだが、彼らは食霊を嫌っている。
堕神に関しては、町に食霊をとどまらせたくないため、料理人ギルドを経由して料理御侍にお金を払い、退治させていた。
だが、一人の可愛らしい少女がその状況を変えた。彼女の名前はよもぎ団子。張という医者の助手として町で働いていた食霊である。
よもぎ団子が町にやってきたとき、少女の外見をしている故、中草町がどれだけ食霊を嫌っていても、彼女を追い出すような真似はさすがにできなかった。
外見に加え、よもぎ団子の性格がとても温厚であったことも起因しているだろう。
そんな経緯を経て、徐々に町の者たちは彼女の存在に慣れつつあった。たまに妙な噂話は出るものの、基本的には平和であった。
だが、よもぎ団子と彼女の御侍が堕神に遭遇したその日に、事態は一変する。
基本戦闘力を持たない食霊と普通の人間が堕神に遭遇したら、結果は言うまでもなかった。
だが、よもぎ団子は御侍の犠牲のお陰で生き残った。その事件後、食霊に対する良くない噂は再び囁かれ始めた。
食霊は不吉だの、厄災をもたらすだの、人を死なせるだの――このような噂は絶えなかった。
それは全部いわれのない中傷だが、そもそも人間にとって食霊も堕神も理解しがたい存在であった。
同じ外見をしている生き物なのになぜ食霊には特別な能力があるのか、なぜ老いさらばえることがないのか、人間は理解できないからだ。
しかし、よもぎ団子はそのような中傷に決して屈しなかった。報復することも、ここを離れることも選ばなかった。彼女は人々の悪意に晒されても、御侍が残した医館を守るために努力を重ねた。
『善意』、それは世界を変えられるもの。
まずはよもぎ団子が医療を学ぶのに手を貸してくれた老人、それから町の子供たち……そうして徐々に、町の人たちはよもぎ団子のことを受け入れ始めた。
そして、中草町の食霊に対する見解も再び変わり始めて、その存在を受け入れ始め、中草町は食霊を歓迎する町へと変わった。
よもぎ団子は、時折老人の手を借りながら、御侍の遺した本から医療について学び、張の医館を大賑わいさせるほどに成長させた。
よもぎ団子の心から御侍の存在は消えることはなかった。けれどもう、彼を思い出して泣くことはない。
そんなとき、思い出したのは、かつて御侍と自分を助けてくれた強い女性のことだった。
お屠蘇からはたまに手紙が届いていた。今は忘憂舎というところにいるらしい。
それは、どんなところなのだろう、とよもぎ団子は想いを馳せる。まだ知らない世界が、この町の外に広がっている。
「今なら、私がいなくても、みんながいるから、医館は大丈夫です。私は御侍様が残してくれた本から学んだ医術でより多くの人を救いたいのです」
誰も反対する者はいなかった。医館の皆は「ここは自分たちに任せてほしい」と、旅立つよもぎ団子のことを応援してくれた。
そして、よもぎ団子は中草町から旅立った。
さて、どこに行こう?よもぎ団子は期待で胸を膨らませる。
中草町を出る前に、お屠蘇へと手紙を出した。旅の途中に、忘憂舎に寄れたらと思ったからだ。きっと彼女は歓迎してくれるだろう。
あれから、化粧の仕方も覚えた。きっとお屠蘇はそんな自分を見たら驚いてくれるはずだ。そんなことを思うと、自然に笑みがこぼれた。
この旅で、やりたいことはたくさんあった。
食霊が人間を守るだけでなく、人間が食霊を守るために自分を犠牲にすることもあるって、みんなに教えてあげたい。
私の大切な御侍様のことを、みんなに伝えたい。
「私は人間と食霊の仲を取り持つ架け橋になりたい……!」
そんな熱い想いを胸に、よもぎ団子は歩みを進めるのだった。
◀ エピソードまとめへ戻る
◀ よもぎ団子へ戻る
Discord
御侍様同士で交流しましょう。管理人代理が管理するコミュニティサーバーです
参加する-
-

-
ななしの投稿者
116年まえ ID:gc1f1kur5話 その3 お願いいたします。
-
-
-

-
ななしの投稿者
106年まえ ID:gc1f1kur5話 その2
-
-
-

-
ななしの投稿者
96年まえ ID:gc1f1kur5話 その1
-
-
-

-
ななしの投稿者
66年まえ ID:p6dny72aよもぎ団子エピ1 ラスト
-
-
-

-
ななしの投稿者
56年まえ ID:p6dny72aよもぎ団子エピ1
-
-
-

-
ななしの投稿者
46年まえ ID:p6dny72aよもぎ団子エピ1
-
-
-

-
ななしの投稿者
36年まえ ID:p6dny72aよもぎ団子エピ1
-
-
-

-
ななしの投稿者
26年まえ ID:p6dny72aよもぎ団子 エピ1
-
-
-

-
ななしの投稿者
16年まえ ID:p6dny72aよもぎ団子 エピ1
-