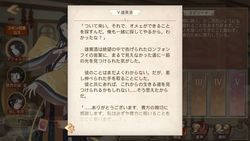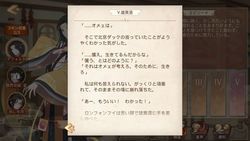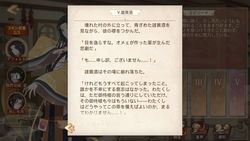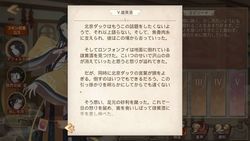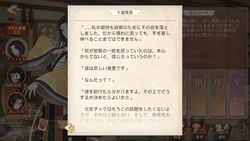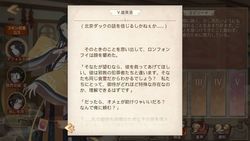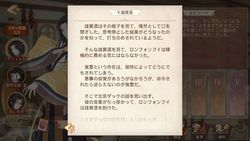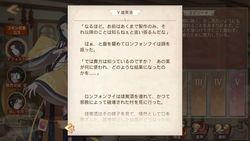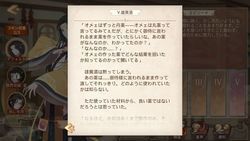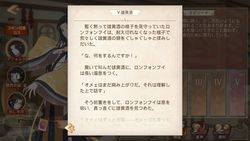雄黄酒・エピソード
◀ エピソードまとめへ戻る
◀ 雄黄酒へ戻る
雄黄酒のエピソード
情に流されたりせず、冷たい印象を与える男。
他の者と関わることを好まず、興味のないものには一切の関心を示さない。
守りたい者のためだけに努力し、全力で尽くす。
Ⅰ 院中雲
煙雲が渦巻いている朱色の部屋には、鼻を突く匂いが漂っていた。
木戸が叩かれて、わたくしは立ち上がり窓を押し開ける。すると、部屋の中から薄い黄色の幽かな煙を見つけた。わたくしは、慌てて窓から外に飛び出した。
それから暫くして。
わたくしはスカーフを外して口元に当て、部屋の中の様子をうかがう。そして、匂いがなくなったことを確認し、やっと部屋へと戻ってくることができた。
「あの方があなたの薬はいつできるかと聞いていましたよ」
入り口の前に立って侍従が告げる。その表情は、余裕がない様子だった。
わたくしは、先ほど作った丸薬を臼の中に入れて粉状にする。そしてそれを黄紙に入れて包み、侍従へと渡した。
「これは御侍様にとって大切な薬です。直接に手で触れてはいけないということを忘れないでください」
「わかった」
侍従は頷いて、足早に立ち去った。わたくしはそんな彼の後ろ姿を見て、小さく嘆息する。
(御侍様……)
わたくしは、不意にここに召喚されたときのことを思い出した。
目を覚ました時、御侍様は冥々の裡にわたくしの目の前に立って、鋭い眼光で射抜いてきた。
「雄黄酒ですね?貴方は私のために何をしてくれますか?」
その問いに、わたくしは返す言葉が見つからない。
(わたくしが彼のためにできることはいったい何ですか?)
突然の問いに何も答えられないまま、わたくしは御侍様の前で立ち尽くしてしまった。
「結構。答えられないのなら、私が教えてあげましょう。丹炉を使って丸薬を作ってください。貴方にはそれができるでしょう?」
その言葉に私は驚いた。
(私は薬を作れる……のだろうか?)
生まれたばかりの私には、わからないことだらけであった。
それでも目の前の人が「御侍様」であり、彼に突き従っていくべきであることだけは、本能的に理解した。
「現在、神教には薬が必要です。これから私たちのために、必要な薬を作ってください。あなたを召喚するために使った幻晶石を無駄にはできませんから」
結果を出してください、と御侍様は告げて立ち去った。
どうしていいかわからず、わたくしは狼狽えてしまう。すると御侍様の侍従と仰る方がわたくしを丹房へと案内した。
その後、侍従が丹房へ次々と原料と処方箋を届けてくるようになった。そして、黄紙を広げ、作った丸薬を出すように言われた。
原料にはありふれた薬草があり、極めて珍しい薬草もあった。その中には微妙なエネルギーを持つ鉱石もあった。
私はこの鉱石が何から採れるのかを知りたいと思い、彼に尋ねました。しかし、その答えは知らない方が良い、と言われてしまう。最終的には、どうか聞かないでくれとまで懇願された。
聞くまでもなく、この鉱石に付着しているエネルギーが食霊の霊力だと感じ取れた。
だから彼らの態度で、この鉱石が何なのかわたくしは確信してしまう結果となった。
御侍様に呼び出されて以来、わたくしはほとんどこの丹房から離れたことがなかった。
たまに休みを与えられたりもしたが、わたくしは丸薬を作る以外のことは何も知らないのだ。だから、わたくしはそんな休みをいつもベッドに腰かけて、窓から除ける狭い空を見つめていた。
――わたくしは、なぜここにいますか?
――何のために、存在していますか?
この、良いものだとは到底思えない丸薬。
それをわたくしは作り続ける。
(何故か?それは御侍様が求めるから)
それ以上の理由はいらなかった。
わたくしを召喚した御侍様がそれを求めていたから。
わたくしに丸薬を作ってくれと頼んだから……わたくしは言われるがまま、丸薬を作り続けるのです。
こうした休みの日は、ついこんな取り留めのないことを考えてしまう。
早くまた丸薬を作りたい。そうしたら、自分の存在意義など、考えなくても済むから。
わたくしは決して「NO」とは言わない。御侍様の求めるまま、わたくしはただただ頷き、言われるままに丸薬を作るのです。
それから数日後。
御侍様に呼び出されました。
何事かと思うものの、それに対して異議を唱えるようなことはなにもない。
わたくしはただ頷いて、御侍様の言うことを聞くだけです。
カップのお茶を飲み干して、わたくしは急いで出掛ける準備し始めました。
支度を終えたわたくしに、御侍様は言いました。
「今日は聖主様に会いに行きますよ」
「聖主……様」
それが誰なのか、何故わたくしがついていく必要があるのか……何もわからない状態でわたくしは頷いて、御侍様と共に丹房を後にした。
Ⅱ 春寒の夜
「桜の島のことは貴方にお任せします」
「ありがとうございます、聖主様! 使命に恥じぬよう、立派に務めを果たします!」
わたくしが謁見の間のドアを開けた瞬間のことだった。聖主様の前に立つ見知らぬ男が胸を張って堂々と叫んでいた。
誰だろう、と気になったそのとき、男がクルリと振り返る。男は半分だけお面で顔を隠していた。やはり、知らない男である。
(わたくしが知っている者は御侍様と、研究室で会えるごく一部の人間しかいないので、当然ではあるのだが)
男は私に目を向けることもなく、颯爽と横を通りすぎていく。わたくしはそんな男の姿を目で追った。彼の着ている服は、光耀大陸では珍しい狩衣だ。わたくしはそんな彼が気になった。
「雄黄酒!」
「……はいっ!」
わたくしは御侍様に呼ばれてハッとする。と、同時にドアが閉まる音がした。男がこの部屋から立ち去ったのだろう。そして、御侍様に呼ばれてしまったわたくしには、もうその男に関心を寄せていられる時間はない。
私は御侍様の後ろを静かについていく。その間、わたくしは横目で部屋の様子を観察する。
窓からは白い光が漏れている。目を細めないと眩しかった。何故、御侍様はこんなところにわたくしを連れてきたのだろうか?
そんな疑問を抱く中、わたくしは御侍様と共に聖主様の前に立った。
その瞬間である。勢いよくカーテンが引かれる音がする。室内は僅かな隙間から差し込む光のみでひどく薄暗い。
(何故急にカーテンを?)
御侍様を見るが、彼はゆっくりと跪く。どうやら質問をできるタイミングではないようだった。だから、わたくしも彼に倣って、その場に跪いた。
「この先の道のりは幾多の困難が待ち受けている。汝はこの座の左腕であるから、危険を冒すべきではない。しかし、様々な検討を重ねた末、やはりこの重荷を背負えるのは貴方しかいないと感じました」
軽やかに語られる聖主の言葉に、御侍の呼吸は荒くなり、頬も高揚で赤く染まる。
「ありがとうございます!」
御侍様は聖主様に向かって、床に額が擦れるほどに頭を下げた。
「聖主のお言葉に必ずや報います……!」
そして謁見の間を後にした御侍様はひどくご機嫌だった。
丹房に戻ってからも、ずっと笑みを浮かべている。その様子にわたくしも嬉しくなった。
(御侍様の笑顔を見られたのはいつぶりでしょうか……!)
少なくともわたくしに向かって、ここまでの笑みを浮かべてくれたことはない。
御侍様につられるようにしてわたくしも自然と顔が綻んでしまう。
すると、御侍様は私の方を勢いよく叩く。
「雄黄酒、よくやった!お前が作った薬でなかったら、聖主様は今回のような機会を私に任せてはくださらなかっただろう!」
そう言って、なんとも嬉しそうに目を細めて御侍様が高笑いをする。
「……ありがとうございます」
「早く自分のものを片付けに行きなさい。近いうちにここを出ます」
「承知しました」
御侍様は笑顔のまま、背を向けて去っていく。その笑顔に、わたくしは長い間悩んでいた問題の答えがようやくわかりました。
――わたくしは、御侍様に認めてもらいたい。
今、とてもわたくしは嬉しい。御侍様が喜んでくれたから。
わたくしが頑張ったことで、御侍様が喜んでくれる……こんなに素晴らしいことがあるだろうか?
わたくしは、彼の言う通りに努力したらいい。そうしたら、彼はわたくしを認めてくれる。
(これからも努力を惜しまぬようにしよう。御侍様に笑ってもらえるように)
わたくしはそう決意した。
これから何があっても、御侍様のために。
あの方が喜んでくれることのために、努力をし続ける……!
わたくしは生きる道が見えて、自然と笑みを浮かべてしまう。
(わたくしは御侍様の言うことを聞いていたらいいのだ。もう悩むことは何もない……!)
私は久々に晴れ晴れとした気持ちで部屋へと戻った。
***
わたくしは御侍様に付き従って、寂れた村へと向かった。
そこは、人間には住みづらい土地だと御侍様から聞いていた。だが、それにしては多くの人間が集まっていて、わたくしは大層驚いた。
彼らは、顔が凶悪で下品な言葉使いをする大男という特徴があった。あと、お洒落なお嬢さんたちも多く見かけた。
また、彼らには『罪人』という共通点があった。どうやら彼らは集ってここに逃げてきていたらしい。
そのことに私が気づいたのは、ここに来てから随分後のことだった。
彼らは多くのお金を持ってここにいた。そのお金は、この住みにくい土地を楽園にするのに十分だった。
しかし、それらのことは、当時のわたくしにとっては問題ではなかった。
そのときのわたくしは、丸薬を作ることだけに熱中していた。
彼の言う通りにしていれば、喜んでもらえれる……それ以外のことには、まるで興味がなかったのだ。
だから、外部の変化に、全く気づくことはなかった。
わたくしの生活はかつてと何ら変わらない。
毎日、丸薬を作る研究に明け暮れていた。夜も昼もない日々を送っていた。そうして、御侍様に会う回数も日を追って少なくなっていったと今になって気づく。
当時のわたくしは、研究に夢中だった。
御侍様に喜んでもらうには、言われるままに丸薬の開発をするしかなかった。
あのときを振り返ると、丸薬を作っていた想い出しかない。あとは御侍様に褒められたこと以外、私が思い出せることはなかった。
ただひとつだけ――それは、些細な出来事ですが、記憶に残っていることがあった。
煙管を手にした男が、夜の闇に紛れてやってきた。勿論、見覚えのない者である。
彼はわたくしの丹房をゆっくりと見回してから、柔らかな笑みを浮かべて言った。
「ここから離れた方がいいですよ」
その質問の意図がわからず、わたくしは彼を見つめる。わたくしにはここから離れる理由がない――何故、この男はそんなことを言ってくるのかまるで見当がつかない。
だからわたくしはその申し出を丁重に断った。
わたくしはかつてとは違う。今の生活に、満足していた。
そもそも御侍様がここにいる時点で、わたくしがここから離れる選択肢はない。
片眼鏡の男は、小さく頷いて近くの椅子に座った。
そしてそのまま窓の外を眺めている。
(何をしているのだろう……?)
わたくしの丹房にやってくる者はこれまでもいなかった訳ではない。
だが、彼のようにこうして寛いだ者は初めてだった。
目的がわからない。ただ、わたくしに危害を加える様子は見えなかった。
わたくしは寝床に腰を下ろし、彼と同じように、窓の外に目を向けた。
――そこには、大きな月が見える。
わたくしはたまに、ひとりでいることに退屈すると、窓の外に目を向けることがあった。
今思えば、そうして月を眺めることが好きだったのかもしれない。
あの日見た月光は格別に輝いて見えた。空には雲がいくつか浮かんでいたが、その暖かい光を遮ることはなかったと記憶している。
早く帰ってくれればいいのに、と思う。どうやって相手をすべきか、初めての経験にわたくしは戸惑った。
わたくしはどうしようもなく、ただ窓の外を見ているしかできなかった。
ふと視線を落とすと、庭に咲いている素晴らしい桃の木が見えた。その日は、桃の花が満開の季節だ。桃の花びらは、わたくしがよく丸薬の残り滓を巻いている影響で、少し血の色を帯びている。
そよ風が吹き、真っ赤な桃の花びらがひらひらと地面に落ちる。その様子に男が感嘆の声をあげる。そしてゆっくりとわたくしを振り返った。笑ったままだが、その目は強い意志を持ってわたくしを見ている。窓から差し込む光が彼の片眼鏡を照らした。
彼は唇をゆっくりと口を開いた。するとそのとき、夜風が木の枝を揺らし、その声を遮った。彼の言葉はその音と混じり、よく聞こえない。
――彼は、私に何を告げましたか?
Ⅲ 荘周夢
御侍様に連れられてきた辺鄙な土地での生活は、淡々と過ぎていく。
この村に住む者たちに、最初は驚いたものの、今ではもう当たり前の光景となった。
基本的に丹房に籠って丸薬を作っていたので、彼らと関わる必要がなかったからだ。
わたくしは召喚されてからずっと丸薬を作っている。それがわたくしのやることであり、他のことはわたくしにとって余所事だ。
日々、丸薬を作っていた。
たまに研究が失敗してしまうことがあり、慌てて外に逃げ出したことあった。
そんな、たまの非日常に少しだけ新鮮なものを感じつつ、わたくしは日々丸薬作りに没頭した。
そうして開発した丸薬は、御侍様の立場をより崇高なものにした。
御侍様が喜んでいる。
あまり話しかけてくれなくなったけれど、それでいいのだ。
(これが、わたくしの望んだことだ)
何度も自分にそう言い聞かせた。この気持ちは、わたくしの心からの声である。
信じていたのだ、本当に。
――あの日までは。
***
その日も、いつものように朝から丸薬を作っていた。
少しでも質の高い、かつ良い丸薬を作るべく注力していた。
そんな中、突然の爆音が響き渡った。
また爆発したか――とスカーフで鼻を覆って、わたくしは慎重に目の前に意識を向ける。
爆発は、わたくしの部屋から起こった訳ではなかった。部屋の外から悲鳴と共に爆音は聞こえてくる。
状況を確認するため、慌てて丹房の外へと飛び出した。
灼熱の赤い炎が、目に見えるすべてを飲み込み、激しい爆発音と共に、暗い空を血色に染めていく。
立ち上る炎に動悸が激しくなる。鼻を覆うスカーフを手に、わたくしは廊下を駆け抜けた。
すると、守衛たちが怒声をあげ、館に置かれた金目のものに手を伸ばしているのが横目に映る。
わたくしはこの不可解な場面に異常なものを感じ取った。すれ違いざま、彼らが次から次へと懐に財物をしまっていくのが映る。
異様な光景に、たまらずそのうちのひとりを捕まえて話しかけた。
「何があったのですか?」
「どけ!ここはもう終わりだ!」
「落ち着いてください。御侍様はどこにいますか?」
「奴のことなど知るものかっ!」
「ここは終わり、とはどういうことです?いったい何があったのです!」
「うるさい!俺の邪魔をするな!」
守衛は鬱陶しそうにわたくしの手を振り払う。その勢いでわたくしは一歩後退する。
(御侍様は、大丈夫でしょうか……!?)
心の奥でわたくしは悲鳴をあげた。不安がどんどんと募っていく。
玄関から外へと飛び出し、わたくしは御侍様を見つけるために闇雲に庭を走り回る。
「御侍様!御侍様!御侍様っ!どちらにいらっしゃいますか!!」
そのとき、屋敷の裏庭の方向から言い争う声が聞こえる。
その片方が御侍様の声だった。
「御侍様!!」
わたくしが裏庭へと出ると、そこには御侍様といつか見た煙管を手にした男の姿があった。
わたくしは慌てて御侍様の前に飛び出す。
「雄黄酒……!」
御侍様の声は怒りに満ちている。
わたくしを睨みつけ腹立たしそうに怒鳴った。
「今頃来るとは……!まぁいい、早くこいつを殺せっ!!」
御侍様の体には細かな傷跡が見える。彼の向かいに立つ男は、無表情でわたくしに視線を向けた。
「この男はそなたを利用しています。それでも彼を守りますか?」
煙管を揺らしながら、男は目を細めて冷静に語り掛けてくる。
その言葉に、わたくしの心の奥でずっと燻っていた不安が顔を覗かせる。
(……御侍様が、わたくしを――)
私は強く手を握りしめる。
「雄黄酒!何をしている!私の言葉が聞こえないのか!?」
「あ……!」
わたくしは動くことができない。
ゆっくりと顔を上げ、御侍様と片眼鏡の男を交互に見る。
片眼鏡の男は、黙ったままだ。わたくしに思考する時間を与えてくれているようだった。
わたくしの周りを浮遊する丹炉が、淡く微かな霧を漂わせる。その煙は次第に私と御侍様を包み込んだ。
「そ、そうかもしれません……けれど、彼はわたくしの御侍様なのです……!」
煙管を一回振って、男は静かに嘆息する。まるでわたくしがそう答えると予想していたかのように、伏し目がちで小さく呟いた。
「……哀れな」
彼は悲し気な瞳でわたくしを見つめながら煙管を吸って、彼はゆっくりと吐息を漏らす。それは周囲の濃淡を変える煙ではなく、灼熱の炎であった。それは、迷わずわたくしと御侍様に向かって襲いかかってきた。
わたくしは御侍様を守るため、男の炎による攻撃をすべて受け止めた。
それは相当に過酷なダメージを与え、わたくしの足はすぐにぐらついた。
喉頭に血が溢れ、わたくしは堪らず咳こんでしまった。口から血が溢れ出し、御侍様の靴を赤く染める。彼は躊躇うことなく、不愉快な表情でわたくしを睨みつけた。
「お前など……もう必要ない!」
彼はそのまま身を翻して駆けだした。そのまま、御侍様は一度も私に振り返らずに、姿を消した。
(御侍様にとって、私は取るにならない『もの』なのだ……!)
わかっていた事実だが、その事実にわたくしはその場に崩れ落ちた。
わたくしの体力は限界に達していた。もう片眼鏡の男に立ち向かうことはできない。
(せめてもの慰めは、御侍様を無事に逃がせたことか……)
たとえ御侍様にとってわたくしが不要なものだとしても、わたくしにとっては命よりも大切な存在なのだ。
(だから……良かった。彼を逃がせたなら、本望だ――)
そう思い、わたくしは最後の覚悟を決め、顔を上げた。
これからわたくしは殺されるのだ、と。
もうその覚悟はできていると、まっすぐに片眼鏡の男を見上げた。
すると男は、御侍の去った方向に手を向ける。もしや、御侍様を狙っているのか!?
「あっ……!」
わたくしが止める間もなく、男の手から熱い炎の群れが、御侍の消えた方向へと飛ばされる。
その瞬間、これまで強固に感じていた御侍様との繋がりがプツリと切れたような気がした。
(御侍様の命が尽きようとしている……!)
微かな命の灯びを感じながらも、わたくしは絶望を覚える。このまま放っておけば、御侍様の命は尽きるだろう。
「仕損じましたか……ならば、もう一回」
冷たい声で男が言い放つ。
その恐怖にわたくしは背筋が凍る感覚に陥った。
「待――って、ください……!」
わたくしにはもう、立ち上がる体力は残されていない。それでも最後の気力を振り絞り、震える手を目の前の男に伸ばす。
「まだ……守ろうとしますか」
嘆息と共に、男は憐れみの表情をわたくしに向けた。そして、掲げた手を下ろす。
「相当な怪我を負わせた筈です。放っておいても、そう長くはもたない。そなたの熱意に免じて、追撃はやめておきましょう」
わたくしは心底ホッとして胸を撫で下ろす。
既にわたくしは、霊力のコントロールができなくなっていた。
この男の慈悲で逃げ延びた御侍様が助かってくれることを一心に願い、わたくしはそのまま地面に全身を預ける。
意識が遠のいていくのを感じる。このままわたくしは消えるのだろう――
たとえ御侍様にとって必要のなかった存在でも……わたくしのしたことは、少しは御侍様のお役に立てた筈だ。
(だったらそれでわたくしの生まれてきた意義はある筈だ……!)
悔やむことはない。
(御侍様が一秒でも長く生きられる役に立てたなら、それで本望だ)
そう思って目を伏せたとき、体が温かくなったのを感じた。
僅かな霊力がわたくしの体に注力される。目を僅かに開くと、男がしゃがみこんでわたくしに手をかざしているのが微かに見えた。
「吾ができるのは、ここまで」
平然としているが、彼自身も相当な怪我を負っているのは、見ればすぐにわかった。
男は胸元を抑え、ゆっくりと立ち上がる。
「……ダック!」
そのとき、急な叫び声と共に女が一人で現れた。
「ああ、よく来てくれましたね。もうすべて終わりましたよ。帰りましょう」
「彼は……?」
「そこまで面倒を見る義理はありません」
微かに笑いながら、男が言った。
女は男の言葉に頷いて、満身創痍の男に肩を貸して立ち上がらせる。
「生き延びられるかは、そなた次第です」
そんな言葉を残し、男は女に身を預け、わたくしに背を向ける。
(どうやらわたくしも、見逃されるようだ)
わたくしの気がかりは御侍様のことだけだった。
今すぐ立ち上がって、御侍様の無事を確認したかった。
だが、わたくしには既に御侍様との繋がりを感じ取れるだけの霊力は残されていなかった。
片眼鏡の男から与えられた僅かな霊力と自らの力で生き残れるか否か?
それすらわからなかった。
(もう指一本動かせません……)
わたくしは御侍様の無事を祈りながら、掠れる目で立ち去る二人を見送った。そうして目の前はまっ白な霧で覆われる。意識も次第に遠のいていった。
――その後、わたくしに訪れたのは、長く暗い静寂であった。
Ⅳ.流年説
片眼鏡の男に、僅かな温情を掛けられたわたくしが、再び目を覚ましたのは見知らぬ部屋の布団の上だった。
(ここ、は……?)
そして、体内の霊力が安定していることがわかった。わたくしは死なずに済んだのだ、ということを認識する。
まだ完全には回復していないが、傷ついた肉体は己の霊力で快復できそうだった。
わたくしは柔らかい布団の上に寝かされていた。ここは病院ではない、街の宿屋のようだ。
だが、誰かが医師を呼んで手当を頼んでくれたのだろう。とても腕の良い医者だったようで、細かな傷も綺麗に治っている。冷たい軟膏を塗られ、至るところがひんやりとしている。そして、怪我の酷い部位は、ガーゼを当てられていた。
そして、着ている服はいつも着ていた服ではなかった。片眼鏡の男と対峙した際にボロボロになった上着はどうしたのだろうか?
(誰かが着替えさせてくれたのだろうか?)
そう疑問に思うも、まるで思い当たる節がない。わたくしには、殆ど知り合いがいないのだ。死にかけたわたくしに、ここまでしてくれる相手がまるで思い当たらない。
ふと室内を見回すと、布団の横にきちんと畳まれた新しい服が置いてあった。
起き上がって着替えたいが、全身がまだ悲鳴をあげている。わたくしは強引に体を起こそうとして、堪らず咳き込んでしまった。
体に鈍い痛みが走って、額に汗を掻いているのがわかる。わたくしは呼吸を整えて、ゆっくりと体を起こす。先ほど体を起したときよりも全身に重みを感じる。
「はぁ、はぁ……」
「ん?やっと起きたか、無理に体を起こすな。まだ怪我は治ってねぇだろ」
扉を開ける音と同時に、誰かが部屋に入ってくる。
不意打ちの声に、わたくしは驚いてしまう。男の後には見知らぬ者の姿がひとつ見えた。
ふたりとも私の知らない者だった。
わたくしは警戒しつつも、この体ではどうにもならないことを理解し、真っ直ぐに彼らを見つめた。
先ほどわたくしに声を掛けた男は、大きな剣を携えていた。
武将だろうか?初めて見る者だった。
男はすぐ近くの椅子に、あぐらを掻いて座った。
見た目はとても高貴に見えるが、随分と豪胆な男だな、と思った。
「貴方は……?」
背中の冷や汗を感じて、本能的に後ろに退いてしまう。
彼も私の驚きの表情に気づいて手を止めた。
「ああ、別に怪しい者じゃねぇ」
ククッと男は不敵な笑みを浮かべて、髪をかき上げた。
「オレの名は、ロンフォンフイ。オメェは邪教の敷地内でぶっ倒れてたんだ。その話をオレにした野郎がいてな。ま、放っておくわけにもいかねぇし。助けてやったって算段だ」
彼は大きな手を差し出してくる。
(握手を求めているのだろうか……?)
彼が差し出した手を取るのを躊躇した。
「オレは……かつては軍を引いて戦ってた武将だったが、今は隠居の身だ。オメェはどこの誰だ?助けてやったんだ、それっくらい教えてくれてもバチは当たんねえだろ?」
この状況で、彼が私を助けたという話を疑う理由はない。仕方なく私は口を開いた。
「……わたくしの名は雄黄酒と申します。わたくしは食霊です。御侍様に召喚され、言われるまま、丸薬を作っていました」
そこまで話して、わたくしは愕然としてしまう。
わたくしは、御侍様との絆がどこにも感じられないことに気づいてしまった。
(もう、御侍様は……いない)
いや、生存についてはまだわからない。ただ、今はあれほど感じていた絆を、まるで感じない――
わたくしは、放り出された子どものように、自分で歩く術すら持っていなかった。
(御侍様に頼まれなければ、わたくしはもう何をすべきかすらわからない……!)
――わたくしにはもう、生きている目的すらないのだ。
男の問いで、その事実に気づいてしまった。それは少なからず、わたくしを無力にさせるに十分な事実だった。
「助けてくださりありがとうございます。ただ、わたくしにはもう何もわからないのです……せっかく助けてくださったのに、もうわたくしは生きている意味のない、抜け殻となってしまいました」
わたくしの言葉に男が息を呑んだ。だがわたくしは俯くしかできない。
考えることすら、己でできないほどに、自分が御侍様に依存していた。そう思うと、もう呼吸すらままならず、涙を流すしかできなかった。
Ⅴ.雄黄酒
雄黄酒は邪教のメンバーである男に召喚された。
御侍である男は、名前すら名乗らずに、雄黄酒に丸薬作りをすることになった。
御侍の願い通り、雄黄酒は優秀な研究者だった。どんな薬であっても、彼は御侍の期待に見合う薬を調合した。
雄黄酒は、御侍が彼の存在の全ての意味だとずっと思っていた。
だから御侍のどんな要望も受け入れ、どれほど冷たく当たられても、御侍のすべての願いを叶えた。
そうして御侍が喜んでくれることこそ、自分の存在理由だと思ったからだ。
ある夜、丹房に北京ダックが現れた。
彼は薄暗い部屋で月光に照らされ、柔らかな笑みを浮かべて雄黄酒へと語り掛ける。
雄黄酒はかつてとある集まりで彼を見かけたことがあった。しかし、御侍は北京ダックが食霊であることを教えてはくれなかった。
食霊であることを言う必要を感じなかったか、もしくはそのこと自体を気にかけていなかったのかもしれない。
御侍と離れ離れになってしまった今となっては、その真意は確認できない。
ともあれ、同じ食霊であった北京ダックに雄黄酒は興味を抱いた。
彼は、不意に雄黄酒の丹房に現れた。柔らかな笑みを浮かべた彼も、御侍を攻撃していた表情が冷ややかだった彼も、どちらも彼の心に残っている。
そして、御侍を守るべく、雄黄酒は北京ダックと対峙することになった。
北京ダックは雄黄酒が御侍に利用されているのを知らないと思っていたようだ。
だが、雄黄酒はそのことを知っていた。
ただ、彼はその事実を認めたくなかった。
同時に、仮に利用されていたところで、彼の御侍に対する気持ちは変わらない。何があっても、御侍を守ろうとしただろう。
そんな雄黄酒を見捨て、御侍はひとりで逃げてしまった。そんな彼に北京ダックは同情し、救いの手を差し伸べた。
***
ひとり見知らぬ部屋で目を覚ました雄黄酒は、これまでのことを少しずつ思い出す。
御侍様との絆はもう感じ取れない。
これは、自分と御侍様の関係が切れてしまったのか、はたまたもう御侍様がこの世にいないのか、雄黄酒には判断がつかない。
しかし、仮に御侍様が生きていたところでもう彼の元には戻れないだろう。
前と同じように、丸薬を作り続けることができるのか――雄黄酒にはわからない。
そして、もうひとつ。
雄黄酒には、わからないことがあった。
それは、同じ部屋にいる男のことだ。
彼の名前は、ロンフォンフイ。
「オメェは、これから何をしたいんだ?」
雄黄酒は彼の質問に、茫然としてしまう。
俯いて、自分の手を見つめると、ふと過去に戻ったような気がした。
それは、御侍様から質問された日のこと。
――私のために、何ができますか?
あの日も、雄黄酒は答えるべき言葉を持っていなかった。
そんな彼に御侍様は丸薬を作るように命じたのだ。
「わたくしは……丸薬を作ることができます。わたくしは他のことはできません」
「違ぇよ、んなこたぁ聞いてねぇ。オレはな『お前が何をしたいのか』を聞いたんだ」
「……わたくしが、したいこと」
ロンフォンフイのじれったそうな言葉に、雄黄酒は堪らず、袖の下の手を思わず握りしめた。
暫く黙って雄黄酒の様子を見守っていたロンフォンフイは、耐え切れなくなった様子で荒々しく雄黄酒の頭をぐしゃぐしゃと揉みしだいた。
「な、何をするんですか!」
「オメェはまだ病み上がりだ。それは理解した上で話す」
そう前置きをして、ロンフォンフイは息を吸い、真っ直ぐに雄黄酒を見つめた。
「オメェはずっと丹薬――オメェは丸薬って言ってるみてぇだが、とにかく御侍に言われるまま薬を作っていたらしいな。あの薬がなんなのか、わかってたのか?」
「なんなのか……?」
「オメェの作った薬でどんな結果を招いたか知ってるのかって聞いてる」
雄黄酒は黙ってしまう。
あの薬は……御侍様に言われるまま作って渡してそれっきり。どのように使われていたかは知らない。
ただ使っていた材料から、良い薬ではないだろうとは思っていた。
「なるほど、お前はあくまで製作のみ。それ以降のことは知らねぇと言い張るんだな」
はぁ、と眉を顰めてロンフォンフイは頭を振った。
「では貴方は知っているのですか?あの薬が何に使われ、どのような結果になったのかを……」
ロンフォンフイは雄黄酒を連れて、かつて邪教によって破壊された村を見に行った。
雄黄酒はその様子を見て、唖然として口を閉ざした。思考停止した結果がどうなったのかを知って、打ちのめされているようだ。
そんな雄黄酒を見て、ロンフォンフイは積極的に責める気にはならなかった。
食霊という存在は、御侍によってどうにでもされてしまう。
悪事の自覚があろうがなかろうが、命令されたら逆らえないのが食霊だ。
そこで北京ダックの話を思い出す。
(北京ダックの話を信じるしかねぇか……)
そのときのことを思い出して、ロンフォンフイは顔を顰めた。
「そなたが望むなら、彼を救ってあげてほしい。彼は邪教の犯罪者たちと違います。そなたも同じ食霊だからわかるでしょう?吾たちにとって、御侍がどれほど特殊な存在なのか、理解できるはずです」
「だったらオメェが助けりゃいいだろ?なんで俺に頼む?」
「……吾の御侍も故郷のためにその命を落としました。だから憐れに思っても、手を差し伸べることまではできません」
「奴が邪教の一助を担っていたのは、本心からでないと、信じろっていうのか?」
「彼は悲しい食霊です」
「なんだって?」
「彼を助けたら分かりますよ。その上でどうするか決めたらよいかと」
北京ダックはもうこの話題をしたくないようで、それ以上語らない。そして、魚香肉糸に支えられ、彼はこの場から去っていった。
そしてロンフォンフイは地面に倒れている雄黄酒を見つけた。こいつのせいで沢山の命が消えていったと思うと怒りが溢れてきた。
だが、同時に北京ダックの言葉が頭をよぎる。倒すのはいつでもできるだろう。この引っ掛かりを明らかにしてからでも遅くない。
そう思い、足元の砂利を蹴った。これで一旦の怒りを留め、歯を食いしばって雄黄酒に手を差し伸べた。
壊れた村の外に立って、青ざめた雄黄酒を見ながら、彼の襟を掴んだ。
「目を逸らすな。オメェが作った薬が生んだ悲劇だ」
「も……申し訳、ございません……!」
雄黄酒はその場に崩れ落ちた。
「けれどもうすべて起こってしまったこと。誰かを不幸にする意志はなかった。わたくしは、ただ御侍様の言う通りにしていただけ。その御侍様も今はもういない――わたくしはどうやってこの罪を償えばよいのか、まるでわかりません……!」
「……オメェは」
そこで北京ダックの言っていたことがようやくわかった気がした。
「……償え。生きてるんだからな」
「償う、とはどのように?」
「それはオメェが考えろ。そのために、生きろ」
雄黄酒は何も答えられない。がっくりと項垂れて、そのままその場に崩れ落ちた。
「あー、もういい!わかった!」
「ついて来い。それで、オメェができることを探すんだ。俺も一緒に探してやるから。わかったな?」
雄黄酒は絶望の中で告げられたロンフォンフイの言葉に、まるで見えなかった道に一筋の光を見つけられた気がした。
彼のことはまだよくわからない。だが、差し伸べられた手を取ることにした。
彼と共にあれば、これからの生きる道を見つけられるかもしれない……そう思えたからだ。
「……ありがとうございます、貴方の親切に感謝します。私は必ずや貴方に報いることをここに誓います……!」
◀ エピソードまとめへ戻る
◀ 雄黄酒へ戻る
Discord
御侍様同士で交流しましょう。管理人代理が管理するコミュニティサーバーです
参加する-
-

-
ななしの投稿者
175年まえ ID:m5k84jlsⅤ 雄黄酒⑰
-
-
-

-
ななしの投稿者
165年まえ ID:m5k84jlsⅤ 雄黄酒⑯
-
-
-

-
ななしの投稿者
155年まえ ID:m5k84jlsⅤ 雄黄酒⑮
-
-
-

-
ななしの投稿者
145年まえ ID:m5k84jlsⅤ 雄黄酒⑭
-
-
-

-
ななしの投稿者
135年まえ ID:m5k84jlsⅤ 雄黄酒⑬
-
-
-

-
ななしの投稿者
125年まえ ID:m5k84jlsⅤ 雄黄酒⑫
-
-
-

-
ななしの投稿者
115年まえ ID:m5k84jlsⅤ 雄黄酒⑪
-
-
-

-
ななしの投稿者
105年まえ ID:m5k84jlsⅤ 雄黄酒⑩
-
-
-

-
ななしの投稿者
95年まえ ID:m5k84jlsⅤ 雄黄酒⑨
-
-
-

-
ななしの投稿者
85年まえ ID:m5k84jlsⅤ 雄黄酒⑧
-