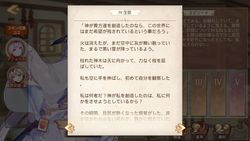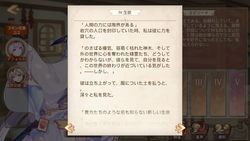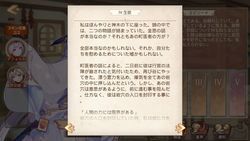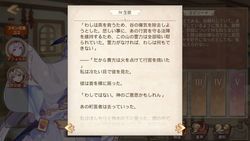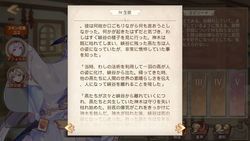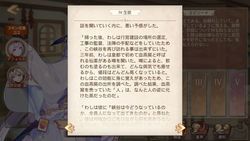冰糖燕窩・エピソード
◀ エピソードまとめへ戻る
◀ 冰糖燕窩へ戻る
冰糖燕窩のエピソード
夢廻谷の谷主である。俗離れしていて、まるで周りを見下しているように見える。実際は箱入り娘で、世間について何も知らないだけ。火が嫌い。人間は欲の塊なので少し拒否している。誰かを好きになったとしても、気持ちをうまく伝えられない。
Ⅰ.情欲
山に住んでいると、時間の移り変わりを感じられない。冬が終わりを迎えている事はわかっているけれど、今年が何年かはもうわからない。
私はしばし山の行宮から離れ、賑やかな都に来ていた。町に灯篭が吊るされているのを見て、やっと今は年の瀬なんだと気付いた。
帰路を急ぐ通行人は、私の横を通過する時、いつも羨ましい目で私を見る。
彼らが何を羨んでいるかは分かっている。
私の容姿、衣服、装飾など外見に過ぎない。
私の名は冰糖燕窩。人間の目を通して、彼らの欲望が見える食霊。
人間は知らない……欲望とは形あるもの。
例えば私の御侍。彼女は皇帝によって山奥に匿われている麗人である。身分などなく、毎日宮廷からの伝書鳩を待っているだけ。
彼女はいつも窓に寄り掛かって座る。彼女の目からは薄紅の欲望が零れていた。
例えば御侍を奉仕する侍女。彼女は失敗すると、土下座して命乞いをしながら涙を流す。彼女の欲望は、その涙と共に燃えているどす黒い殺意。
だから、人が多い場所は嫌いだ。
人が多い場所は、人から流れる欲望も多く、そして複雑だ。欲望の火は天地の姿をも変え、爽やかな面影すらなくさせる。その火から出る俗な煙は、私を蝕む。
しかし、今日はその嫌いな場所に行かざるを得ない。
御侍は身体が弱い。毎日薬膳を食べているが、一向に良くならない。
近頃、突然嚥下障害になり、更に腹痛が酷く、体調はますます悪くなった。
宮廷から派遣された医者は帰省したため、私は王宮に火急の手紙を送った。しかし、返事は来なかった。
御侍の体調が悪くなっていくのを見て、嫌だが仕方なく下山して、医者を連れてくる事を決めた。
医館に入ったが、人気はなく、薬局の番頭らしき人しかいなかった。
算盤を動かしていた番頭は、私が入ってくるのを見て、顔を上げた。
「いらっしゃいませ、お嬢様は何をお求めで?新しく入荷した朝鮮人参はいかがですか?健康に良い上物ですので、贈答用にしても、自分で食べるのもお勧めですよ」
「問診に伺いました」
「おお!どうなさいました?私は医者です」
「病気を患っているのは私ではない、本人は出歩けないため、先生に往診をお願い出来ないでしょうか?」
伺った目的を伝えたら、あの番頭みたいな人は興味を無くした顔で算盤を続けた。
「お嬢ちゃん、年の瀬に往診するのは縁起が良くないよ」
「彼女の病状はかなり深刻です。何卒助けて頂けないでしょうか?」
番頭は顔を上げて私を見た、目の奥に青い打算の火が燃え上がった。
「うーん、行ってやっても良いが、往診料は高くつくなぁ。今日、営業している医館はうちぐらいしかないからねぇ」
私は真珠一袋を取り出して、彼の前に置いた。
「これなら足りますか?」
彼の目の火は緑色になりさらに強く燃えた、まるで薄気味悪い笑い鬼のようだった。
「これはこれは、少々お待ちください。今すぐ医療道具を用意してきます」
私は頷き、外で待つ事にした。青空を見て、せめて目を休ませなければ。
御侍は山奥に建つ行宮に住んでいる。帰る時は医者と一緒のため、行きより少し時間が掛かった。それでも、医者は私の速さに驚き、行宮に辿り着いた頃には、医者は我慢できず吐いてしまった。
森から行宮までの道には、皇帝が手配した方陣があるため、関係者以外は決して道を見つけられない。王宮から遠く離れたこんな山奥に行宮があるなど、普通の人は絶対に想像できないだろう。
医者もやはりここが誰の土地かわからずにいた。妖怪の巣窟に連れこまれたと勘違いしたのか、覚束ない足取りで、ひたすら念仏を唱えていた。あの真珠が彼に勇気を与えたからか、震えながらも思い切って御侍の寝殿に踏み入った。
御侍は床に伏し、昏睡していた。病が顔に出ていたが、それでも美しい容姿に変わりない。私は赤い紐を引いて、御侍の腕に結び、もう一方を医者に渡した。
医者は本当に往診をお願いされていた事を確認し、やっと落ち着いた。赤い糸に触れて真剣に脈をとる姿から、ようやく医者らしさを伺えた。
しばらくして、彼は疑いの眼差しで御侍を見て、また私を見た。
「失礼を承知で伺いますが。この方、以前に流産した事はございますか?」
私は呆然とした。
皇帝は長い間いらっしゃっていない。
医者は私が何も言わないのを見て、すぐ「いいえ、何もありません。」と言い、処方箋を出してきた。
「この方は血虚症でございます。体にたくさんの毒素が溜まっているため、普通の薬草では一時の苦しみを緩和する事しか出来ない。早く毒を排出しなければ恐らく……」
「どんな薬なら治せますか?」
「血燕窩でしたら、毒素を完全に排出できるかもしれません」
「血燕窩?」
「血燕窩は血燕の巣であり、貴重な薬です。数年前市場に出回った際は、高値で取引されていたが、すぐに売れ切りました。血燕は中々見つからないので、野外で見つかるかどうか…」
「見つかるかどうかは、試してみないと…」
「では幸運がありますように。」
そう言って医者は去ろうとした。
「今回はありがとうございました。山の入口まで案内します」
「いいえいいえ、結構です。自分で歩けます、何日か歩いて体を鍛えようと思います」
彼は数歩歩き、何かを思い出したかのように振り返り言った。
「この辺に金地谷という場所があるはずです。伝説によると血燕の生息地ですから、あそこに行って運試しをしてみてください」
「金地谷ですか…?」
Ⅱ.利欲
医者は私に言った、血燕の嘴は血の様に赤い。断崖絶壁にしか燕窩——巣を作らないため、見つけにくいと。しかし、彼が言うには、この辺りの金地谷と呼ばれる場所は血燕の生息地らしい。
御侍の病気はもう一刻の猶予も許されない状態だった。その晩、侍女に必ず時間通りに薬を準備するように言いつけた後、金地谷向かった。そして三日三晩を掛け、ようやく高い断崖でそれを見つける事が出来た。
しかし見つけた時、何故か攻撃を受けた。
「妖怪!どけ!」
投げられた何かを無意識に掴んで見ると、小さな石だった。
中空にふわりと浮かんでいた私は、石の持ち主を探したーー見つけたのは、草履を履いている少女。
彼女は断崖の下、出っ張った岩に座っていた。片足を怪我しているようだった。彼女は憤りの目で私をじろじろ見ているが、私は何も感じ取る事が出来ずにいた。
彼女のような目を、私は見た事がない。
綺麗で、純粋で、欲望など浮かんでいない。
人間の目……欲望に眩んでいない目は、まさかこんなにも透き通っているとは。
私は思わず彼女に近づき、もっと見たくなってしまった。
「何?近づくな!何がしたいんだ?!」
私は彼女の叫びを無視した。彼女の目から金色の光ーー『生きたい』という欲望が出るまでは。
近づくのをやめた私は彼女に話しかけた。
「私は食霊です」
「食霊?妖怪の一種か?」
「そうかもしれません。しかし、私に悪意はありません」
「燕窩を取ろうとしていたのに、悪人じゃないって言うのか?」
「必要だったからです。お金のためではなく、病気を患っている主人が、これでしか治らないと言われたので」
彼女は一瞬固まって「……本当か?」と。
「はい」
彼女は俯いて、悩んでいる様子を見せた。しばらくして、決心したかのように「じゃあ、あげるよ」と一言。
「ありがとうございます」
私は頷き、彼女に手を差し伸べた。
彼女は驚いて、後ずさる。
「何よ?もう燕窩はあげたでしょう?まだ行かないの?」
「貴方は怪我をしていますね、一緒に山を降りましょうか」
彼女はまた一瞬固まり、その後青白い顔が少しだけ赤くなった。
少し考え込んで、服で手を拭ってから、私に伸ばしてくれた。
行宮で彼女に傷薬を塗った後、ようやく何があったのかを教えてくれた。
彼女は「金思」、金地村に住んでいるという。
村は断崖絶壁という天然の障壁に囲まれ、冬は暖かく、夏は涼しい。村人たちは断崖から出入りするため、全員が崖登りが得意だと。
元々、農業や紡糸で生計を立てていた村だった。血燕窩は村で大して珍しいものではなく、誰の家の軒先にもあったという。そして血燕は毎年村で冬を過ごしたと。
三年前、ある皇城の官吏が村を経由した際、管理が崖から転落して酷い怪我を負った。村人は彼を救うため、血燕窩を煮込んで彼に食べさせた。本来なら完治するのに数ヶ月は掛かるはずの怪我が、奇跡的に半月で治ったという。
官吏は村人にどんな神薬を使ったのかと尋ねた。村人は珍しい物ではない、どこにもある普通の燕窩だと答えた。
回復した官吏は村を離れたが、しばらくして、召使を連れて戻ってきた。世話になった村人に恩返しするため、血燕窩を買い取りたいと言い出した。村人は珍しい物ではないと思っていたが、相手が食い下がらないため、普通の傷薬の価格で売ってしまった。
無価値だと思っていた燕窩でお金を儲けて、村人たちが喜んだのも束の間。
街から帰ってきた村人が「血燕窩は高値で取引されていた」事を村中に知らせた。
「気付いたら村人全員農業や紡糸をやめて、朝から晩まで、一日中崖で燕窩を探すようになったんだ。見つけては街に行って売るのを繰り返した。何人かで協力して見つけた物は、分前問題で喧嘩する人もいたよ。何十年も仲良く暮らしていたお隣さんが、血燕窩のせいでお互いを目の敵として見るようにも……」
金思は続きを言う。
「低めの谷にあった燕窩は段々と無くなって、それから村人たちは高いところで探すようになって……」
いくら崖登りが得意と言えど、彼らは普通の人間に過ぎない。高く登れば事故も起こる。
「最初は怪我程度で済んだけど、最終的に何人か落ちて死んじゃった。その時になって、やっとみんなは危険を冒してまでこんな事をするのは、割りに合わないと気付いたんだ。多くの村人たちは燕窩を探すのをやめて、普通の暮らしに戻ろうとしたよ」
「だけど一年に渡って農業をしなかったせいで、土地はもう荒れ果てちまった。しかも、今まで起きた事がない虫害も起きた。何の役にも立たないと思っていた燕たちが、実はこの虫の天敵だったんだとよ。燕はこの土地で冬を過ごす時、ついでに土に埋もれていた虫の卵を食べ尽くしてたんだ。燕が来なくなったから、土地も荒れきってしまったんだ」
「農業が出来なくても、人は生きなきゃいけねえ。燕窩を売ってお金を得た人たちは村から離れ、都会に行った。残されたのは燕窩を手に入らなかった数軒だけ。ある人は燕が戻ってくるのを待って、ある人は諦めずに崖を登って、ここを離れるために燕窩を探してたよ」
金思はその残された村人の一人。数日前、偶然血燕窩を見つけたという。燕窩の中には怪我をした燕が一羽いたが、彼女は燕を連れて帰るのが怖かった——大人たちが必ず燕窩の場所を問いただして、この残された一つの燕窩も取っていっちゃうと思ったため。
金思は毎日遊びに行くふりをして、こっそり燕に餌を与えに行った。半月後のある日、燕の姿が見つからなくなった。彼女は慌てていたため、したの大きな岩に落ちて怪我をした。そして、燕窩を探しに来た私と出会ったのだ。
「……そういう事だよ」
私は彼女が嘘をついているか確認するため、彼女の目を見つめた。それは相変わらず澄んでいた。
「半月の間、足を怪我してまで燕窩を守ったのに。最終的に、私に採られてしまって、本当に宜しいのですか?」
金思は手を振った。
「あなたは人を救うためだから。人助けは良い事だ」
「しかし、燕が戻ってきても、帰る家がなくなるのではないでしょうか?」
「大丈夫、燕が帰ってこない事は分かっていた」
「どうしてですか?」
「冬が来たら、燕たちはもっと暖かいところに行く。治ったら離れると思ってたよ。ただ、金地村がなくなったら、どこに飛んでいくかはわからない」
「他の燕と一緒に、南の方へ行ったのかもしれませんん。来年の春にはまた会えるでしょう」
「南?行ったことないや、暖かい場所だといいな」
金思は目に希望の光を浮かべながら続ける。
「大丈夫。良い場所なら、会えなくなっても、きっと大丈夫だよ」
Ⅲ.殺欲
「この世に永遠なんて存在しない、共に過ごしている時に楽しければ十分だ」
御侍は血燕窩を飲みながら言った。
この血燕窩は確かに仙薬だった。御侍がそれを飲んだ後、体調は徐々に回復していった。
当初宮廷に送った手紙の返事も届いた。宮廷医はたくさんの薬を持ってやってきたが、御侍に色々な診察を行った結果、町から呼んできた医者と同じ結論を出した。
虚血症というのは、主に堕胎したい妊婦が薬の用量を間違えた時になるものだという。宮廷医は額に大量の汗を浮かべながらも、御侍の病状を如実に皇帝に報告した。
皇帝は激怒して、徹底的にこの件を調査するよう命じた。数日後、御侍付きの侍女の部屋から使った痕跡があるサフラン水を見つけた。彼女は御侍からの扱いに不満を持っていたため、恨んでいた。毎日少しずつ食事に混ぜ、知らず知らずの内に彼女を殺そうとしたのだ。
侍女はすぐに殴り殺され、死体も谷に捨てられた。
皇帝は御侍を見舞うために行宮に足を運び、一晩泊まったが、翌朝忙しなく帰っていった。
「妾を慰めているのか?」
御侍が私に聞いてきた。
「いいえ。ただご自分で自分を許してあげなければ、体に悪いと思っただけです」
御侍が笑った。
「どこで聞いた話だ?」
「麓の村に住んでいる女の子です」
「いくつの子だ?」
「十四歳ぐらいです」
「まだ子どもではないか」
「御侍は自分の命であのお方の関心を引こうとしているではないですか。あの子と同じ、子どものような行為ではありませんか?」
「燕窩、妾のことを説教するな」
御侍は器を置いた。
「お前にはわからない」
私にはわからないものなのだろうか?
御侍の目に常に灯っている薄紅の炎を見ていると、金思の目が恋しくなった。
彼女は怪我が治ってすぐ、一縷の未練もなく行宮から出ていった。
別れの日、私は行宮前の陣法の解き方を彼女に教えてあげた。
「どうしてこれを教えてくれるの?」
「ただ、教えたかっただけです」
彼女はしばらく私をじろじろ見てから笑った。
「ねえ、もしかして私を家に帰らせたくないの?」
私は何も言わず、体を傾けて彼女の目にキスをした。
彼女の睫毛は少し震え、まるで二羽の飛び立とうとしている燕のようだった。
「早く帰りなさい、家族が心配しているでしょう」
彼女は再び目を開いた。
「また遊びに来るよ」
「それは良い、いついらっしゃいますか?」
彼女は空を見上げて、手を伸ばし、風に吹き飛ばされた松の葉を掴んだ。
「冬は寒過ぎるから……来年の春、燕たちが帰ってきた頃にまた」
御侍が体を起こして、 鏡台の前に座った。
「燕窩、来なさい」
私は御侍の隣に来て、簪を外して髪を解いてあげた。
彼女の髪は簪に絡まっているため、丁寧に外していった。
元は侍女の仕事だが、あの事件の後全て私の仕事となった。
あまり上手ではないため、少しずつ梳かしていくしかなかった。
御侍は自分の髪をとても大切にしていた。 彼女はいつも「髪の一本一本は恋の糸でもあるから、決して蔑ろにしてはいけない」 と言っていた。
侍女が間違えて彼女の髪を切ってしまった時、彼女はいつも容赦なく侍女の顔をはたいた。
御侍は鏡の中の私を見ながら、何かを考えている様子だった。
彼女は一つため息をついた。
「妾がやる」
彼女は手を伸ばして、頑固に絡まる簪を引っ張り、化粧箱の中に投げ入れた。簪の上には切れた髪の毛が数本揺れていた。
「妾は眠い、燕窩も下がって良いぞ」
彼女は立ち上がって寝台に向かった。
私は彼女が布団に入ったのを見届け、部屋のロウソクを消し、静かに部屋を出た。
思いがけない災難は深夜起きた。
最初は強風の音が聞こえた。次第に、高温の熱気に吹かれ起こされた。
辺りを見渡すと火の海が広がっていた。逃げ惑う人の悲鳴しか聞こえない。
「水、早く水を!」
「出られない!行宮は何かに囲まれてる!」
私は霊力で扉をこじ開け、外に飛び出た。
行宮は火の壁に囲まれ、 炎は空まで迫り上がっていた。ここは地獄絵図と化していた。
召使い等は自分の部屋から逃げ出せてはいるが、行宮から脱出する道は見つけられないでいた。
彼らの目に映る金色の欲望の炎は既に目の縁を乗り越え、その身体を燃やしていた。 既に本物の炎と見分けがつかない。 燃えている人はまるで飛び散る火花のよう、どこに行くと死に、どこに行けば生きられるか分からずに逃げていた。
私は頭が痛くなって、 その中の一人を止めた。
「御侍はどこ?」
「どけ!邪魔するな!」
彼が私を振り払った瞬間、懐からたくさんの宝石が落ちてきた。その中の一つの簪が私の足元に落ちた、上には髪が絡まっていて――血痕があった。
私は彼を掴んで火の海に捨てた後、なりふり構わず寝殿に飛んだ。
霊力で寝殿の扉を開けて中に入っていった。
濃い煙が立ちこめる中、彼女を見つけた。
彼女は鏡台の前に伏せていた。背中には焼き焦げたかのような黒い血痕が、純白の絹の衣に残されていた。目を疑うような光景だった。
「御侍様!」
私は彼女の体を起こし、止血を試みた。
「燕窩、もう良い」
彼女は既に虫の息だった。力なく私に寄りかかり、話し始めた。
「お前は……もう自由になる……なぁ、教えてくれ……契約が消えるのは……どんな気分なのだ?」
どうして今そんな事を聞くんですか?
「教えてくれ」
彼女は私の治療を躱して、執拗に続けた。
苛立った私は、彼女の執着を無視しようとしたが、彼女の目から桃色の欲望の炎が消えていた事に気付いた。
それだけではない、
金色の生きる欲望すら見えない。
「御侍様……」
「教えてくれ。痛いか?それとも……嬉しい?」
「……痛くありません、ただ……悲しいです」
一粒の涙が彼女の顔に落ちていた。 知らず知らずのうち、私は泣いてしまっていたのだ。
「悲しむな……泣かないでくれ……永遠なんて存在しないのだから……」
御侍は私を見ているのに、まるで私を通して誰か別の人を見ているみたいだった。
彼女の目はとても寂しく、そして満足していたようだった。
この世に永遠なんて存在しない。
王歴六十八年、私が召喚されてから七年目、
御侍は冬の山火事で亡くなった。
召使いの裏切りのせいで、皇帝から賜った簪のせいで、彼女自身が望んだ愛のせいで。
Ⅳ.生欲
あの山火事は七日七晩も続いた。皇帝の法陣は三日目までしか維持出来ず、崩れた。
山奥に隠された豪華な行宮は人前に姿を現したが、またすぐ劫火に吞み込まれてしまった。
法陣が崩された瞬間、私は霊力で道を拓いて、生き残った召使いを連れて脱出した。
彼らは自らの運命に従って四方に散った。
私も立ち止まらず、金地谷に向かった。
金思が教えてくれた道筋に沿って下に向かって飛び続け、谷底に辿り着いた。しかし彼女が言った村は見つけられなかった。
地面に降りて、辺りを注意深く探し、ようやく一つの洞窟を見つけた。
中を探ろうとした時、突然背後から声が届いた。聞き覚えのある声だった。
「お嬢さん、ここから先は進まない方が良い」
振り向くと、そこにいたのはなんとあの町医者だった。
彼は私を見てもあまり驚かなかった。
「この先は瘴気が立ちこめている。特にお嬢さんのような霊物にとっては、避けられない害がある。前に進まない方が良い」
「貴方はどうしてここにいるのです?どうして私の正体を知っているのですか?」
彼は笑った。
「お嬢さんの正体をきちんと知っている訳ではない。ただ、今の皇帝の傍に仕える强者は伝聞によると、一日に千里進む事が出来、万物を支配出来て、空を飛ぶ事も出来る上に、不老不死だと。お嬢さんはあの強者の同族であり、同じく神樣の創造物であると」
私は何も答えなかった。あの進んではいけない洞窟を見た。
「ここは一体どんな場所なのですか?私はとある村を探しに来ました。洞窟を通れば辿り着けるか、ご存知ですか?」
彼は冗談を聞いたみたいに言った。
「村なんて最初から存在していない」
私は疑いの気持ちで胸がいっぱいになっていた。彼は手招いて「ついてきな」と言ってきた。
私は彼に続き、彼が来た方へ向かった。川を越えて、その上流に一本の巨大な木があった。
その木には葉はなかった、枯れた枝だけが空に向かって延び、何かを掴み取ろうとしているようだった。
「十年前、皇帝に命じられたわしはこの山脈に来て土地を探した。皇帝はある人を隠すため、隠れ行宫を建造しようとしていたのだ。わしがこの峡谷に差し掛かった時、落馬してしまいこの産から落ちてしまった。燕たちが集まってわしの命を助けた」
私は疑わしい目で彼を見た。彼は巨木に近づき、大事そうに巨木の幹を撫でた。目には淡い青の火種が見えた——彼は過去に想いを馳せていた。
「あの燕たちは代々この峡谷に住んでいた。この神木を住処とし、全員霊力を持っていた。彼らは精一杯わしを助けたが、崖から落ちた事で負った傷は深かった。それで彼らは自分らの唾液でわしの治療を行った。しばらくすると、わしの怪我は治っていた」
「燕たちに感謝するため、わしは彼らに欲しい物はあるかと尋ねた。彼らはないと返事した。当時のわしは、若気の至りで自分は何でも出来ると思っていた。その上、彼らのような精霊みたいな種族は、全員人の姿になりたいものだと思い込んでいた。だから、燕たちに人の姿になって、外の世界を見に行かないかと提案した」
「賀成する燕もいたが、拒否した燕もいた。それでわしは人の姿になれる法術を峡谷に残って燕たちと別れた。しかし、これが恩を仇で返す始まりであるとは思いもしなかった」
話を聞いていく内に、悪い予感がした。
「帰った後、わしは行宮建設の場所の選定、工事の監督、法陣の手配などをしていたため、この峡谷を再び訪れる事は出来ずにいた。三年前、わしは皇都で初めて血燕窩と呼ばれる仙薬があると聞いた。噂によると、飲むのも塗るのも出来て、どんな病気でも癒せるから、値段はどんどん高くなっていると。わしはこの効能に身に覚えがあったため、この血燕窩の出所を調ベた。調ベた結果、血燕窩を売っていた『人』は、なんと人の姿に化けた燕だったのだ」
「わしは彼に『峡谷は今どうなっているのか、全員人になって出てきたのか』と尋ねた。彼は何故か口ごもりながら何も言おうとしなかった。何かが起きたはずだと気づき、わしはすぐ峡谷の様子を見に行った。神木は既に枯れてしまい、峡谷に残った燕たちは人の姿になっていたが、非常に憔悴していた事を知った」
「当時、わしの法術を利用して一羽の燕が人の姿に化け、峡谷から出た。帰ってきた時、他の燕たちに人間の世界の素晴らしさを伝え、人になって峡谷を離れることを唆した」
「燕たちが次々と峡谷から離れていくにつれ、燕たちと共生していた神木は守りを失い枯れ始めた。谷底の瘴気がこれをきっかけに神木を蝕んだ。神木が枯れた後、峡谷は死の谷になってしまった。残った燕たちは生きるため、神木と峡谷から離れるしかなかった。自分らの巣を高い場所に移動させていった」
「それからまもなく、神木が枯れてから最初の冬がやってきた。人間の世界の冬を経験した事がなかった燕たちは、その時やっとこの暖かい峡谷の事を思い出した。でもこの峡谷は既に帰る事の出来ない場所になっていた」
「一部の燕は冬の寒さには敵わず、死んでしまった」
「一部は町で生き残った。二年目、世間を知らない彼らは燕窩を売る事でか生活できなかった。すぐに人間ではない事実が暴かれ、町にいた燕たちは貴族に捕まり、血を供給するだけのペットと成り下がった」
「人間の世界に行けない、谷にも帰られない。今、わしも彼らの居場所が分からなくなっていた。あの日、お嬢さんに血燕を探させたのは、まだここに彼らがいるかどうかを知りたかったからだ。お嬢さん、見つけられたか?」
ここまで話を聞いて、まず思い出したのは金思の目、そして御侍の最期の空っぽな目だった。色んな感情が湧き出そうと、喉まで血がのぼってきた感覚がした。
「わしは燕を救うため、谷の瘴気を除去しようとした。悲しい事に、あの行宮を守る法陣を維持するため、この山の霊力は全部吸い取られていた。霊力がなければ、わしは何もできない」
——「だから貴方は火を点けて行宮を焼いた」
私は冷たい目で彼を見た。
彼は首を横に振った。
「わしではない。神のご意思かもしれん」
あの町医者は去っていった。
私はぼんやりと神木の下に座った。頭の中では、二つの物語が絡まっていた。金思の話が本当なのか?それともあの町医者の方が?
全部本当なのかもしれない。それか、自分たちを慰めるためについた嘘かもしれない。
町医者の話によると、二日前に彼は行宮の法陣が崩されたと気付いたため、再び谷にやってきた。漂う霊力を込め、瘴気を全てあの岩穴の中に押し込んだという。しかし、あの岩穴は意思があるように、前に進む事を阻んだ。仕方なく、彼は岩穴の入口を封印する事に。
「人間の力には限界がある」
岩穴の入口を封印していた時、私は彼に力を貸した。
「のさばる瘴気、容易く枯れた神木、そして外の世界に心を奪われた精霊たち、どうしてかわからないが、彼らを見て、自分を見ると、この世界の終わりが近づいている気がした。――しかし」
彼は立ち上がって、服についた土を払うと、深々と私を見た。
「貴方たちのような名も知らない新しい生命」
「神が貴方達を創造したのなら、この世界にはまだ希望が残されているという事だろう」
火は消えたが、まだ空中に灰が舞い散っていた、まるで黒い雪が降っているよう。
枯れた神木は天に向かって、力なく枝を延ばしていた。
私も空に手を伸ばし、初めて自分を観察した。
私は何者だ?神が私を創造したのは、私に何かをさせようとしているから?
その瞬間、目尻が熱くなった感覚がした、涙か炎かわからない何かが、静かに燃えていた。
Ⅴ:冰糖燕窩
遠い昔、冰糖燕窩は古代の光曜大陸で召喚された。彼女の御侍は皇帝の囲っていた妃だった。
その妃と皇帝の間には、人に言えない秘密があった。皇帝は山に法陣を作るように命じ、この妃を外界から隔て、自由に出入りすることを許さなかった。
伝聞によると、冰糖燕窩が誕生した日、侍女はいつも通り、妃に燕の巣のスープを出した。妃もいつものように「今日は陛下の手紙は届いているか?」と聞いた。
侍女は「いいえ、まだ」と返事をすると、妃は燕の巣のスープを横にあった魔動炉に撒いた。それでも怒りが収まらず侍女をはたいた。
あの時代の人間はまだ魔動炉の使い方を知らないという。この魔動炉は、皇帝がまだ妃に心を寄せていた時、暇を潰すおもちゃとして彼女に与えたものだった。誰も彼女が食霊を召喚できるとは思っていなかったが、食霊の冰糖燕窩はこの時姿を現したのだった。
冰糖燕窩が誕生して初めて見た景色は、土下座している侍女の前で器を投げ壊す妃、その目には赤い炎が燃えていた。戦々恐々と命乞いをしている侍女、その目には黒い殺意が溢れていた。
「人間の目は欲望に塗れると、こんなにも醜くなるのか」
このような印象が残ったため、彼女は人間へ好感が持てなくなっていた。
でも彼女の想像とは違い、この我儘な御侍は自分をこき使う事はなかった。逆に、勝手に行宮から離れずできる限り妃の傍にいる以外は、彼女には何も求めず、自由にさせていた。
彼女は分からなかった、御侍は皇帝の庇護下にあり、また多くの侍女が仕えていたのに、どうしてそんなに不安なのか。この謎を、御侍が亡くなっても彼女は解けなかった。
ある日、御侍は突然病にかかった。これをきっかけに冰糖燕窩の物語は進み出した。
彼女は金思という、澄んだ目を持つ女の子に出会った。それから、春にやってきて、冬に別れを告げる親友が出来た。
彼女は峡谷に残り、神木の上にツリーハウスを建てた。山の霊気を利用し、あの岩穴に追いやった人間を呑み込もうとする瘴気と戦った。
その後、彼女はここで気の合う仲間たちに出会い、本来ツリーハウスだった建物は増築を経て山荘となった。
例え神木がなくなっても、この世の誰かが新たな守護者となるものだ。
隠居生活をしていた冰糖燕窩は、山の外で起きた事を知らないのは当然だった。
伝聞によると、あの山火事の真犯人が見つかった。それは褒美をもらいたい森林官だった。彼は火をつけたが、火の勢いをコントロール出来なかったのだった。最終的に、彼の一家は全員皇帝の命によって斬首された。
皇帝の座も長くは続かなかった。山火事の二ヶ月後、皇帝に忠誠を誓っていた強者は突然謀反を起こし、その手で皇帝を殺害した。その後姿を消した。
民間の噂によると、あの強者は悪鬼で、彼の墓はあの山火事が起きた場所にあるという。皇帝に忠誠を誓っていたのは、皇帝が彼の墓を抑え、それを使って彼を脅していたからだと。山火事で皇帝に呪詛が破られたため、彼はこれをきっかけに皇帝に仕返しをしたと。
この噂にはそれなりの根拠があった。民は皆皇帝があの山で大きな工事をしていた事を知っていたのだ。そのため、しかし、最終的に完成した物を誰も見ていない。そのため、あの工事は地下で行われ、いわゆる地下宮殿を作っていたという説が有力視されていた。
その強者の来歴、本当に悪鬼かどうか、最後はどこに行ってしまったのか、これらの謎は王朝の滅びとともに散っていった。
この乱世で様変わりしてしまった伝承を、冰糖燕窩は知らなかった。
ただ皇帝が殺された日、寝ていた彼女は自分の一本の血脈がとても熱くなった事を感じた。まるで彼女と同じ血液を共有する「人」が、自分の血を沸騰させているようだった。
彼女は気にせず、寝返りを打って引き続き眠りについた。
初春の日々がやってきた。静かな山では、遠い場所から届く燕の鳴き声だけが響いていた。
◀ エピソードまとめへ戻る
◀ 冰糖燕窩へ戻る
Discord
御侍様同士で交流しましょう。管理人代理が管理するコミュニティサーバーです
参加する