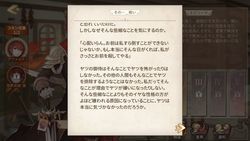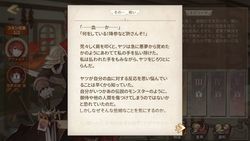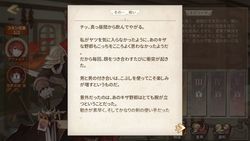ビーフステーキ・エピソード
◀ エピソードまとめへ戻る
◀ ビーフステーキへ戻る
ビーフステーキのエピソード
戦闘力がかなり強く、戦闘が生きがいだ。戦い好きの血が何事にもまっすぐ挑む性格を作り、高貴な身分が彼を孤高にさせた。言葉で解決するよりも、力づくで解決しようとする。赤ワインとは犬猿の仲で、会うたび取っ組み合いになってしまう。
Ⅰ 戦い
私が初めて赤ワインに会ったのは、特別に手入れの行き届いた花園でのことだった。
その花園にはデリケートで傷つきやすい花があふれていた。バラやコウシンバラ、それに私が名前を知らない数多くの花々。
花園の主は花のように美しい少女だった。御侍の言い方でいうと、彼のフィアンセだ。
独立心が旺盛な花園の主は、風が吹けば倒れそうな弱々しいぶりっ子に比べればずいぶんましだったが、彼女の食霊は人をイラつかせるキザな野郎だった。
男のくせに汗を掻くのが嫌いで、いつも戦いに不向きなタキシードを身に付けていた。
酒を飲むときはわざとらしくグラスを揺らしながら、おちょぼ口でテイスティングなどといいやがる。
そしてあいつは、私が着ている戦闘服を品がないと言って嫌った。
まったく面倒くさくてイヤな野郎だ。
出会った時、奴は陰になった壁に凭れ、我関せずといった風情で酒を飲んでいた。そして時折、陽光の下でいちゃついているバカップルを眺めていた。
チッ、真っ昼間から飲んでやがる。
私が奴を気に入らなかったように、あのキザな野郎もこっちを快く思わなかったようだ。
だから毎回、顔を突合わす度に衝突が起きた。
男と男の付き合いは、拳を使ってこそ楽しみが増すというものだ。
意外だったのは、あのキザ野郎はとても腕が立つということだった。
動きが素早く、そしてかなりの剣の使い手だった。
私は二本の剣を握りしめ、怒りに火が付き始めた奴に向かっていった。
どれだけ長い間、思う存分に戦っていなかっただろう。
楽しい時間はいつもすぐに過ぎ去る。私があいつを認めるのは互いにやり合っている時間だけだ。
ひと勝負終わると、やはいつも眉間に皺を寄せ、疎ましそうに体についた埃を払う。そして大抵の場合、服を着替えるため部屋の中へ戻っていく。
ちっ、男のくせに何だあのひねくれようは。
しばらくて気づいたのだが、赤ワインは日陰に一人で佇み、ぼうっとしていることがよくあった。
ある時は日光に照らされた御侍の背中を眺め、ある時は自分の手の中を見つめ、またある時は何も見ていなかった。
赤ワインがそんな素振りを見せる理由を私はずっと知らなかったのだが、ある時、恒例のように戦いを繰り広げていると、奴の長剣が私の肌を傷つけたことがあった。
それまで私を嘲っていた奴は急に眉間に皺を寄せ、長剣に付いた血の跡を呆然と見つめた。
「……血……か……」
「何をしている!降参など許さんぞ!」
荒々しく肩を叩くと、奴は急に悪夢から覚めたかのように慌てて私の手を払い除けた。
私は払われた手を揉みながら、奴をじろりと睨んだ。
奴が自分の血に対する反応に思い悩んでいることは早くから知っていた。
自分がいつかあの伝説のモンスターのように、御侍や他の人間を傷つけてしまうのではないかと恐れていたのだ。
しかしなぜそんな些細なことを気にするのか。
「心配いらん。お前は私すら倒すことができないじゃないか。もし本当にそんな日がくれば、私がさっさとお前を殺してやる」
奴の御侍はそんなことで奴を怖がったりはしなかった。そのほかの人間もそんなことで奴を排除するようなことはなかった。私だってそんなことが理由で奴が嫌いになったりしない。
そんな些細なことよりも、そのイヤな性格のほうがよほど嫌われる原因になっていることに奴は本当に気付かなかったのだろうか。
Ⅱ 誓い
私の御侍はとても間抜けな人物だ。
もしあの事件がなければ、彼と彼の愛する娘の距離が近づくことは永遠になかったに違いない。
あの時、娘が死んでしまったと勘違いした御侍は、みんなの前で思い出す度に耳まで赤くなるような告白の言葉を口にしたのだ。
その後、彼が泣きながら娘に告白したという話は街中に広がり、国王でさえ彼を冷やかすという事態となった。
彼にとって幸いだったのは、ただ恥をかいただけでなく、既に彼を好きになっていた娘が、特にロマンチックとも言えないようなその告白に心を動かされたということ。
二人が出会う時、私がそばに付き添うことはなかったが、別れを告げる際には赤ワインとともに二人のそばに控えた。
人間にとって、時間というのは残酷なものだ。
秋が過ぎ、春が来てさらに月日が流れれば、どんなに熱く燃え上がった愛も、時間によって冷まされることは避けられない。
御侍は長年の戦いで体に無数の傷が刻まれ、髪の毛は真っ白になり、まもなく人生の終わりを迎えようとしていた。
私は病床に苦しそうに眉を寄せる彼を見ていた。そして椅子を引き寄せ、腰を下ろした。
「話せよ。言いたいことがあるんだろ」
「こんなに長い年月が経ったのにお前は変わらないな。私がもうすぐ死ぬという時でさえ喜ばせるようなことは言わない。ゴホゴホ……」
「物は持ち主に似るっていうじゃないか、私たちも同じさ。何も言うことがないなら行くぞ」
「いいだろう、はっきり言おう。私はもうすぐ死ぬ。そこで最も心残りなのは彼女のことだ。分かるだろう?」
「それが遺言か?」
「こう言い換えてもいい。これからは私に代わって彼女の面倒を見てほしい。同時にあの赤ワインのやつもな」
「どうして私があいつの面倒まで見なくちゃならない?」
「なぜなら彼女の心配事は私を除けば、赤ワインのことだけだからだよ。お前と彼は仲がいいじゃないか。頼んだぞ」
「……どこをどう見て私たちの仲がいいなどと思ったんだ?分かったよ、貴方と奥さんのためだ。あのバカのことは私にまかせろ」
私は誓いを守る人間だ。しかし予想外だったのは、この誓いの一部はあまりにも早く期限を迎えたということだ。
御侍が死んだ二日後、奥さんは彼のそばに横たわり、静かにこの世を去った。
奥さんの遺体をじっと見つめる赤ワインを見て、耐えきれず後ろからヤツの頭を叩いた。
「おい、いつまで見ているつもりだ。彼女はもう死んだんだぞ。いくら見ても生き返ったりはしない」
次の瞬間、また私たちの戦いが始まった。
今回は二人とも、示し合わせたように腰の武器は使わず、拳だけを交え、胸の中の悲しみを吐き出し合った。
私は当初、戦いが終わったらこいつから別れを告げられると考えていた。
しかし奴は言いようのない微妙な表情をしていた。
まるで嫌いなものを食べているような、明らかにそうしたくないのにそうせざるを得ないというような。
しばらく向かい合った後、先に口を開いたのはやはり私だった。
「私の騎士団に入らないか。お前の剣の腕ならギリギリ合格だから」
あ、そういえば赤ワインのパンチがこれほど重いとは知らなかったな。
Ⅲ 不意打ち
聖剣騎士団はもうかなり長く存在していた、私達の御侍が居る国の歴史よりも長いかもしれない。
元の王城は既に君主を替えた。
分不相応にも食霊の力を望んでいた御侍の親族達は、逆に私たちの人間に対する美しい印象を壊し続けた。
私達はその思いが詰まっていた土地を離れることを決めた。
主が居ない食霊の周りには、いつも下心丸出しの人類が取り囲んでいる。
私と赤ワイン、決して仲がいい訳ではないが、長年の切磋琢磨を経て、既に十分に息が合うようになった。
私達二人が揃えば、いかなる困難も粉砕できるほどに。
目標のない食霊にとって時間は呪いみたいなものだが。
私にとって、時間は恵みだ。
時間が有ればあるほど、私は私のしたい事ができる、守りたい人々を守れる、駆除したいすべてを駆除できる。
時間は食霊を優遇しているから、私は年をとり体が弱くなって自分の手にある両剣を振り回し敵を切り裂けないことを心配する必要はなかった。
私と赤ワインは騎士団の呼び方に対する意見が割れているが、受ける任務に関して、彼が口を挟んでくることは稀にしかない。
老人のために屋根を修繕することから、無数の人を殺した堕神を退治することまで、あらゆる任務を請け負っている。
しかし最近、おかしな事が多発していた。
郊外で堕神を駆除するとき、よく影から矢が飛んできた。
これらの事で私は、赤ワインが悪意を持ってる何者かに狙われているんじゃないかと疑ってる。
すべての矢が、赤ワインを目掛けて飛んでくるからだ。
ジンジャーブレッドは盾で再び赤ワインを陰で狙ってきた矢を防いだ。
彼女は怒って矢が飛んできた方向を見た。
しかし赤ワインが彼女を引き止め、彼は冷たい目であの方角を見ると、相手をするつもりがないような顔をした。
「気にする必要はない、ただの虫けらだ」
「しかし――!」
「大丈夫。相手にしたら、付け上がるだけだ。放っておけ」
彼はよく配達やジンジャーブレッド、私から差出人不明な手紙をもらっていた。毎回彼は冷静にこれらの手紙を燃やした。まるでこのような細かいことは取るに足りないようで。
私は彼に相手の正体を知ってるのかと聞いたが、彼はいつも余計なおせっかいだと手を振った。
赤ワインは聖剣騎士団の重要なメンバーの一人だ、彼を狙ってる奴を放っておくわけにはいかない。
Ⅳ 真相
赤ワインを狙ってる卑怯な奴のことを調査するのは容易い。
赤ワインは受け取った手紙を隠したりしなかったから、私は簡単に元凶を突き止めた。
私は独りでかつての土地に戻った。あの薄暗くて不気味な城を見上げる。あの時と変わらない人を不安にさせる城だった。
私は剣を手に、城の門を蹴り開けた。
これはあの時連続殺人事件を犯した犯人の住処だった。
あの後荒れ果てたはずの城の門を開けた瞬間、冷たい光を帯びた矢が飛んできた。
手で鼻先を真っ直ぐ狙ってきた矢を叩き落して、私は冷たい目でこの血生臭い匂いがまだ散っていない不吉な屋敷を見た。
「誰だ、出てこい!」
隠れてるそいつが出てきた瞬間、私は彼の身に纏っている幻覚を引き起こせそうなほどに濃い血生臭い匂いを感じた。
私はこいつに会ったことがある。
あの供物を選ぶためのでたらめなダンスパーティーで。
彼の手には御侍の愛する人が抱かれていた。
私達が間に合わなかったら、奥様は恐らく次の供物になっただろう。
彼は恵まれた外見を持っている。
彼は知らん振りで石柱の後ろでぶるぶる震えていた。もし私が真相を知らなかったら、恐らく彼に惑わされていただろう。
あの王国をどよめかせた悲惨な事件は赤ワインが画策したものだと、彼は言った。
あの少女たちは赤ワインの手によって殺された。彼と彼の御侍は罪を被せられただけだと。その原因は彼が少女達の血を渇望していたと。
私は静かに目の前のこの段々興奮してきた奴を見て、思わず溜息をした。
「彼はずっとあなた達を騙していたんだ。彼があなたのそばに居るのは、ただあなたの血が気に入っただけだ!彼はあなたを次の供物にするつもりだ」
私を説得したつもりのこいつは徐々に近づいてきた、愚かにも私が彼の後ろに隠されてた毒ナイフに気づいていないと思ってたようだ。
赤ワインは潔癖症で、服に自分の血が付いたことで顔を崩して、生臭い匂いがする魚のスープが嫌いな奴だ。
それに、私はそのもっともいい年で死んだ女の子にあったことがある。
彼女は恋するような目で彼を見ていた。彼の赤い目にも優しい情緒が流れていた。
奇襲が失敗したこいつが身を躍らせて私の両剣を躱した。彼の笑顔がますます怪しくなった。
次の瞬間彼は壁の仕掛けを引いた。すぐ、私達の間から火の壁が燃え上がった。
「なぜ私を信じない……彼がどれだけ血を欲しているのか知っているはずだ……」
「私がどれだけ彼が嫌いなのか知っているか?」
「もちろん知っている!だから僕がやっている事はあなたのためにもなることだ!」
「なら……一人を嫌うために、その人のことをどれだけ理解しなければならないのか分かってるのか?」
「……何故あいつのことばかり、僕じゃ駄目なのか?私はただあなたのために!」
「そんなものは要らない。彼は私の聖剣騎士団のメンバーで私の舎弟だ。そんなくだらない理由で彼を、私を挑発することは許さない」
火が木製の家具に蔓延し、ますます勢いを増した。火の後ろで深く考え込んでいる奴を見て、私は思わず眉を顰めた。
彼は城の隠し通路を引き開けて、理解できない目つきでこっちを長く見たら、隠し通路に潜り込んだ。
長年の直感が私に教えた、そいつは見た目通りに単純な奴ではないと。そいつに関わったらろくなことにならないと。
だが、たとえどんなことになろうと、私の容認限度を超えることだけは許さない。
Ⅴ ビーフステーキ
(※誤字を一部編集者の判断で変更して記載しています)
ビーフステーキは1人の騎士によって召喚された。
それは金髪碧目で、家の名声も高く、腕も良くて、すべての女の子の憧れになれる騎士だった。
しかし惜しいことに、その騎士の頭には生まれつきロマンチックといった神経が欠けていたようだ。
更に惜しいことに、その騎士の食霊は外見に恵まれていた。
彼に比べて、彼の御侍は八方美人といえるだろう。
この手に両剣を持って危険の中で往来していた奴は、忠実で頼れる奴で、騎士があるべきすべての品格を守っていた。
危険な堕神との対峙で真っ先に飛びかかることだけじゃなく、老人の家の屋根の水漏れを直すことも、迷子の子供の親を探すことも厭わなかった。
このように他人を助ける道をどんどん進んでいく奴だが、上手に話せる口には恵まれなかった。
「わ、私、あなたの御侍の事が好きです!ラブレターを彼に渡してもらえませんか……婚約者がいることは知ってますが……でも、これは私の気持ちです……」
「彼に婚約者がいると知ってるのにラブレターを渡すとは、不倫をしたいのか、それは許されない事だ」
「……うっ!!私、あなたが嫌いです!!」
……このように彼の機嫌を損わせた人は少なくなかった。
最も彼を憤らせた者は、彼の御侍の婚約者の家に仕えている赤ワインという名の食霊だった。
赤ワインは貴族のような教養を持つ者だが、その彼もよくビーフステーキの行為に憤り腰の長剣を抜き出す。
当然ながら、ビーフステーキも赤ワインのことがあまり好きではなかった。
赤ワインはあらゆる習慣に気を付ける人物だから、いくつかの入念な行為はかなりわざとらしいように見えた。
それに、赤ワインはよく隠し事をする。
これらが原因で、ビーフステーキは赤ワインの事が気に食わなかった。
だが、長く付き合ってきたら、ステーキはだんだんと初見の時とは違った赤ワインが見えてきた。
彼は不公平なことに立ち向かったり、善良で無垢な少女に優しくしたり、兄のように自分の御侍を見守ったりする。
これら以外にも、彼にはステーキと対等に渡り合える実力も備わっている。
このすべてが徐々に元々あった嫌悪を変えた。
彼らは一緒に座って美酒を楽しんで兄弟と呼び合ったりするようになったと同時に、以前のように剣を持って向き合って、お互い譲らなかったりもする。
でも二人は主にどうでもいいことで口喧嘩ばかりしていた。
ステーキは思いやりのある奴ではない、彼は自分の親友が細かいことで悩んでいると感じた時、彼は決して優しいとは言えない方法を選んで、彼を光に押し出した。
赤ワインはかつて自分の血液に対する執着に悩んだ、彼は自分がそのせいで他人を傷付けけてしまうのではないかと心配していた。
あの時彼の最も近くにいたステーキは、優しく説いたりしなかった、蔑んだりもしなかった、そのことを口にすることすらなかった。
まるで言う必要のない些事とでも思っていたように。
彼は静かに自分の行為で赤ワインに教えた。
私たちはそんなこと気にもしていない。お前がそこまでそのことを恐れてることの方がわけがわからない。
ある日、酔った後のステーキは赤ワインに聞いたことがあった。
「お前は、へぷっ、それを恐れているから、ずっと影に隠れてるのか、へぷっ!」
「……考えすぎだ。俺様はただ汗を掻きたくないだけだ」
赤ワインが何を言おうと、傍らで見ているジンジャーブレッドはわかってる、この世で赤ワインの感情を露わにできるのはビーフステーキだけ。
他の者は知らない、ステーキも赤ワインが原因で失態を犯したことがあった。
数多くの少女を殺害した悪魔が捕まったあの日。
彼は城の中に突っ込んだ。赤ワインが犯人に単独で上の階に呼び出されたと聞くと、怒りに満ちた叫びをあげた。
彼は赤ワインが人類に左右されるような存在ではないと分かっていたが、それでも自分を失うほど慌てた。
多分彼自身でさえよく分からなかっただろう、あの瞬間爆発した不安な情緒は一体何なのかを。
もちろん、それも彼が赤ワインを嫌っている原因の一つかもしれない。
◀ エピソードまとめへ戻る
◀ ビーフステーキへ戻る
Discord
御侍様同士で交流しましょう。管理人代理が管理するコミュニティサーバーです
参加する