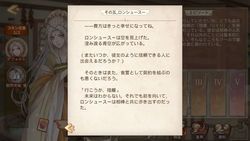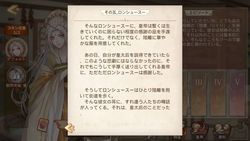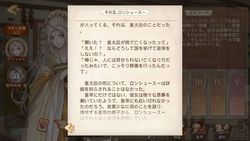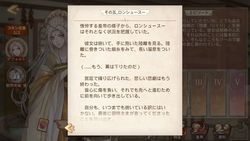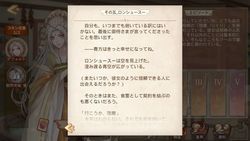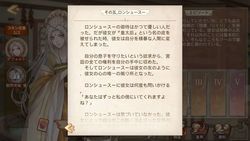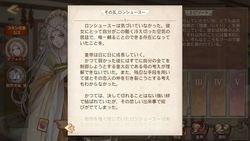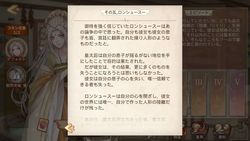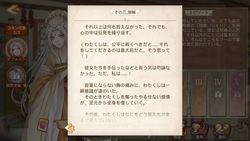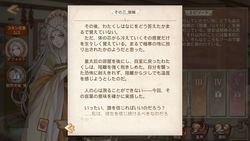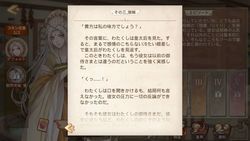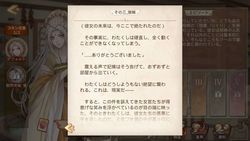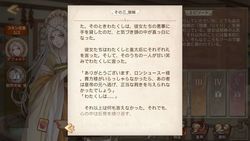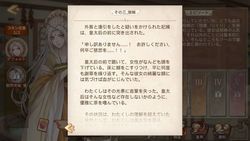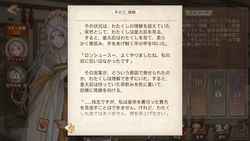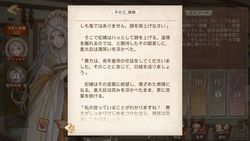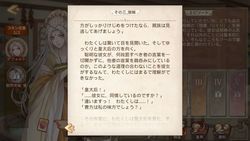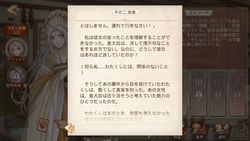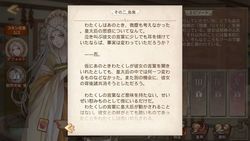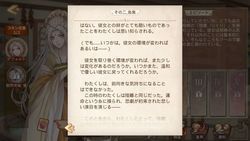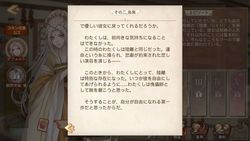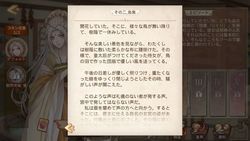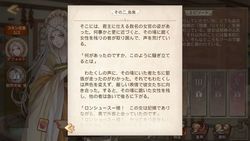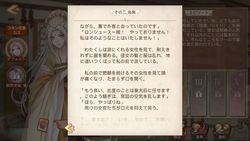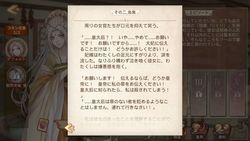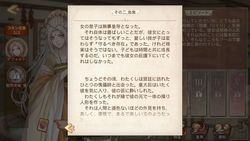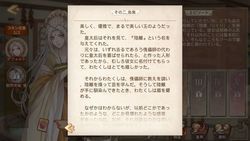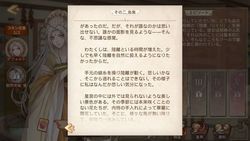ロンシュースー・エピソード
◀ エピソードまとめへ戻る
◀ ロンシュースーへ戻る
ロンシュースーのエピソード
長く宮廷で暮らしていたせいか、とても品の良い傀儡師。相棒の人形「陸離(りくり)」を操って諸国をまわっている。 彼女は相棒の人形のみを溺愛し、それ以外のことには基本的に関心を示さない。そんなところもクールで麗しいと、多くの者に慕われている。
Ⅰ 信頼
わたくしは流れ着いた街で、いつものように相棒の陸離と共に芸を見せる。
「すごい!本当に話してるみたい!」
「とても綺麗なお人形ね。どこで買ったの?」
偶然足を止めた観客たちが、わたくしと陸離の芸を見て歓声を上げる。
「この子は、わたくしが生み出しました。まだ、宮廷に仕えていた頃のことです」
わたくしは簡単に昔のことを話す。詳しい時期は告げず、あくまで『昔語り』として告げる。
かつて、皇太后の食霊として契約を交わしていたことがあること。
そんな彼女の友として、長く寄り添い、その時の歴史を垣間見たこと。
そこで……とても悲しい物語があったこと。
わたくしは息を吸った。この話をするとき、いつも胸がチクリと痛む。大分痛みは和らいできたものの、まだ自分の中に根強く残る、後悔の念。
(これは、わたくしが過去を受け止め、前に進むための儀式なのだ)
言葉に乗せると、まるで作り話のようになってしまうが、それでもわたくしにとっては紛れもない事実。
「今はこの陸離と放浪の旅をしているしがない傀儡師……そんな私が一時仕えた宮廷での一幕。よろしければ、お付き合いください」
* * *
私が皇太后の食霊として仕えはじめて暫くすると、宮廷の者たちは私の存在を認めるようになっていた。
――皇太后にとって、特別な人。
その認識が皆の中に植え付けられていたのであろう。私は食霊としては相当に良い待遇であの場所にいられたと今でも思う。
そのようにしてくれたのは、紛れもなく私の御侍であった皇太后のおかげだ。
彼女はいろいろあったが、私のことを大切にしていてくれたのだろうと思う。最近、やっとそんな風に思えてきた。
その日、私は宮中の女官に眉を引かせていた。化粧くらいは自分でやると言ったが、皇太后から「貴方は私にとって特別な者なのだから」と彼女は譲らなかった。
自分の可愛がる者が、たとえ食霊であろうと身の回りのことを自分でやらなければならないということが、どうしても彼女には耐えられなかったようだ。
他人の世話になることに、私は最後まで慣れることはできなかったが、それでも御侍である皇太后が満足してくれるなら我慢しようと思っていた。
女官が手元の粉黛を用いて、細く私の眉をなぞる。無事完成したのを見届けて、私は手を挙げて彼女を下がらせた。そして、立ち上がり両手を挙げた。
すると侍女が素早く近づいてきて、淡く光沢のある羽織を私にかけた。
「報告いたします。皇太后陛下のお食事が定刻に寝室へと届けられました。太妃様は貴方様と共にお食事をとご所望です」
侍女は静かにそう告げ、拱手の礼をする。私は片腕をあげて頭を上げさせ軽く頷いた。
私が部屋から出ると、何人もの宮殿内侍の姿があった。私が歩き出すと、彼女たちは列をなして付き従う。
頭上の装飾が一定のリズムを刻みながら揺れ動くのを多少疎ましく思いながら、私は皇太后の宮殿前へと向かった。
そして目的地に着くと、内侍がすぐさま私の到着を皇太后に報告する。
報告が済んだ内侍が戻ってきて、私を皇太后の元へと案内する。そして、皇太后の寝室のドアを厳かに上げた。私は、ゆっくりと室内へと入っていき、礼儀正しく礼をする。
「ロンシュースー、顔をあげなさい。何度も言っているでしょう?私の宮殿内では畏まらなくて良いと。貴方は私の食霊なのだから」
「礼とは法なり、いかなる理由があろうと、怠れば人より笑われてしまいましょう」
「貴方は相変わらず真面目なのね、ロンシュースー。私は疲れてしまうわ」
「御侍さまはお寛ぎください。わたくしは大丈夫ですので」
「そんなこと言われて寛げるはずないわ。意地悪よ、ロンシュースー」
ジロリ、と御侍様が恨みがましい目つきで睨む。しかしわたくしは微動だにせず、形を崩さない。
「もうっ!根競べは私の負けね。もういいでしょう?早く椅子に座って」
「はい」
わたくしは腰掛ける前に長いスカートを整え、決して失礼のないようにゆっくりと腰を下ろす。手先で軽く乱れた箇所を整え、太妃の前に座った。そのとき、ノックの音が聞こえる。
「失礼します」という声と共に、深々とお辞儀をする官僚の姿が目に入った。
「入りなさい。ドアはしっかり閉めて」
「御意」
官僚は言われるまま、ドアを閉め、鍵を掛けた。そしてツカツカと食卓の横まで移動し、一瞬わたくしに視線を向け、自信に満ち溢れた笑顔を浮かべる。
軽く会釈をしたわたくしを確認してから、官僚は跪いた。相手は勿論、皇太后陛下だ。彼女が「どうぞ」と会話を促すと、やっと彼は話し始めた。
朗々と語る官僚の話を、皇太后は澄ました顔で聞いている。
わたくしは、その場にいないものとして、黙ってその場に座っていた。とはいえ、当然官僚の言葉は耳に入ってくる。それらの会話から、彼の野心や欲望は十分に感じられた。
「お話は分かったわ、下がりなさい」
「は、はい!ではこの件については……?」
「考えておきます。王……貴方がここに留まるのは良くないわ。早く行ってください」
「はい!ありがとうございます、皇太后!感謝いたします!」
皇太后が王と名乗る官僚をこの場から退かせた後、心ここにあらずの状態になっていたわたくしを見て柔らかく微笑んだ。
「ロンシュースー、今の話を聞いていたでしょう?これが人間よ。ほんの数十年生きるために、あれほどの悪態を晒すのです。それで国が危険に晒されようとも、民の命が犠牲になろうとも……まるで厭わない。幼い我が子のためにも、あのような虫は――払わねば」
「ならば何故皇太后は……」
「黙って聞いていたのかと? そうしなければ、彼の目的を聞き出すことはできなかったわ。ロンシュースー、こんな醜い宮廷において、私が唯一信頼を置けるのは、貴方と息子だけよ」
そこで一息ついて、皇太后は再び話し出す。
「だから、お願い。貴方が私についていてくれる限り、私は貴方に万人が羨む名誉と地位を与えましょう」
「わたくしは皇太后陛下の食霊です。わたくしが尊ぶのは皇太后陛下のみ。この世界において、皇太后陛下の傍以外で、いったいどこに行き場がありましょう?」
「ありがとう……それなら良いのよ」
その時のわたくしは、人の心の複雑さをまだ理解できていなかった。どれだけ厚い信頼があっても、誤解が生まれたら、少しづつ崩れていく。
どれだけ強い絆であっても、次第に脆くなっていく。
信じたいと思えば思うほど、現実は辛くなる……そんな悲しい現実を、わたくしは痛いほどに実感している。
それでも信じたい想いがあるのだと――過去を思い出すたびにわたくしは考えていた。
Ⅱ 告発
わたくしの御侍さまは当時、朝廷の皇后だった。彼女はかつては温和で優しい女性だったが、母となったことで強い女性にならざるを得なかった。
この弱肉強食の宮廷内で、彼女はまだ幼い我が子の皇太子を守るため、険しい道を歩いてきた。それは理解を得難いものであったが、ただ一つ幸運だったのは――彼女は成功したのだ。
前皇帝の死去は突然で、あの時の御侍様が一体どれだけの苦労をして、自身の子を皇帝の地位まで押し上げたのかわたくしは知らない。
どうであれ、御侍さまの庇護があって、彼女の息子は無事皇帝となった。
それ自体は喜ばしいことだが、彼女にとってはそうなってもずっと、愛しい我が子は変わらず『守るべき存在』であった。けれど現実はそうではない。子どもは時間と共に成長するのだ。いつまでも彼女の庇護下にいてくれはしなかった。
ちょうどその頃、わたくしは宮廷に訪れたひとりの傀儡師と出会った。皇太后はいたく彼を気に入り、彼の芸に酔いしれた。
わたくしもそれが縁で彼の元で一体の操り人形を作った。
それは人間と遜色ないほどの外見を持ち、美しく、優雅で、まるで美しい玉のようだった。
皇太后はそれを見て、『陸離』という名を与えてくれた。
元々は、いずれ去るであろう傀儡師の代わりに皇太后を喜ばせられたら、と作った人形であったから、むしろ彼女に名付けてもらって、わたくしはとても嬉しかった。
それからわたくしは、傀儡師に教えを請い、陸離を操って芸を学んだ。そうして陸離が手に馴染んできたとき、わたくしは眉を顰める。
なぜかはわからないが、以前どこかであったかのような、どこか見慣れたような感覚があったのだ。だが、それが誰なのかは思い出せない。誰かの面影を見るような――そんな、不思議な感覚。
わたくしは、陸離といる時間が増えた。少しでも早く陸離を自然に扱えるようになりたかったからだ。
手元の細糸を繰り陸離が動く。悲しいかな、そこから逃れることはできない。その様子に私はなんだか悲しい気分になった。
皇宮の中には外では見られないような美しい景色がある。その季節には本来咲くことのない花たちが、内侍の手入れによって華麗に開花していた。そこに、様々な鳥が舞い降りて、樹蔭で一休みしている。
そんな美しい景色を見ながら、わたくしは樹蔭に敷いた柔らかな布に腰掛けた。その横で、皇太后がつけてくださった侍女が、鳥の羽で作った団扇で優しい風を送ってくる。
午後の日差しが優しく照りつけ、重たくなった瞼をゆっくり閉じようとしたその時、騒がしい声が聞こえた。
このような声は礼儀のない者が発する声。宮中で発してはならない声だ。
私は眉を顰めて声の方へ向かう。するとそこには、君主に仕える数名の女官の姿があった。何事かと更に近づくと、その場に跪く女性を残りの者が取り囲んで、声を荒らげている。
「何があったのですか、このように騒ぎ立てるとは」
わたくしの声に、その場にいた者たちに緊張が走ったのがわかった。それでもわたくしは声色を変えず、厳しい表情で彼女たちに向き合った。すると、その場に跪いた女性を残し、他の者は急いで後ろに下がる。
「ロンシュースー様!この女は妃嬪でありながら、裏で外客と会っていたのです」
「ロンシュースー様!やっておりません!私はそのようなことはいたしません!」
わたくしは涙に暮れる女性を見て、耐えきれずに眉を顰める。彼女の髪と服は乱れ、地に這いつくばって私の前で涙している。
私の前で懇願を続けるその女性を見て頭が痛くなり、たまらず口を開く。
「もう良い、此度のことは皇太后に任せます。このような騒ぎは、宮廷の空気を乱します」
「ほら、やっぱりね」
周りの女官たちが口元を抑えて笑う。
「……皇太后!?いや……やめて……お願いです!お願いですから……!太妃に伝えることだけは!どうかお許しください!」
妃嬪はわたくしの足元にすがり寄り、涙を流した。なりふり構わず泣き喚く彼女に、わたくしは嫌悪感を抱く。
「お願いします!伝えるならば、どうか皇帝に!皇帝に私の罪をお伝えください!皇太后に知られたら、私は殺されてしまう!」
「……皇太后は罪のない者を貶めるようなことはしません。連れて行きなさい!」
私は彼女の言ったことを理解することができなかった。皇太后は、決して理不尽なことをするお方ではない。なのに、どうして彼女はあれほど涙していたのか?
(知らぬ……わたくしには、関係のないこと)
そうしてあの事件から目を背けていたわたくしは、暫くして真実を知った。あの女性は、皇太后が近々消そうと考えていた勢力のひとつだったのだ。
わたくしはあのとき、微塵も考えなかった。皇太后の思惑についてなんて。
泣き叫ぶ彼女の言葉に少しでも耳を傾けていたならば、事実は変わっていただろうか?
――否。
仮にあのときわたくしが彼女の言葉を聞きいれたとしても、皇太后の中では何一つ変わるものなどなかった。また別の機会に、彼女の背後諸共消そうとしただろう。
わたくしの言葉など意味を持たない。せいぜい慰みものとして傍にいるだけだ。
わたくしの言葉に皇太后が動かされることはない。彼女との絆がとても脆いものであったことをわたくしは思い知らされる。
(でも……いつかは。彼女の環境が変わればあるいは――)
彼女を取り巻く環境が変われば、また少しは変化があるのだろうか。いつかまた、温和で優しい彼女に戻ってくれるだろうか。
わたくしは、前向きな気持ちになることはできなかった。
この時のわたくしは陸離と同じだった。運命という糸に操られ、悲劇が約束された悲しい演目を演じる――
このときから、わたくしにとって、陸離は特別な存在になった。いつか彼を自由にしてあげられるように……わたくしは傀儡師として腕を磨こうと思った。
そうすることが、自分が自由になれる第一歩だと思ったからだ。
Ⅲ 策略
外客と逢引きをしたと疑いをかけられた妃嬪は、皇太后の前に突き出された。
「申し訳ありません……!お許しください、何卒ご慈悲を……!!」
皇太后の前で跪いて、女性がなんども頭を下げている。床に額をこすりつけ、平に何度も謝罪を繰り返す。そんな彼女の綺麗な額には気づけば血がにじんでいた。
わたくしはその光景に言葉を失った。皇太后はそんな女性など存在しないかのように、優雅に茶を嗜んでいる。
その状況は、わたくしの理解を超えていた。呆然として、わたくしは皇太后を見る。
すると、皇太后はわたくしを見て、柔らかく微笑み、手をあげ軽く手の甲を叩いた。
「ロンシュースー、よくやりましたね。私の目に狂いはなかったです」
その言葉が、どういう意図で発せられたのか、わたくしは理解できずにいた。すると、皇太后は持っていた茶飲みを机に置いて、妃嬪に視線を向ける。
「……残念ですが、私は皇帝を裏切った貴方を見逃すことはできません。けれど、わたくしも鬼ではありません。顔を御上げなさい」
そこで妃嬪はハッとして顔を上げる。温情を賜れるのでは、と期待したその眼差しに、皇太后は薄笑いを浮かべた。
「貴方は、長年皇帝の世話をしてくださいました。そのことに免じて、白綾を送りましょう」
妃嬪はその言葉に絶望し、青ざめた表情になる。皇太后は笑みを浮かべたまま、更に言葉を続ける。
「私の言っていることがわかりますね?貴方がしっかりけじめをつけたなら、親族は見逃してあげましょう」
わたくしは驚いて目を見開いた。そしてゆっくりと皇太后の方を向く。
聡明な彼女が、何故罰すべき者の言葉を一切聞かずに、他者の言葉を鵜呑みにしているのか。このような道理の合わないことを彼女がするなんて、わたくしにはまるで理解ができなかった。
「皇太后!」
「……彼女に、同情しているのですか?」
「違いますっ!わたくしは……!」
「貴方は私の味方でしょう?」
その言葉に、わたくしは皇太后を見た。すると、まるで感情のこもらない冷たい眼差しで皇太后がわたくしを見返す。
このときわたくしは、もう彼女は以前の御侍さまとは違うのだということを強く実感した。
「くっ……!」
わたくしは口を開きかけるも、結局何も言えなかった。彼女の圧力に一切の反論ができなかったのだ。
そもそも彼女はわたくしの御侍さまだ。彼女に逆らうなど、わたくしの中にそのような選択肢は存在していなかった。
そのとき、部屋のドアが開かれる。内侍が手に白綾を持って入ってくる。
「それを、彼女に」
そう告げた皇太后の言葉に、内侍は静かに頷き、妃嬪に手にした白綾を渡す。妃嬪はそれを受け取り、憎々しげにわたくしを睨んだ。
(彼女の未来は、今ここで絶たれたのだ)
その事実に、わたくしは硬直し、全く動くことができなくなってしまう。
「……ありがとうございました」
震える声で妃嬪はそう告げて、おずおずと部屋から出ていく。
わたくしはどうしようもない絶望に襲われる。これは、現実だ――
すると、この件を訴えてきた女官たちが得意げな笑みを浮かべているのが目の端に映った。そのときわたくしは、彼女たちの悪事に手を貸したのだ、と気づき頭の中が真っ白になった。
彼女たちはわたくしと皇太后にそれぞれ礼を言った。そのうちの一人が甘い笑みでわたくしに言った。
「ありがとうございます、ロンシュースー様。貴方様がいらっしゃらなかったら、あの者は皇帝の元へ逃げ、正当な裁きを与えられなかったでしょう」
「わたくしは……」
それ以上は何も言えなかった。それでも、心の中は反発を繰り返す。
(わたくしは、公平に裁くべきだと……それをしてくださるのは皇太后だと、そう思って!)
彼女たちを手伝ったなどと言う気は勿論なかった。ただ、わたくしは……!
言葉にならない胸の痛みに、わたくしは一瞬意識が遠のいた。
そのときわたくしを襲ったやるせない感情が、足元から全身を侵していく。
その後、わたくしはなにをどう答えたかまるで覚えていない。
ただ、体の芯から冷えていくその感覚だけを生々しく覚えている。まるで極寒の地に放り出されたかのようだと思った。
皇太后の部屋を後にし、自室に戻ったわたくしは、陸離を強く抱きしめた。自分を襲った恐怖に耐えきれず、陸離から少しでも温度を感じようとしたのだ。
人の心は測ることができない――今回、その言葉の意味を確かに実感した。
いったい、誰を信じればいいのだろう?
……わたくしは、彼女を信じ続けるべきなのだろうか?
Ⅳ 終焉
「仮によからぬことがあったとしても、それを他人にどうこうされたくなどなかった……私の預かり知れぬところで――このような扱いを受けさせたくなかった」
「……皇帝」
あのとき、わたくしは身を挺してでも彼女を守るべきだったのだろうか。
御侍さまのしたことに、わたくしは納得している訳ではない。
(御侍さまは、妃嬪の権力が邪魔だった。だから、今回の件を利用したに過ぎない)
男女の蜜事が実際にあったかどうかは、調べられることもなかった。それを理由に、彼女とその一族の権力を奪いたかっただけだ。
「母上は言うだろう。彼女は私の仇になると。そうしていつまでも私を縛り続けるつもりなのだろう?」
「わ、わたくしは、知りません」
「知らないはずはない!お前がいなければ、今回このような事件は起きなかった!」
「それは……!」
彼の一言一言が私の胸を打つ。私は何か言いたかったが、この場で言っても何の意味もないと思った。
「たとえ母上であっても、このような無慈悲な仕打ち、許す訳にはゆかぬ」
服の袖を強く握り、大切な者を失った皇帝に、わたくしは深く息を吸い込んだ。
「……皇帝」
「なんだ」
その決断はわたくしにとって大きかった。今までしたことがないことだが、もうこれ以上現状を受け入れ続けるのは苦しすぎた。
だから――わたくしは、勇気をもって皇帝に言った。
「どうか、温情を。皇太后と相談してきます」
「……相談する?」
「あなたはもう大きくなりました、これらのことは、今後貴方が決断するべきだと」
「なんの冗談だ? お前は母上の食霊だろう」
「……この件において、わたくしに非があることは重々承知しております。そのことを踏まえて、これがわたくしに唯一できることと思いました」
皇帝はまっすぐにわたくしを見据える。わたくしは一呼吸おいて、言葉を付け加える。
「ぶしつけなお願いをお許しください。皇帝、どうか彼女も責めないであげてください。彼女は貴方を守るのに必死だっただけなのです」
「お前の同情なぞいらぬ」
「同情などではありません。これはわたくしからのお願いです。どうか今一度、機会をくださいませ。皇太后にも言い分があると思うのです」
しかし、皇帝は答えない。わたくしは跪いて、床に額を擦らせるほどに深く頭を下げて「どうか……!」と懇願する。
(まるで――あの日の彼女のようだ)
わたくしは、あのとき彼女を助けなかったことを今更ながらに後悔した。
「……わかった。面を上げよ」
苦しそうに皇帝が呟いた。彼も彼女の最後は聞き及んでいるだろう。目を伏せて、その手を震わせていた。
「これが母上に与える最後の機会だ。何故このようなことをしたのか……納得できる理由があってほしいものだな」
皇太后はわたくしを月見に招いた。広大な宮廷において、彼女と月を見ながら話ができるのはわたくしだけだった。
わたくしは陸離を傍らに置き、皇太后の隣に座る。彼女はわたくしに自分の好きな甘味を勧めながら微笑んだ。
「可笑しなことを言うのね。まるでお嫁さんから懇願されてるみたい。もしかして、恋人が欲しいの? だったらそう言ってくれればいいのに。私がなんとかしてあげます。大丈夫、あなたの面子は私が保証するわ」
その優し気な言葉に、わたくしは軽く微笑み返した。だが、握った手には力がこもり、ぎこちない笑顔になってしまう。
「いいえ、わたくしは恋人などいりません。皇帝ですら自分の恋人を守れないというのに、それ以外の者に何ができるでしょう。わたくしには陸離がいれば十分です」
「……ロンシュースー、何が言いたいの。私が……先の事で手を出し過ぎたというの?」
皇太后は体を震わせ、大きく目を見開きわたくしを睨む。
「いいえ。ただ、皇帝はもう大人になりました。ですから皇太后陛下も……それに先の件も、あそこまでする必要はなかったのでは」
「そう……わかったわ。貴方は私の味方ではないのね? 貴方さえも……!」
「違います!ただ皇太后陛下に聞きたかったのです……」
「黙りなさい!誰か!ここに来て頂戴!ロンシュースーの手足を縛って、寝室に閉じ込めてしまいなさい!私の許可がない限り、決して出してはなりません!」
「皇太后陛下!」
「総て……総て私のものよ!誰にも渡さない……!まだ無知なあの子のために、いろいろしてあげたのに……そうよ!あの子にだけじゃない、貴方にも……いろいろなことを……!なのにどうして……どうしてなのよ……!!」
わたくしは駆け付けた者たちに囚われた。抵抗はできない。叫び惑う皇太后を見て、言葉を失ってしまった。
わたくしにはもうわからなかった。何が正しくて、何が間違っているのか――
あの時、わたくしには叫び惑う皇太后の悲しみを理解することはできなかった。
この場所で、唯一わたくしが信頼していた御侍様はもういない。
彼女とわたくしの心は……あの時点でとっくにもう離れていたのだ。
部屋に閉じ込められていた日々に苦痛はなく、皇太后はわたくしを裁いたりはしなかった。
あれから一日もしない間に拘束は解かれた。ただ、彼女はもうわたくしと共に食事をしてはくれなかった。
(この宮殿で彼女と共に食事ができたのはわたくしだけだったのに)
あの日、彼女は唯一傍にいてくれる存在を失い、わたくしも唯一信頼できる人を失った。
わたくしは陸離を強く抱きしめる。
(わたくしには、陸離がいる……)
人間は、信用できない。卑劣な奴ばかりだ。
皇太后だって変わってしまった。もう、誰も信用したくない―――
わたくしは寝室の窓辺に腰掛け、代り映えのしない空を見上げて呆けていた。そんな時、急に部屋のドアが開いた。驚いた私はただ茫然とその声の主を見上げた。
「わかっただろう。彼女は私を守ろうなどと思っていない。お前にさえ、彼女はこんな仕打ちをした。彼女は自分の権力のためにやっているだけだ」
皇帝は高らかに笑う。その表情はとても厳しいものだった。彼も信じたかったのだ、自分の母親のことを。
(わたくしがもっとうまく皇太后を説得できていたら良かった)
そう思うも、言葉にはできない。そもそも最初からただの食霊であるわたくしが、何かを変えようなどということが烏滸がましかったのかもしれない。
どう答えたらいいのかわからず、わたくしは黙ってしまった。
「私は全てを取り戻す。彼女には相応の代価を支払わせる!」
「……」
勢いよくドアを開け放ち、皇帝が立ち去って。その背中を見て、それでもわたくしは答えを見つけ出せずにいた。
そんなある日、皇太后がわたくしの寝室へやってきた。何があったのか、戸惑いつつ彼女の言葉を待った。しかし彼女は、ただわたくしを静かに見つめているだけだった。
「あの……」
そうわたくしが声をあげると、彼女はしばらく見せていなかった優しげな笑顔を浮かべた。しかし、その笑みはどこか儚げで……悲しみを漂わせていた。
「もしかしたら私は間違っていたのかもしれないわ……貴方の言うことが、正しかったのかもしれない」
わたくしは驚いて、皇太后をまっすぐに見つめる。そんなわたくしに、皇太后はかつての優しいまなざしでこう言った。
「ロンシュースー、お茶を注いでくれない?貴方に注いでもらうお茶は、何よりも特別だったわ」
その時、激しい金属音が響き渡る。そして、切りつけられ悲痛な声を上げる者たちの声が聞こえた。
(――これはいったい……?)
私は窓から空を見上げる。そこには、いつもと変わらぬ美しい月があった。
「これが最後よ、ロンシュースー。付き合って……くれるでしょう?」
とても正常な状況ではなかった。まだ、ここまでは誰も来ないだろう。だが、それも時間の問題。
「逃げて……逃げてください、皇太后陛下! わたくしも付き添いますから!!」
わたくしは慌てて陸離に手を伸ばす。彼だけは――連れて行かねば。
「いいえ。私はどこにも行きません。ここにいます」
「でも……!」
「私の最後のお願いを、聞いてはくれませんか?」
わたくしはゆっくりと陸離を離す。
――皇太后は、もう覚悟を決めているのだ。
そんな彼女に、もうわたくしはどんな言葉も持ち合わせてはいなかった。
「ここには、あまり良いお茶はありませんが」
「いいのよ。貴方と一緒に飲むことが、大切なことだから」
わたくしは机に置かれた茶器でお茶を注いだ。激しい喧騒の中、それでも月だけは静寂だ。わたくしは、どうするべきなんだろう?
まだ逃げられるかもしれない……こんなところでお茶を飲んでいる場合ではないのかもしれない。
「どうぞ」
厳かにわたくしは、お茶を皇太后へと差し出す。彼女はとても優雅な仕草で手を伸ばし、そっと口元へと持っていく。
「初めて貴方にお茶を入れてもらったことを思い出すわ、ふふ……懐かしい」
「貴方に教えてもらって、わたくしはお茶の入れ方を学びました」
「そう……わたくしは、そういうことしか知らないから」
皇太后は小さく嘆息する。外は変わらず騒がしい。しかし彼女はまるで気にならないかのように、お茶をゆっくりと飲みほした。
「美味しかったわ。最後に、こうして貴方とお話しできて良かった」
「ま、待ってください!どこに行かれるのですか?」
「さぁ、どこでしょう?貴方は自分が最終的にどこに行くのか、知っているの?」
「わたくしはただ、貴方に幸せでいて欲しかった」
「……私は今最高に幸せよ。こうして、最後に貴方とお茶ができたんだもの」
怒号と剣、叫び声が次第に大きくなっていく。ああ、もうここにもすぐに辿り着いてしまうだろう。
「やっとあなたの言葉の意味がわかったような気がします。私はあの子なら私の苦労を理解してくれると考えていた。でも……それは私の勘違いだった」
そこで一息つき、皇太后は微笑んだ。しかし、その目元には涙がにじんでいる。
「私はこの宮廷に踊らされていたんだわ。大切な者たちをどんどん失って……気づけば取り戻せないほどの距離ができていた――」
そのとき、わたくしはやっと気づいた。陸離に特別な感情を抱いたのは、彼に自分を見ていたのだと。感情とは裏腹に、わたくしは何もできない……言われるがまま動くだけ。
(きっと――皇太后陛下も、同じだ……)
「皇太后陛下……」
「私は御侍――そう名乗ってもいいかしら?もう皇太后なんてやめるの……私はずっと皇太后という名の人形だったわ。この名前に操られて、やりたくもないことをたくさんやってしまった……もう、疲れたの」
「御侍……さま」
「貴方と会えてよかったわ」
そのとき、激しくドアが叩かれた。皇太后は毅然とドアに向かって叫ぶ。
「私はここにいます!すぐにあの子の……皇帝の元へと参ります。私は決して逃げたりはしません!」
「御侍さま、わたくしは貴方のことを愛しています。ずっと、貴方の幸せを望んでいます」
「ありがとう、ロンシュースー。私もよ……似てるわね、私たち」
二度と告げることができぬ告白を、わたくしは最後に辛うじて言葉にすることができた。
これは恋の告白ではない。もっと別の――御侍とその食霊にしかわからないであろう、絆に対する愛の言葉。
「行くわね。貴方は幸せになるのよ」
そしてドアを開け、皇太后は外に出ていく。しかし、誰も彼女には手を出さない。まだ皇太后である彼女に、最低限の敬意は払われているのだろう。
御侍さまの足音はどんどん小さくなっていく。彼女を行かせて本当に良かったのか……それはわからない。そのときはただ陸離を抱きしめ、声を殺し涙を流すことしかできなかった。
Ⅴ ロンシュースー
ロンシュースーの御侍はかつて優しい人だった。だが彼女が『皇太后』という名の皮を被せられた時、彼女は自分を横暴な人間に変えてしまった。
自分の息子を守りたいという欲求から、宮廷の全ての権利を自分の手中に収めた。
そしてロンシュースーは彼女の友のように、彼女の心の唯一の拠り所となった。
ロンシュースーに彼女は何度も問いかける。
「あなたはずっと私の傍にいてくれますよね?」
ロンシュースーは気づいていなかった。彼女にとって自分がこの酷く冷え切った空気の宮廷で、唯一頼ることのできる存在になっていたことを。
皇帝は日に日に成長していく。
かつて弱かった彼にはすでに自分の全てを制御しようとする皇太后である母の考えが理解できないでいた。また、残忍な手段を用いて彼とその恋人の仲を引き裂こうとする考えもわからなかった。
かつては、決して切れることはない強い絆で結ばれていたが、その悲しい出来事で綻びが出てきてしまった。
御侍を強く信じていたロンシュースーはあの論争の中で思った。自分も彼女も彼女の息子も皆、宮廷に翻弄された操り人形のようなものだったと。
皇太后は自分の息子が揺るがない地位を手にしたことで目的は果たされた。
だが彼女は、その結果、更に多くのものを失うことになろうとは思いもしなかった。
彼女は自分の息子の心を失い、唯一信頼できる者も失った。
ロンシュースーは自分の心を閉ざし、彼女の世界には唯一、自分で作った人形の陸離だけが残った。
あの日、皇太后が立ち去った後、皇太后がロンシュースーの前に現れることはなかった。
代わりにやってきた皇帝に、宮廷を出ていくように言われた。母の最期は穏やかであったこと、ロンシュースーが傍にいてくれたことに感謝すると、彼は伝えた。それでも、皇太后のいない今、ここに留まらないほうがいい、と彼は言った。そのことに異論はなかった。
自分はあくまで皇太后の食霊。彼女がいないいま、ここにいる理由はない。
そんなロンシュースーに、皇帝は暫くは生きていくのに困らない程度の感謝の品を手渡してくれた。それだけでなく、陸離に華やかな服を用意してくれた。
あの日、自分が皇太后を説得できていたら、このような悲劇にはならなかったのに、それでもこうして手厚く送り出してくれる皇帝に、ただただロンシュースーは感謝した。
そうしてロンシュースーはひとり陸離を抱いて街道を歩く。
そんな彼女の耳に、すれ違う人たちの噂話が入ってくる。それは、皇太后のことだった。
「聞いた?皇太后が病で亡くなったって」
「ええ!?ならどうして国を挙げて追悼をしないの?」
「噂じゃ、人には見せられない亡くなり方だったみたいで、こっそり葬儀を行ったんだって」
皇太后の死について、ロンシュースーは詳細を知らされることはなかった。
皇帝にだけではない、彼女は様々な悪事を働いていたようで、皇帝にも庇い切れなかったのだろう。言葉少なに母のことを語り、憔悴する皇帝の様子から、ロンシュースーはそれとなく状況を把握していた。
彼女は俯いて、手に抱いた陸離を見る。陸離に巻きついた細糸をみて、長い溜息をついた。
(……もう、幕は下りたのだ)
宮廷で繰り広げられた、悲しい悲劇はもう終わった。
皆心に傷を負い、それでも先へと進むために前を向いて歩き出している。
自分も、いつまでも俯いている訳にはいかない。最期に御侍さまが言ってくださったことを思い出す。
ーー貴方はきっと幸せになってね。
ロンシュースーは空を見上げた。
澄み渡る青空が広がっている。
(またいつか、彼女のように信頼できる人に出会えるだろうか?)
そのときはまた、食霊として契約を結ぶのも悪くないだろう。
「行こうか、陸離」
未来はわからない。それでも前を向いて、ロンシュースーは相棒と共に歩き出すのだった。
◀ エピソードまとめへ戻る
◀ ロンシュースーへ戻る
Discord
御侍様同士で交流しましょう。管理人代理が管理するコミュニティサーバーです
参加する-
-

-
副管理人
-
-
-

-
ななしの投稿者
136年まえ ID:gc1f1kur5話 その3
-
-
-

-
ななしの投稿者
126年まえ ID:gc1f1kur5話 その2
-
-
-

-
ななしの投稿者
116年まえ ID:gc1f1kur5話
-
-
-

-
ななしの投稿者
106年まえ ID:gc1f1kur3話。その3 最後薄くなってしまいましたが、その行で終わりです。
-
-
-

-
ななしの投稿者
96年まえ ID:gc1f1kur3話。その2
-
-
-

-
ななしの投稿者
86年まえ ID:gc1f1kur3話。お願いします。
-
-
-

-
ななしの投稿者
76年まえ ID:gc1f1kur2話。その3 お願いいたします。
-
-
-

-
ななしの投稿者
66年まえ ID:gc1f1kur2話。その2
-
-
-

-
ななしの投稿者
56年まえ ID:gc1f1kur2話です。
-